ブロックチェーン技術にはいくつかの種類がありますが、その中でも「コンソーシアムチェーン」という言葉を聞いたことはありますか。
誰でも参加できるパブリックチェーンや、一つの企業が管理するプライベートチェーンとは、また少し違った特徴を持つブロックチェーンの形態です。
「コンソーシアムチェーンって、具体的にどんな仕組みなの?」 「他のブロックチェーンと比べて、どんな良い点や気になる点があるんだろう?」 「どんな場面で使われているのかな?」
そんな疑問を持つ方もいるかもしれませんね。
この記事では、複数の組織が協力して管理・運営する「コンソーシアムチェーン(Consortium Chain) とは」何か、その基本的な仕組みから、メリット・デメリット、具体的な活用例、関連する技術まで、詳しく掘り下げて解説していきます。
特定の暗号資産への投資をおすすめするものではありません。
あくまでブロックチェーン技術の一つの形態であるコンソーシアムチェーンについて、情報収集や学習の参考として読んでいただけると嬉しいです。
コンソーシアムチェーンってどんなブロックチェーン?
まず、「コンソーシアムチェーン(Consortium Chain)とは」何か、基本的なところから見ていきましょうか。
コンソーシアムチェーンとは、特定の単一の組織ではなく、「複数の」企業や団体などが共同で「コンソーシアム(共同事業体)」を形成し、そのグループで管理・運営するブロックチェーンネットワークのことです。
パブリックチェーンのように誰でも自由に参加できるわけではありません。
プライベートチェーンのように一つの組織だけが管理するのでもありません。
ちょうど、パブリックチェーンとプライベートチェーンの中間のような性質を持っていると考えるとイメージしやすいかもしれませんね。
ネットワークへの参加やデータの閲覧、取引の承認といった活動は、コンソーシアムに参加している組織や、その組織から許可を得たメンバーに限られます。
そのため、プライベートチェーンと同様に「許可型(Permissioned)ブロックチェーン」の一種に分類されます。
この「複数の組織で管理する」「参加には許可が必要」という点が、コンソーシアムチェーンの大きな特徴です。
コンソーシアムチェーンはどうやって動いているの? その仕組み
複数の組織が協力して管理するコンソーシアムチェーンは、どのようにして成り立ち、機能しているのでしょうか。
その中心となる仕組みを見ていきましょう。
参加者が限定されているからこその、特徴的な仕組みがありますよ。
参加は承認制「パーミッションド」モデル
コンソーシアムチェーンの基本は、プライベートチェーンと同じく「パーミッションド(Permissioned)」、つまり許可制のアクセス管理です。
ネットワークに参加できるコンピューター(ノード)、データを閲覧できる利用者さん、取引を承認する役割を持つ検証者などは、すべてコンソーシアムのルールに基づいて事前に承認された主体に限られます。
誰がネットワークに参加しているかが明確であり、参加者間である程度の信頼関係が前提となることが多いです。
これにより、機密性の高い情報を扱いやすくなると同時に、ネットワークの運営ルールを参加組織間で共有し、守っていくことが可能になります。
合意形成はどうやって? 使われるコンセンサスアルゴリズム
ブロックチェーンが記録の正しさを保つためには、「コンセンサスアルゴリズム(合意形成のルール)」が欠かせませんね。
コンソーシアムチェーンでは、参加者が限定され、信頼できる組織で構成されることが多いため、パブリックチェーンで使われるプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のような、不特定多数の参加者による競争を前提としたアルゴリズムは通常用いられません。
その代わりに、プライベートチェーンと同様に、より高速で効率的なコンセンサスアルゴリズムが採用される傾向があります。
例えば、次のようなものが考えられます。
プルーフ・オブ・オーソリティ(Proof of Authority, PoA)
コンソーシアムによって信頼できると承認された特定のノード(オーソリティ)が、ブロックの承認を行います。
参加組織が分担してオーソリティの役割を担うことが多いです。
PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)系統
少数の不正なノードや故障したノードが存在しても、ネットワーク全体として正しい合意を形成できるアルゴリズムです。
参加ノード間の投票のようなプロセスで合意に至ります。
高速な取引確定(ファイナリティ)が特徴です。
Raft系統
主にノードの故障に対する耐性を重視したアルゴリズムです。
リーダーを選出して合意形成を進めます。
これらのアルゴリズムは、PoWに比べて計算資源やエネルギー消費が少なく、高速なトランザクション処理を実現できるため、企業間の連携など、効率性が求められる場面に適しています。
どのアルゴリズムを採用するかは、コンソーシアムの目的や参加組織間の合意によって決定されます。
誰がどうやって管理する? コンソーシアムによるガバナンス
コンソーシアムチェーンの運営において非常に重要なのが、「ガバナンス(統治)」の仕組みです。
単一の管理者がいるプライベートチェーンとは異なり、コンソーシアムチェーンでは、参加している複数の組織が共同でネットワークのルールを決定し、管理・運営していく必要があります。
例えば、新しい組織の参加承認、既存メンバーの権限変更、プロトコルのアップデート、問題発生時の対応方針などを、どのようにして合意形成し、決定していくのか。
そのためのルールやプロセスを、コンソーシアムとして明確に定めておくことが不可欠です。
ガバナンスの設計は、コンソーシアムチェーンの成功を左右する重要な要素となります。
参加組織間の利害関係を調整し、公平で透明性のある意思決定プロセスを確立することが求められます。
この共同管理体制が、コンソーシアムチェーンの複雑さでもあり、同時に単一組織による独断を防ぐメリットにもなり得ます。
コンソーシアムチェーンのメリットは? どんな良い点がある?
複数の組織が協力して運営するコンソーシアムチェーンには、パブリックチェーンやプライベートチェーンにはない、独自のメリットがあります。
企業間の連携などで、この形態が選ばれる理由を見ていきましょう。
プライベートチェーンより分散的、パブリックチェーンより効率的
コンソーシアムチェーンは、単一の組織が管理するプライベートチェーンに比べると、複数の組織が管理に関与するため、より分散的な性質を持ちます。
これにより、特定の管理者の意向だけでルールが変更されるリスクを低減し、より公平な運営が期待できます。
一方で、参加者が限定されているため、誰でも参加できるパブリックチェーンに比べると、合意形成のプロセスが高速で、トランザクションの処理能力(スケーラビリティ)も高い傾向にあります。
つまり、プライベートチェーンの効率性と、パブリックチェーンの分散性の、ある種の「いいとこ取り」を目指した形態と言えるかもしれません。
管理されたプライバシーと透明性
参加者が限定されているため、プライベートチェーンと同様に、機密性の高い情報を扱うことができます。
取引データへのアクセス権限を、コンソーシアムの参加組織や、さらにその中の特定の役割を持つメンバーに限定するなど、柔軟なコントロールが可能です。
しかし、コンソーシアム内では、参加組織間で共有されたルールに基づいて情報が管理されるため、単一組織が情報を独占するプライベートチェーンよりは透明性が高いと言えます。
必要な情報を関係者間で共有しつつ、外部には公開しない、というバランスの取れた運用が可能です。
共有インフラによるコスト削減と標準化
複数の組織が共同でブロックチェーンネットワークを構築・維持するため、各組織が個別にシステムを開発・運用する場合に比べて、インフラコストや開発コストを分担し、削減できる可能性があります。
共通のプラットフォーム上でデータをやり取りすることで、業界標準のデータフォーマットや業務プロセスを確立しやすくなるというメリットも考えられます。
これにより、組織間の連携がスムーズになり、業界全体の効率化に繋がることも期待できます。
規制への対応のしやすさ
参加者が特定されており、運営ルールも明確であるため、金融規制やデータ保護規制など、特定の業界に適用される規制要件に対応しやすい場合があります。
参加組織の身元が明確であるため、KYC(顧客確認)やAML(マネーロンダリング対策)などのプロセスも実施しやすいと考えられます。
コンソーシアムチェーンのデメリットや考慮すべき点は?
多くのメリットを持つコンソーシアムチェーンですが、その運用形態ならではの課題や、導入にあたって考慮すべき点も存在します。
使い方によっては、これらの点が課題になるかもしれません。
複雑なガバナンスと意思決定
複数の組織が関与するため、ネットワークの運営ルールや意思決定プロセスの合意形成が複雑になる可能性があります。
参加組織間の利害が対立した場合、意思決定が滞ったり、コンソーシアムの運営自体が困難になったりするリスクも考えられます。
公平で効率的なガバナンス体制を構築し、維持していくことが、コンソーシアムチェーンの成功のための大きな課題となります。
設立と維持のコスト・手間
コンソーシアムを設立し、参加組織間の合意を取り付け、共通のプラットフォームを構築・運用するには、相応の時間とコスト、そして労力が必要となります。
技術的な専門知識に加え、法務、契約、組織間の調整など、多岐にわたる調整が求められます。
限定的な分散性と透明性
パブリックチェーンと比較すると、参加者が限定されているため、分散性や透明性は制限されます。
コンソーシアム外部からの監視や検証は難しく、内部での談合や不正のリスクもゼロではありません。
コンソーシアムの運営が不透明であったり、一部の組織に権力が集中したりすると、その信頼性が損なわれる可能性があります。
相互運用性の課題
他のブロックチェーンネットワーク(パブリックチェーンや他のコンソーシアムチェーンなど)との連携(相互運用性)は、依然として技術的な課題が残る場合があります。
コンソーシアム内で閉じた運用は効率的かもしれませんが、外部のエコシステムとの接続が必要になった場合に、障壁となる可能性があります。
コンソーシアムチェーンはどんなことに使われているの? ユースケース
コンソーシアムチェーンは、その特性から、特に複数の企業や組織が協力して、信頼できる共通の基盤を構築したい場合に適しています。
具体的なユースケースを見てみましょう。
サプライチェーン管理とトレーサビリティ
業界全体で協力して、モノの流れを透明化する動きにコンソーシアムチェーンが活用されています。
-
業界横断的な製品追跡: 食品、医薬品、自動車部品など、複数の企業が関わるサプライチェーンにおいて、製品の生産から流通、販売までの情報を関係者間で共有し、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保します。
これにより、品質管理の向上、偽造品の防止、リコール対応の迅速化などが期待されます。
-
貿易金融プラットフォーム: 輸出入に関わる企業、銀行、保険会社、船会社などがコンソーシアムを組み、貿易書類(信用状、船荷証券など)を電子化し、ブロックチェーン上で共有することで、手続きの効率化、迅速化、コスト削減を目指します。
(例 Marco Polo, we.trade などが知られています)
金融サービス
金融機関同士の連携や、規制対応の効率化にもコンソーシアムチェーンが役立っています。
-
銀行間決済・清算: 複数の銀行が参加するコンソーシアムチェーンを構築し、銀行間の送金や証券決済などのプロセスを効率化・高速化する試みがあります。
-
KYC/AML情報の共有: 金融機関の間で、顧客確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)に関する情報を、規制に準拠した形で安全に共有するためのプラットフォームとして利用されることがあります。
保険業界
保険業界特有の複雑なプロセスにも、コンソーシアムチェーンが応用されています。
-
再保険業務の効率化: 保険会社と再保険会社がコンソーシアムを組み、契約情報や請求処理などをブロックチェーン上で共有することで、業務プロセスを効率化し、エラーを削減する取り組みがあります。
(例 B3i などが知られています)
その他(医療、不動産、エネルギーなど)
様々な分野で、複数の組織が協力するための基盤としてコンソーシアムチェーンが検討されています。
-
医療情報連携: 複数の病院や研究機関が参加し、患者の同意のもとで医療データを安全に共有・活用するための基盤として検討されています。
-
不動産取引プラットフォーム: 不動産会社、金融機関、登記所などが連携し、不動産取引に関わる情報共有や手続きを効率化する試みがあります。
-
エネルギー取引: 発電事業者、送配電事業者、小売事業者などが参加し、電力取引や再生可能エネルギー証明書の管理などを効率化するためのプラットフォームとして利用される場合があります。
これらのユースケースでは、参加組織間の信頼関係を基盤としつつ、ブロックチェーンによるデータの共有とプロセスの効率化を図るという、コンソーシアムチェーンならではの利点が活かされています。
コンソーシアムチェーンと他のチェーンタイプとの比較
コンソーシアムチェーンの特徴をより明確にするために、パブリックチェーン、プライベートチェーンと比較してみましょう。
それぞれのチェーンタイプには、得意なことと苦手なことがありますね。
-
パブリックチェーン
-
参加者: 誰でもOK(パーミッションレス)
-
管理者: いない(非中央集権)
-
透明性: 高い(基本オープン)
-
処理速度: 相対的に遅め
-
主な使い道: 暗号資産、オープンなプラットフォーム
-
例: ビットコイン、イーサリアム
-
-
プライベートチェーン
-
参加者: 管理組織の許可が必要(パーミッションド)
-
管理者: 一つの組織(中央集権的)
-
透明性: 低い(参加者限定)
-
処理速度: 速い
-
主な使い道: 企業内システム、秘密情報の管理
-
-
コンソーシアムチェーン
-
参加者: コンソーシアムによる許可が必要(パーミッションド)
-
管理者: 複数の組織(連合型)
-
透明性: 中程度(参加組織限定)
-
処理速度: 速い
-
主な使い道: 企業間連携、業界プラットフォーム
-
例: Hyperledger Fabric (構成による), R3 Corda
-
このように、コンソーシアムチェーンは、パブリックチェーンのオープンさとプライベートチェーンの管理しやすさの中間に位置し、特定の目的を持つ複数の組織が協力して信頼できるネットワークを構築するのに適した形態と言えます。
コンソーシアムチェーンの代表的なプラットフォーム例
コンソーシアムチェーンを作るためのソフトウェア基盤もいくつかあります。
企業などがコンソーシアムチェーンを構築する際に、よく使われている代表的なプラットフォームを紹介しますね。
-
Hyperledger Fabric(ハイパーレジャー ファブリック): Linux Foundationが中心となって進めているHyperledgerプロジェクトの一つで、企業向けのブロックチェーン基盤として広く利用されています。
部品を組み合わせるような柔軟な設計が可能で、参加者の役割や権限を細かく設定できます。
コンソーシアムチェーンとしての利用事例が豊富です。
-
R3 Corda(アールスリー コルダ): 主に金融業界向けに開発された分散台帳プラットフォームです。
取引の情報を関係者だけで共有するなど、プライバシー保護を重視した設計が特徴です。
企業間取引の自動化と記録に適しています。
これらのプラットフォームは、コンソーシアムがその目的に合わせてカスタマイズし、信頼できるブロックチェーンネットワークを作るための道具を提供してくれています。
コンソーシアムチェーンのこれから
コンソーシアムチェーンは、ブロックチェーン技術を特定の業界や企業グループの課題解決に応用するための、現実的かつ効果的なアプローチとして注目され、多くの実証実験や実用化が進められてきました。
今後、コンソーシアムチェーンはどのように発展していくのでしょうか。
まず、異なるコンソーシアムチェーン間や、パブリックチェーンとの連携を可能にする「相互運用性」の向上が期待されます。
これにより、特定のコンソーシアム内で閉じるのではなく、より広範なエコシステムとの接続が可能になり、活用の幅が広がると考えられます。
ガバナンスモデルの洗練も重要なテーマです。
複数の組織が公平かつ効率的に意思決定を行い、ネットワークを持続的に発展させていくための、より良いガバナンスの仕組みが模索されていくでしょう。
標準化されたフレームワークやツールの登場により、コンソーシアムの設立や運営がより容易になることも期待されます。
プライバシー保護技術の進化も、コンソーシアムチェーンの活用を後押しする可能性があります。
ゼロ知識証明などの技術を使えば、コンソーシアム内で共有する情報の範囲をより細かく制御しつつ、必要な検証を行うといった、高度な利用が可能になるかもしれません。
コンソーシアムチェーンは、企業や組織が協力してデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める上で、信頼できるデータ共有基盤として、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。
業界標準の確立や、新しいビジネスモデルの創出に貢献していく可能性を秘めています。
まとめ コンソーシアムチェーンを理解する
今回は、「コンソーシアムチェーン(Consortium Chain) とは」何か、その基本的な仕組みから、メリット・デメリット、ユースケース、他のチェーンタイプとの比較、そして将来性まで、詳しく見てきました。
コンソーシアムチェーンは、複数の組織が共同で管理・運営する許可型のブロックチェーンネットワークです。
パブリックチェーンの透明性や分散性と、プライベートチェーンの効率性や管理しやすさのバランスを取ろうとした形態と言えます。
高い処理速度や管理されたプライバシーといったメリットがある一方で、ガバナンスの複雑さなどの課題も抱えています。
企業間の連携や業界共通のプラットフォーム構築など、特定の目的を持つグループにとって、有力な選択肢となり得ます。
ブロックチェーン技術の多様な形態の一つであるコンソーシアムチェーンを理解することは、この技術が社会やビジネスにどのように応用され、価値を生み出していくのかを知る上で役立つでしょう。
免責事項
この記事は、コンソーシアムチェーンに関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定のブロックチェーンプラットフォーム、サービス、または投資戦略を推奨・勧誘するものではありません。
ブロックチェーン技術の導入や利用、暗号資産の取引には様々なリスクが伴います。
本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為の結果についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。
技術の評価や導入、投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討の上で行ってください。
必要に応じて、専門家にご相談することをお勧めします。

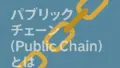
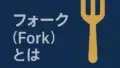
コメント