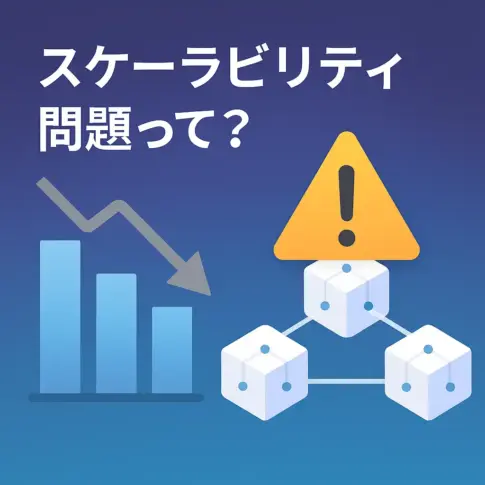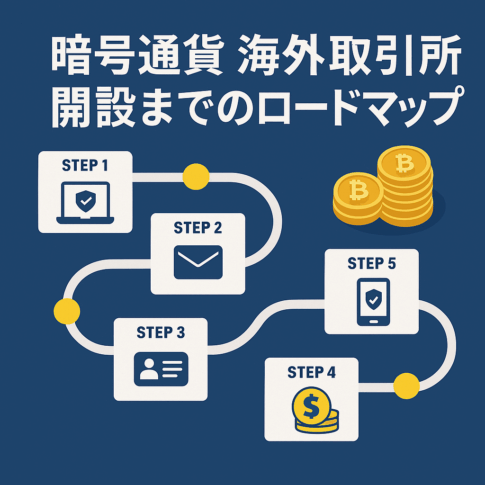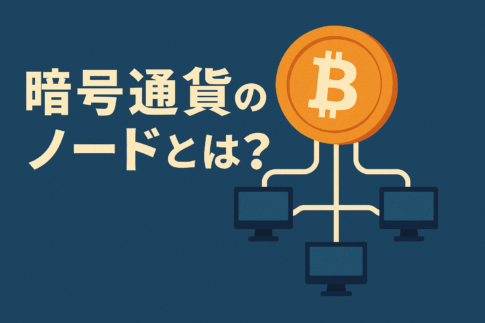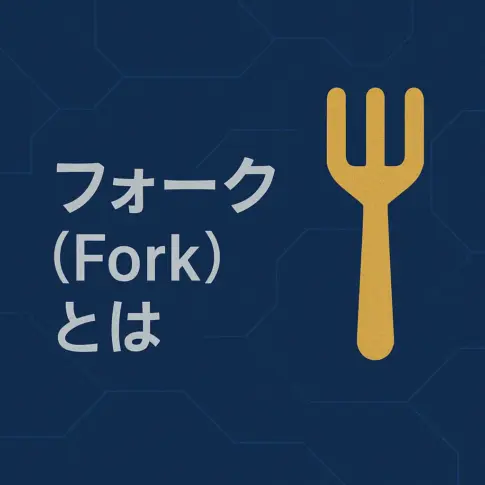私たちの暮らし、資産のあり方を変える可能性「ブロックチェーン」技術。
その中でも、「速さ」と「スムーズな処理」を目指して開発が進められているのが、
Sui(スイ)というレイヤー1ブロックチェーンであり、スマートコントラクトプラットフォームです。
この記事では、Suiが一体どんなプロジェクトで、どんなすごい技術が使われていて、私たちの未来にどんな影響を与える可能性があるのか、その仕組みや将来について、わかりやすくお伝えできればと思います。
Suiについてもっと知りたい方や、新しいブロックチェーンの世界を覗いてみたい方にとって、この記事が少しでもお役に立てると嬉しいです。
- 「Sui(スイ)」って何?次世代の速さと使いやすさを追求する新ブロックチェーンの全貌!
- ゲームもDeFiも快適に?Sui独自の「オブジェクト中心」技術と高速処理の秘密に迫る。
- 面倒なパスワード管理は不要?「zkLogin」などSuiの革新的な便利機能とは。
- SUIトークンの役割から急成長エコシステムまで、Sui経済圏の最新動向をチェック!
- 期待と課題を徹底解説!Suiが描く未来と、知っておくべき注意点。
Sui プロジェクトの始まりと目指す世界
Suiは、私たちがデジタルなものを「持つ」という体験を、もっとスムーズで、安全で、誰にでも使いやすいものに変えようと生まれたプロジェクトです。
このSuiの開発をリードしているのは、「Mysten Labs」という会社です。
Mysten Labsを作った人たちの中には、以前Meta(昔のFacebookですね)で、Diem(ディエム)というブロックチェーンプロジェクトや、Move(ムーブ)というプログラミング言語を作っていた経験豊富なエンジニアさんがたくさんいるんです。
その知識や経験が、Suiの開発にしっかりと活かされています。
Suiが目指しているのは、今までのブロックチェーンが持っていた「たくさんの処理をすると遅くなっちゃう」「使うのにお金がかかる」みたいな課題を乗り越えることです。
特に、ゲームや金融サービスみたいに、リアルタイムでの反応の速さが大事な分野で、快適に使えるプラットフォームを提供しようとしています。
開発する人にも、使う人にも、「これ、いいね!」って思ってもらえるような、Web2サービスみたいに使いやすくて、でもWeb3ならではの便利な機能がたくさん詰まった世界を目指しているんですね。
Suiを特別にしている技術のヒミツ
Suiが「高性能だね」「ユニークだね」と言われるのには、いくつかの面白い技術が使われているからなんです。
その中でも特に大事なのが、「オブジェクト中心のデータモデル」「Moveプログラミング言語」「トランザクションの並列実行」という3つのポイントです。
これらの技術が、Suiの土台をしっかりと支えています。
オブジェクト中心のデータモデル 新しいデータの扱い方
Suiの仕組みの中で、特に目を引くのが「オブジェクト中心」というデータの扱い方です。
今までの多くのブロックチェーンは、「アカウント」に情報が紐づいて管理される「アカウントベース」という形が主流でした。
ですが、Suiでは、トークンやNFT、スマートコントラクトといったデジタルなデータ一つひとつを、独立した「オブジェクト」として扱います。
それぞれのオブジェクトには固有のIDがあって、誰か一人のものとして持つことも、みんなで共有することもできるんです。
この「オブジェクト中心」の考え方のおかげで、Suiはすごい力を発揮します。
例えば、Aさんの持っているオブジェクトと、Bさんの持っているオブジェクトを同時に動かすような処理も、お互いに邪魔することなく、並行してサクサク進められるんです。
これが、Suiが高い処理能力とスピードを実現できる大きな理由の一つなんですね。
開発する人にとっても、まるで現実世界のモノを扱うみたいに、直感的にデジタルな資産をプログラムできるというメリットがあります。
Moveプログラミング言語 安全性と使いやすさを求めて
Suiで動くスマートコントラクトは、「Move」というプログラミング言語で書かれています。
Moveは、もともとDiemブロックチェーンのために作られた言語で、デジタルな資産を安全に扱ったり、誰かに渡したり、アクセスを管理したりすることに特に力を入れて設計されています。
プログラミング言語のRust(ラスト)をベースにしていて、より安全で効率的にプログラムを書けるように工夫されているんです。
Move言語のすごいところは、「資産」とか「所有権」といった大事な概念を、プログラムの中でハッキリと扱えるようにしている点です。
これによって、例えば「同じお金を二重に使っちゃう」とか「勝手にデジタルアイテムがコピーされちゃう」みたいな、ブロックチェーンで起こりがちな困った問題を、言語のレベルで防ぎやすくしています。
Suiは、このMove言語が元々持っている安全性や柔軟性を活かしつつ、さらに使いやすくパワフルにするための独自の工夫を加えています。
例えば、「プログラマブルトランザクションブロック(PTB)」という機能を使うと、1回の指示でMoveのプログラムを複数まとめて実行できたり、「ダイナミックフィールド」という機能でオブジェクトの情報を後から自由に追加したり消したりできるようになっています。
これによって、開発者さんはもっと複雑で面白いアプリケーションを作りやすくなるんですね。
並列トランザクション実行 スピードアップの鍵
Suiがとても速く処理できるもう一つの大きな秘密は、「トランザクションの並列実行」にあります。
今までの多くのブロックチェーンは、1つ、1つの取引(トランザクション)を順番に処理していくのが普通でした。
ですが、Suiは複数の取引を同時に、並行して処理する能力を持っているんです。
これは、先ほどお話しした「オブジェクト中心のデータモデル」が可能にしています。
Suiは、それぞれの取引がどの「オブジェクト」にアクセスするのかを事前に把握します。
そして、お互いに関係のない取引、例えばAさんのオブジェクトを操作する取引と、Bさんのオブジェクトを操作する取引は、同時に処理を進めることができるんです。
特に、持ち主が一人のオブジェクトや、内容が変わらないオブジェクトだけを扱うようなシンプルな取引は、ネットワーク全体での複雑な合意形成を待たずに、とてもスピーディーに完了することがあります。
Suiのテストでは、1秒間に数十万もの取引を処理できたという報告や、取引が最終的に確定するまでの時間も平均して1秒もかからないという結果が出ています。
これは、今までの主要なブロックチェーンと比べても、驚くほど速いスピードです。
この「並列実行」のおかげで、Suiはネットワークの規模が大きくなっても処理能力を上げやすい「水平スケーリング」という特徴を持っていて、将来たくさんの人に使われるようになっても対応しやすい構造になっていると言えます。
コンセンサスプロトコル みんなで合意を形成する仕組み
ブロックチェーンが正しく動き続けるためには、ネットワークに参加しているみんなで「この取引は正しいね」と合意するための仕組みが必要です。
これを「コンセンサスプロトコル」と呼びます。
Suiは、「デリゲートされたプルーフ・オブ・ステーク(DPoS)」という仕組みをベースにしながら、現在は「Mysticeti(ミスティセティ)」という進んだプロトコルを使って合意を形成しています。
Mysticetiが生まれるまでには、「Narwhal(ナーワル)」や「Tusk(タスク)」といった技術が活躍してきました。
Narwhalは、たくさんの取引情報を効率よくネットワークに広めて、それぞれの取引がどんな順番で起こったのかを整理する役割を持っています。
Tuskは、Narwhalと協力して、実際に取引の順番について合意を作り出すアルゴリズムです。
Mysticetiは、これらの技術の良いところを取り入れつつ、特に「処理の遅延を少なく、たくさんの処理をこなせるように」と最適化されています。
例えば、複数のバリデーター(取引を検証してブロックを作る人たち)が同時にブロックの候補を提案できるような仕組みになっているんです。
この専門的で洗練された合意の仕組みが、Suiが公表しているような高いパフォーマンスを実現するための重要なカギとなっています。
ユーザーにとって嬉しい機能 zkLoginとスポンサードトランザクション
Suiは、裏側のすごい技術だけではなく、私たちがWeb3のサービスをもっと気軽に使えるようにするための機能開発にも力を入れています。
その代表的なものが、「zkLogin(ズィーケーログイン)」と「スポンサードトランザクション」です。
zkLoginは、私たちが普段使っているGoogleやFacebook、TwitchみたいなWeb2サービスのIDを使って、Suiのウォレットを作ったり、Sui上のアプリケーション(dApps)にログインしたりできる機能です。
これがあれば、暗号資産にまだあまり馴染みがない方にとって、ちょっと難しかった「秘密鍵の管理」とか「シードフレーズを覚える」みたいな手間をグッと減らすことが期待できます。
スポンサードトランザクションは、アプリケーションを作っている開発者さんが、ユーザーさんの代わりに取引の手数料(ガス代)を支払うことができる機能です。
これによって、ユーザーさんはSUIトークンを事前に持っていなくても、気軽にdAppsを使い始めることができます。
これも、特に初めてWeb3に触れる方にとって、利用のハードルを大きく下げてくれる嬉しい機能と言えそうですね。
これらの機能は、Web3をもっと身近なものにして、たくさんの人がSuiのエコシステムに参加しやすくなることを目指しています。
SUIトークン Sui経済圏を支えるコイン
Suiネットワークで使われる独自のコインが「SUI」です。
このSUIトークンは、Suiの経済活動全体を支え、ネットワークを安全に保つための中心的な役割を担っています。
SUIトークンには、主に4つの大切な役割があります。
ガス代としての役割
まず一つ目は、取引を実行したり、データを保存したりする時にかかる手数料、いわゆる「ガス代」の支払いです。
Suiは効率的に動くように設計されているので、このガス代はとても安く抑えられると報告されています。
ステーキングへの参加
二つ目は、「ステーキング」という仕組みへの参加です。
SUIトークンを持っている人は、そのトークンをネットワークに預け入れる(ステークする)ことで、Suiの安全性を高める活動に参加できます。
バリデーターと呼ばれる人たちは、SUIを担保にして取引の検証作業を行い、その報酬としてSUIトークンを受け取ります。
一般のSUIトークン保有者も、自分のSUIを信頼できるバリデーターに「委任」することで、間接的にネットワーク運営に貢献し、報酬の一部をもらうことができるんです。
ガバナンスへの参加
三つ目は、「ガバナンス」つまりSuiネットワークの運営方針を決めるプロセスへの参加です。
SUIトークンを持っていると、Suiのシステムをアップグレードする時や、その他の重要な決定事項に対して、投票する権利を持つことができます。
これによって、Suiの将来の方向性に自分の意見を反映させることができるんですね。
多目的なデジタル資産として
そして四つ目は、SUIトークンが「多目的なデジタル資産」として機能することです。
お金としての基本的な役割(計算の単位、交換の手段、価値の保存)に加えて、Suiのエコシステムの中で、もっと複雑なスマートコントラクトを動かしたり、他のシステムと連携したりするための、柔軟で流動的な資産として活躍します。
SUIトークンの発行上限は100億SUIと決められています。
また、Suiには「ストレージファンド」という面白い仕組みがあって、ネットワーク上に保存されるデータが増えると、より多くのSUIがこのファンドにロックされる可能性があります。
そうなると、市場に出回るSUIの量が減るかもしれないので、SUIの価値に影響を与えるデフレ的な要素として働くかもしれないと考えられています。
広がりを見せるSuiのエコシステム
Suiブロックチェーンは、その高い性能と開発しやすい環境を武器に、どんどん仲間を増やしています。
特に、「DeFi(分散型金融)」や「GameFi(ゲームと金融の融合)」、そして「NFT(非代替性トークン)」といった分野で、たくさんの面白いアプリケーション(dApps)が生まれてきているんです。
Suiのエコシステムで注目されているプロジェクトには、例えばSuiで初めて作られた本格的な取引所システム「DeepBook(ディープブック)」や、効率的なトークン交換ができる「Cetus Protocol(セタスプロトコル)」、お金の貸し借りができる「Suilend(スイレンンド)」、NFTを売買したり新しいNFTを発行したりできる「BlueMove(ブルームーブ)」などがあります。
これらのプロジェクトは、Suiブロックチェーンが実際にどんなことができるのか、その可能性を私たちに見せてくれています。
Suiのエコシステムがどれくらい成長しているかを見るための一つの目安として、「TVL(Total Value Locked)」という数字があります。
これは、DeFiのサービスにどれくらいの資産が預けられているかを示すもので、SuiはこのTVLがメインネットの開始以来、大きく増えていると報告されています。
ユーザーさんの活動も活発になっているようです。
さらに、SuiはWeb3の世界だけでなく、私たちが普段使っている金融システムや現実世界のサービスとのつながりも大切にしています。
例えば、ヨーロッパで実際の支払い手段としてSuiを使えるようにするためのxMoney(エックスマネー)という会社との提携や、ギリシャのアテネ証券取引所グループと一緒に、ブロックチェーンを使った新しい資金調達の仕組みを作るプロジェクトなどが進められています。
Suiの今とこれから 最近の出来事もチェック
Suiの独自トークンであるSUIは、世界中の主要な暗号資産取引所で売買されていて、多くの人々の関心を集めています。
SUIの価格は、Suiエコシステムの成長具合や新しい技術の発表、そして市場全体の雰囲気など、色々な要因で変動します。
最近では、機関投資家と呼ばれるプロの投資家さんたちからの注目も集まってきているようで、例えば、デジタル資産の運用で有名なGrayscale(グレースケール)という会社が、Suiに特化した投資信託「Grayscale Sui Trust」を作ったりしています。
Suiのエコシステムは、日々新しい技術が開発されたり、新しいパートナーシップが結ばれたりと、常に変化し続けています。
2023年5月にSuiのメインネットが本格的に動き出したことは、Suiにとって大きな一歩で、ここから本格的なエコシステムの拡大が始まりました。
一方で、良いことばかりではありません。
2025年の5月には、Sui上で人気のあった分散型取引所「Cetus Protocol」が、ハッキングの被害に遭うという残念な出来事がありました。
これは、スマートコントラクトのプログラムの弱点を突かれたものだと見られていて、一時的にSUIの価格やSui全体の預かり資産(TVL)にも影響が出ました。
CetusのチームやSui Foundation、バリデーターの人たちが協力して対応にあたり、被害を最小限に抑えようと努力したそうです。
この出来事は、Moveという安全性を重視した言語を使っていても、アプリケーションの作り方によっては問題が起こりうるということを私たちに教えてくれました。
そして、エコシステム全体でセキュリティ対策をさらに強化していくことの大切さを改めて認識させるきっかけになったと言えるでしょう。
Suiの未来図 これからどうなるの?
Suiは、今の技術をもっと良くして、もっとたくさんの人に使ってもらうために、ワクワクするような計画をたくさん持っています。
これからSuiが力を入れていこうとしている主なポイントとしては、例えば、ネットワークが混雑している時にはガス代(手数料)を自動で調整する「動的ガス料金」という仕組みの導入があります。
これによって、いつでも手数料が予測しやすくなって、ユーザーさんにとって使いやすくなることが期待されています。
他の有名なブロックチェーン、例えばEthereum(イーサリアム)やSolana(ソラナ)などとの間で、資産やデータをスムーズにやり取りできるようにするための「クロスチェーン相互運用性」の強化も進められています。
これによって、Suiの中にあるトークンの使い道がもっと広がったり、開発者さんが色々なブロックチェーンを組み合わせた新しいサービスを作りやすくなったりするかもしれません。
スマートコントラクトの安全性をさらに高めるために、「形式検証ツール」という専門的なチェックツールの導入も計画されています。
これは、プログラムに間違いがないかをより厳密に確認するためのもので、特にDeFiのようなお金を扱うサービスにとっては非常に重要です。
プライバシーを大切にしながら使えるアプリケーションや、個人のデジタルな信頼情報を管理するシステムを作るために、「ゼロ知識(ZK)インフラストラクチャ」という技術の開発も進められています。
Suiの運営方法(ガバナンス)についても、将来的には中央集権的な形から、もっとコミュニティのみんなでSuiの未来を決めていくような、分散化された形に移行していくことが計画されています。
SUIトークンを持っている人が、Suiのシステムのアップグレードや大事な方針変更に対して、投票で意見を言えるようになる予定です。
Suiが長期的に目指しているのは、デジタルな資産を世界中でスムーズにやり取りするための基盤となり、たくさんの人が当たり前に使うような分散型ウェブサービスを実現するためのインフラになることです。
この大きな目標を達成するために、Suiは一般の消費者向けの製品(例えばゲーム機など)と、プロの投資家や企業向けの高度なアプリケーションの両方をサポートしていくことや、Web2サービスのような使いやすさとWeb3ならではの便利な機能を融合させること、そして特に高い性能が求められるゲームやDeFiといった分野での活用に力を入れていくとしています。
Suiと他のブロックチェーン どう違うの?
Suiは、たくさんのレイヤー1ブロックチェーンがひしめき合う競争の激しい市場に登場しました。
Suiがどんな特徴を持っているのかを理解するために、他の有名なプラットフォームと少し比べてみましょう。
Ethereum(イーサリアム)との比較
例えば、ブロックチェーンの代表格であるEthereumと比較すると、SuiはEthereumが時々直面する「処理が遅くなりがち」「手数料が高くなりがち」といった課題を解決することを目指しています。
Suiの「オブジェクト中心モデル」や「並列実行」といった仕組みによって、理論上はEthereumよりもずっと多くの取引を、ずっと安い手数料で処理できる可能性があると言われています。
Solana(ソラナ)との比較
高速な処理で知られるSolanaも、Suiとしばしば比較されるブロックチェーンです。
Suiが使っている「Mysticeti」という合意形成の仕組みは、Solanaの「Proof-of-History」とはまた違ったアプローチを取っていて、特定の状況ではSuiの方が有利になる場面もあるかもしれません。
データの扱い方も、Suiは「オブジェクト中心」なのに対し、Solanaは「アカウントベース」という大きな違いがあります。
Aptos(アプトス)との比較
Suiととてもよく似た背景を持つのが、Aptosです。
SuiもAptosも、もともとMetaのDiemプロジェクトから生まれた兄弟のような関係で、同じMoveというプログラミング言語を使っています。
しかし、よく見ると、合意形成の仕組みや、どうやって取引を並列処理するかの方法、最初の頃にどんな分野に力を入れていたかなど、技術的な部分で大切な違いがいくつかあります。
Suiは、オブジェクト同士の関係性を見ながら並列処理を行うのに対し、Aptosは「Block-STM」というまた別の方法で並列処理を実現しようとしています。
Suiならではの強み
Suiが他のブロックチェーンと比べて「ここがユニークだ!」と言える点は、やはり「オブジェクト中心モデル」とそれによる「並列実行」、そして「Mysticeti」という高性能な合意形成の仕組み、安全性を重視してSui独自に強化された「Move言語」、さらに「zkLogin」や「スポンサードトランザクション」といったユーザーさんが使いやすい機能に力を入れていることなどが挙げられます。
これらの要素がバラバラに存在するのではなく、お互いにうまく連携して、全体として「速くて、使いやすくて、安全なプラットフォーム」を提供しようとしているのが、Suiの大きな特徴と言えるでしょう。
Suiについて知っておきたいこと 注意点も
Suiは、とても革新的で大きな可能性を秘めたプロジェクトですが、他のブロックチェーンプロジェクトと同じように、いくつか知っておきたい注意点もあります。
技術的なリスクとセキュリティ
まず、技術的な弱点やセキュリティについてです。
Suiで使われているMove言語は、安全性をとても重視して作られていますが、それでもスマートコントラクトのプログラムに間違いがあったり、設計に問題があったりすると、不正な利用の原因になることがあります。
先ほどお話ししたCetus Protocolのハッキング事件も、その一例です。
Suiの仕組みは新しくて複雑な部分もあるので、まだ見つかっていないバグが隠れている可能性もゼロではありません。
ですから、Suiの上で作られたアプリケーション(dApps)を使う時には、そのプロジェクトが信頼できるか、専門家によるチェック(監査)を受けているかなどを、ご自身でよく確認することが大切です。
市場の変動について
次に、市場の変動性です。
SUIトークンを含め、多くの暗号資産は、市場全体の雰囲気や色々なニュースによって、価格が大きく上がったり下がったりすることがあります。
また、Suiはまだ新しいプラットフォームなので、これからどれだけ多くの開発者さんやユーザーさんに使ってもらえるか、エコシステムがどれだけ成長していくかによって、プロジェクト全体の成功が左右されます。
その道のりには、不確実な部分もあるということを理解しておく必要があります。
ルールの変化に対応できるか
そして、法律やルール(規制)がこれからどう変わっていくか、という点も重要です。
暗号資産の世界は、まだ新しい分野なので、国や地域によってルールが違ったり、これから新しいルールができたりする可能性があります。
そういった変化が、Suiの成長や活動に影響を与えることも考えられます。
競争の激しさ
さらに、競争環境も見ておく必要があります。
レイヤー1ブロックチェーンと呼ばれる分野は、技術の進歩がとても速く、たくさんのプロジェクトが競い合っています。
Suiは、すでに有名なプロジェクトや、同じように新しく出てきた強力なライバルたちの中で、自分たちの良さを証明し続けなければなりません。
分散化についての議論
最後に、Suiの「分散化」についての色々な意見があることも知っておくと良いでしょう。
Suiが採用しているDPoSという合意の仕組みは、比較的少数のバリデーター(取引を検証する人たち)によってネットワークが運営される可能性があります。
この点が、「本当に十分に分散化されているの?」という疑問の声につながることがあります。
Cetusのハッキング事件の時に、バリデーターが盗まれた資産を凍結したという対応は、被害を食い止めるためには役立ちましたが、一方で「少数の人たちが勝手に取引を止めたりできるのは問題ではないか」という議論も呼びました。
Suiがこれから計画している、よりコミュニティ主導の運営体制への移行が、こういった懸念にどう応えていくのかが注目されます。
これらの注意点は、Suiに限った話ではなく、多くの新しいブロックチェーンプロジェクトに共通して言えることです。
色々な情報を集めて、ご自身でよく理解を深めることが、とても大切になります。
まとめ 「Suiの未来と私たちができること」
Suiは、「オブジェクト中心のデータモデル」や「Moveプログラミング言語」、「並列トランザクション実行」といったユニークな技術を武器に、今までのブロックチェーンが持っていた「遅い」「使いにくい」といったイメージを塗り替えようとしている、とてもエキサイティングなプロジェクトです。
特に、ゲームやDeFiといった分野での活躍が期待されていて、zkLoginのような便利な機能を通じて、もっとたくさんの人が気軽にWeb3の世界を楽しめるようになることを目指しています。
しかし、新しい技術だからこその未知のリスクや、厳しい市場での競争、そしてエコシステムをこれからもっと成熟させていくための課題も、確かに存在します。
Cetus Protocolのハッキング事件は、セキュリティ対策を常に続けていくことの重要性を私たちに教えてくれました。
Suiがこれから本当に大きな成功を収めるかどうかは、その高い技術力を、実際にたくさんの人に使ってもらえるサービスや、活気のあるエコシステムの成長に繋げられるか、そしてセキュリティや分散化といった課題にうまく対応していけるかにかかっていると言えるでしょう。
今後、Suiの計画にある新しい機能がどのように実現されていくのか、コミュニティがどのようにSuiの運営に関わっていくのか、そして現実の世界でSuiがどのように使われていくのか、その動きに注目していくと面白いかもしれません。
この記事が、Suiというプロジェクトについて、皆さんの理解を少しでも深めるお手伝いができたなら、とても嬉しいです。
暗号資産やブロックチェーンの技術は、本当に日進月歩で進化しています。
ですから、これからも色々な情報源から新しい情報をキャッチして、多角的な視点から学び続けることをお勧めします。
- Suiは、Move言語とオブジェクト中心設計により、高速処理とスケーラビリティを目指すレイヤー1ブロックチェーン。
- トランザクションの並列実行やzkLoginといった革新技術で、性能と利便性を両立。
- SUIトークンは、ガス代支払い、ステーキング、ガバナンス投票など、エコシステム内で多様な役割を担う。
- DeFiやゲーム分野でエコシステムが成長する一方、Cetus Protocolのハッキング(2025年5月)などセキュリティ課題も。
- 今後は技術改善、クロスチェーン連携、分散化を進め、主要L1としての地位確立を目指す。
【免責事項】
本記事は、暗号資産Sui(スイ)に関する情報の提供を目的としており、特定の暗号資産の購入や投資を推奨するものではありません。
暗号資産の取引は価格変動リスクを伴い、元本を失う可能性があります。
投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において行うようにしてください。
本記事の情報は、作成時点において信頼できると思われる情報に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
Suiに関する最も信頼性の高い情報は、以下の公式サイトおよび関連ページから入手できます。
- Sui公式サイト:https://sui.io/
Suiブロックチェーンの概要、特徴、エコシステム、最新ニュース、開発者向けリソースなどが提供されています。 - Mysten Labs公式サイト:https://mystenlabs.com/
Suiの開発元であるMysten Labsの公式サイトです。企業情報やSuiに関するブログ記事などが見つかります。 - Suiドキュメント:https://docs.sui.io/
開発者向けの包括的なドキュメントサイトです。Suiのコンセプト、アーキテクチャ、スマートコントラクトの書き方、APIリファレンスなどが提供されています。 - Suiブログ: https://blog.sui.io/
最新情報や技術的な解説が掲載されています。 - Sui GitHubリポジトリ:https://github.com/MystenLabs/sui
Suiのオープンソースコードが公開されており、技術的な詳細や開発の進捗を確認できます。
『ホワイトペーパーおよびリサーチペーパー』
Suiの技術的な詳細や設計思想については、以下のホワイトペーパーやリサーチペーパーで解説されています。
- Suiリサーチページ (公式サイト内):https://sui.io/research
このページには、Suiに関する複数のホワイトペーパーや学術論文へのリンクが集約されています。オリジナルのSuiホワイトペーパーやトークノミクスに関するホワイトペーパーなどが含まれています。 - Suiホワイトペーパー (直接リンクの例):https://github.com/MystenLabs/sui/blob/main/doc/paper/sui.pdf
これは、Suiの初期の設計思想や技術的アプローチについて記述された主要なホワイトペーパーの一つです。SuiのGitHubリポジトリ内にも関連文書が格納されています。
補足情報
Move言語: Suiは、Metaが開発した安全なスマートコントラクト記述言語であるMoveを採用しています。Move言語自体に関する情報も、Suiを理解する上で重要です。
コミュニティ: Suiには活発な開発者コミュニティがあり、DiscordやTelegram、フォーラムなどで情報交換が行われています。公式サイトからこれらのコミュニティへのリンクを見つけることができます。
これらの情報源を参照することで、Suiブロックチェーンの技術、エコシステム、そして将来の展望について深く理解することができるでしょう。
特に、技術的な詳細に関心がある場合は、公式サイトのリサーチページやGitHub上のホワイトペーパー、ドキュメントを参照することをお勧めします。