「ブロックチェーンってよく聞くけど、仕組みが難しそう…」
「分散型台帳(Distributed Ledger)とは、結局どういうもの?」
「暗号資産(仮想通貨)との違いは?」
「私たちの生活にどう関係あるの?」
最近よく耳にするこれらのキーワード。その中心にあるのが分散型台帳技術(DLT)という、未来を変えるかもしれない注目の技術です。
この記事では、「分散型台帳(Distributed Ledger)とは何か?」という基本から、ブロックチェーンとの違い、気になる仕組みや使い方まで、専門用語をなるべく使わずに、分かりやすく解説します。
特定の金融商品などをおすすめするものではありません。
あくまで技術について知るため、学習するための情報として、リラックスして読んでみてくださいね。
そもそも分散型台帳(DLT)ってどんな考え方?
まずは、「分散型台帳(DLT)とは」何か、その基本的なイメージをつかんでいきましょう。
すごく簡単に言うと、DLTは「みんなで同じ情報を記録して、共有し合うノート(台帳)」のような仕組みのことです。
これまでの多くのシステムでは、大切な情報、例えば銀行の取引記録などは、銀行という一つの大きなコンピューター(中央サーバー)にまとめて保管されていました。
これはこれで便利なのですが、もしその中央サーバーが故障したり、悪い人に狙われたりすると、大変なことになってしまいますよね。
そこで登場したのがDLTの考え方です。
DLTでは、情報を一箇所に集めるのではなく、ネットワークに参加しているたくさんのコンピューター(「ノード」と呼びます)に、同じ情報をコピーして分散させて持ち合います。
新しい情報(例えば、誰かが誰かにお金を送った記録など)が追加されるときは、参加しているみんなで「この情報は正しいね」と確認し合ってから、全員のノートに書き加える、というルールになっています。
みんなで管理するから安心
この「みんなで情報を持ち合う」という点が、DLTの大きな特徴です。
特定の誰か一人に頼るわけではないので、どこか一つのコンピューターが動かなくなっても、他のコンピューターが動いていれば、システム全体が止まってしまう心配が少なくなります。
これを「分散性」と呼んだりします。
中央の管理者がいなくても、みんなで情報をチェックし合うことで、情報の正しさを保つことができるんですね。
分散型台帳(DLT)はどうやって動いているの? その特徴を探る
では、DLTは具体的にどんな仕組みで動いていて、どんな良い点があるのでしょうか。
もう少し詳しく、その特徴を見ていきましょう。
DLTのすごさは、情報を安全に、そして正しく共有するための工夫にあります。
情報がオープン? 透明性について
DLTの種類にもよりますが、多くのDLTでは、記録された情報がネットワークの参加者に見えるようになっています。
誰がどんな取引をしたのか(もちろんプライバシーには配慮されていますが)が分かるので、不正が起こりにくいと考えられています。
これを「透明性」と言います。
ただし、企業などで使う場合には、関係者だけが見られるように設定することも可能です。
一度書いたら消せない? 不変性(改ざん耐性)の仕組み
DLTのとても重要な特徴の一つに、「一度記録された情報は、後から書き換えたり消したりするのが極めて難しい」という点があります。
これを「不変性」や「改ざん耐性」と呼びます。
これは、情報を記録する際に、「ハッシュ関数」という特殊な暗号技術が使われているためです。
ハッシュ関数は、元の情報から、その情報固有の暗号コード(ハッシュ値)を作り出す計算式のようなものです。
元の情報が少しでも変わると、全く違う暗号コードが生成されます。
ブロックチェーンの場合、新しい情報の塊(ブロック)には、その前の情報の塊の暗号コードが含まれています。
情報が鎖のようにつながっていくイメージですね。
もし誰かが昔の情報をこっそり書き換えようとしても、暗号コードのつじつまが合わなくなり、周りのみんなにすぐにバレてしまう、という仕組みになっているのです。
これにより、記録された情報の信頼性がとても高くなります。
どうやって「正しい」と決めるの? 合意形成アルゴリズム
新しい情報をノートに書き加える前に、「この情報は本当に正しいか」をみんなで確認する作業が必要だとお話ししましたね。
この確認作業のルールや手順のことを「合意形成アルゴリズム」または「コンセンサスアルゴリズム」と呼びます。
みんなが納得できるルールがないと、バラバラになってしまいますから、とても大切な部分です。
ビットコインで使われている「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」というルールが有名ですが、これは大変な計算競争をして、一番になった人が情報を書き込む権利を得る、というものです。
しかし、たくさんの電気を使うという課題も指摘されています。
そのため、最近では、特定のコインをたくさん持っている人が承認作業に参加しやすい「プルーフ・オブ・ステーク(PoS)」など、より効率的な新しいルールもたくさん考え出されています。
どのルールを使うかによって、そのDLTの得意なことや苦手なことが変わってきます。
分散型台帳(DLT)とブロックチェーンは何が違うの?
DLTの話をすると、必ずと言っていいほど出てくるのが「ブロックチェーン」という言葉です。
この二つは、どういう関係なのでしょうか。
結論から言うと、DLTは「データを分散してみんなで管理する技術」という大きな枠組みのことです。
そして、ブロックチェーンは、そのDLTを実現するための具体的な方法の一つ、と考えると分かりやすいでしょう。
ブロックチェーンは、情報を「ブロック」という箱に入れて、その箱を「チェーン(鎖)」のようにつなげていく、という特徴的なデータの管理方法を使っています。
この方法が、情報の改ざんをとくに難しくしているんですね。
しかし、DLTの中には、ブロックチェーンとは違う方法で情報を管理するものもあります。
例えば、「DAG(ダグ)」と呼ばれる技術を使ったものは、情報を鎖状ではなく、網目状につなげていくイメージです。
ブロックチェーンよりも速く情報を処理できる場合があると言われています。
ですから、「DLT」という大きなカテゴリーの中に、「ブロックチェーン」や「DAG」といった、いくつかの具体的な技術が含まれている、と理解しておくと良いでしょう。
分散型台帳(DLT)にはどんな種類があるの?
DLTは、誰でも自由に参加できるか、それとも参加に許可が必要か、といったルールによって、いくつかのタイプに分けられます。
代表的なタイプを見てみましょう。
誰でも参加OK! パブリック型DLT
「パブリック」は「公共の」という意味ですね。
パブリック型DLTは、インターネットにつながっていれば、基本的に誰でも自由にネットワークに参加できるタイプのDLTです。
特別な許可はいりません。
ビットコインやイーサリアムなどがこのタイプです。
情報がとてもオープンで、特定の管理者がいないのが大きな特徴です。
自由度が高い反面、誰でも参加できるので、ルール作り(合意形成アルゴリズム)をしっかりして、不正が起きないように工夫する必要があります。
参加者が多いと、情報の処理に少し時間がかかることもあります。
参加者を限定! プライベート型・コンソーシアム型DLT
こちらは、ネットワークに参加するために「許可」が必要なタイプのDLTです。
プライベート型は、一つの会社や組織が管理していて、その組織内の人や、許可された人だけが参加できます。
社内システムのようなイメージですね。
コンソーシアム型は、複数の会社や組織がグループ(コンソーシアム)を作って、共同で管理するタイプです。
例えば、いくつかの銀行が集まって作る決済システムなどが考えられます。
許可型DLTの良い点は、参加者が信頼できるメンバーに限られているため、情報の処理が速く、効率が良いことです。
企業の秘密情報などを扱うのにも向いています。
ただし、管理者がいるため、パブリック型ほどの完全なオープンさはありません。
このように、DLTにはいくつかのタイプがあり、利用する目的や、どんな情報を扱いたいかに合わせて、最適なものが選ばれています。
分散型台帳技術(DLT)を使うと、どんないいことがあるの?
DLTを活用することで、これまでのやり方では難しかった、たくさんのメリットが生まれると期待されています。
一体どんな良い点があるのでしょうか。
安全性が高まる!
データが分散して保管され、暗号技術で守られているので、ハッキングやデータの書き換えがとても難しくなります。
一つの場所が狙われても、システム全体がダウンしにくいのも安心ですね。
情報が分かりやすくなる!
参加者みんなで同じ情報を共有するので、取引のプロセスなどが(許可された範囲で)とてもクリアになります。
「あの情報は今どうなっているんだろう?」という疑問が減り、お互いの信頼関係を築きやすくなります。
手続きが速く、楽になる!
これまで、お金のやり取りや契約などで、間に入って手続きをしてくれる銀行などの「仲介役」が必要な場面が多くありました。
DLTを使うと、この仲介役をなくしたり、役割を減らしたりできる可能性があります。
当事者同士で直接やり取りができるようになるので、手続きにかかる時間や手間を大幅に減らせるかもしれません。
特に、海外とのやり取りなどでは、効果が大きいと期待されています。
「スマートコントラクト」という、あらかじめ決めたルール通りに自動で契約などを実行してくれるプログラムを使えば、さらに便利になります。
コストが安くなるかも!
仲介役がいなくなれば、その手数料も不要になりますね。
書類のやり取りや、システム間の情報の突き合わせといった作業も減らせるので、全体的なコストを抑えられる可能性があります。
モノの流れが追いかけやすくなる!
製品がどこで作られ、どのように運ばれてきたか、といった履歴を正確に記録し、後から追いかけることができます。
これを「トレーサビリティ」と言います。
例えば、食品が安全なルートで運ばれてきたかを確認したり、ブランド品が本物かどうかを証明したりするのに役立ちます。
良いことずくめに見えるDLTですが、まだまだ新しい技術なので、解決すべき課題や、注意しておきたい点もいくつかあります。
一度に処理できる量に限界? スケーラビリティ問題
特に、たくさんの人が利用するパブリック型のDLTでは、一度に処理できる情報の量に限りがあり、処理に時間がかかってしまうことがあります。
これを「スケーラビリティ問題」と呼びます。
この問題を解決するために、処理能力を上げるための様々な技術開発が進められています。
ルール作りが追いついていない? 法規制とガバナンス
DLTを使った新しいサービスが次々と生まれていますが、それに関する法律やルール作りが、まだ十分に追いついていない面があります。
国によってルールが違うこともあります。
また、特定の管理者がいないネットワークで、どうやってみんなでルールを決めて、運営していくか(ガバナンス)も、試行錯誤が続いています。
他のシステムと繋がりにくい? 相互運用性
いろいろな種類のDLTプラットフォームがありますが、違うプラットフォーム同士で、スムーズに情報をやり取りするのが難しい場合があります。
これを「相互運用性」の課題と言います。
違うシステム同士をつなぐ技術も開発されていますが、まだ標準的な方法が確立されているわけではありません。
電気の使いすぎ? エネルギー消費
ビットコインなどで使われている一部のルール(PoW)は、たくさんの計算をするために、多くの電気を消費することが問題視されています。
環境への影響を心配する声もあります。
そのため、より少ないエネルギーで動く新しいルール(PoSなど)への移行や、省エネ技術の開発が進められています。
ちょっと難しい? 技術的な複雑さ
DLTの仕組みは、まだ少し専門的で、誰にでもすぐに理解できるというわけではないかもしれません。
使いこなすためには、専門的な知識が必要になる場面もあります。
もっと簡単に使えるように、技術者さんたちが日々工夫を重ねています。
プライバシーは大丈夫?
パブリック型DLTでは情報がオープンになることが多いですが、個人のプライバシーに関わる情報などをどう守るか、という点はとても重要です。
情報を暗号化して、関係者以外には見えなくする技術なども開発されており、透明性とプライバシーのバランスをどう取るかが考えられています。
分散型台帳技術(DLT)はどんなことに使われているの? 具体例を見てみよう
DLTは、すでに私たちの身の回りの様々な分野で、実際に使われ始めています。
どんな場面で活躍しているのか、いくつか例を見てみましょう。
お金の世界(金融サービス)
海外へのお金の送り: これまで時間や手数料がかかっていた海外送金が、DLTを使うことで、より速く、安くできるようになるかもしれません。
株などの取引: 株などの売買や名義変更といった手続きを、DLT上で行うことで、もっとスムーズで安全にしようという動きがあります。
貿易のお金のやり取り: 貿易ではたくさんの書類が必要ですが、これをデジタル化してDLTで共有することで、手続きを簡単にしようとしています。
新しい金融サービス(DeFi): 銀行などを介さずに、個人同士でお金の貸し借りや交換ができる、新しい金融サービスの仕組みもDLTから生まれています。
モノの流れを管理(サプライチェーン)
食べ物の安全: 野菜やお肉がどこで生産され、どう運ばれてきたかの情報をDLTに記録すれば、お店でスマホをかざすだけで、安全な食品かどうかを確認できるようになるかもしれません。
お薬の管理: 偽物の薬が出回るのを防ぐために、薬が工場から患者さんの手元に届くまでの流れをDLTで管理する試みがあります。
ブランド品の証明: 高級バッグや時計などが本物であることを証明するために、DLTが使われることもあります。
健康や医療の分野(ヘルスケア)
自分の健康記録: 病院の診察記録などを、安全な形で自分で管理し、必要に応じてお医者さんに見せられるような仕組みが考えられています。
お薬の開発: 新しい薬を作るための臨床試験(治験)のデータを、正確に、改ざんできない形で管理するためにDLTが役立つと期待されています。
エネルギーの分野
電気の個人売買: 家の太陽光パネルで発電した電気を、電力会社を通さずに、近所の人と直接売り買いできるような仕組みに、DLTが使われ始めています。
そのほかにもいろいろ!
不動産の取引: 家や土地の売買に関する手続きを、もっと簡単で安全にするためにDLTを活用しようとしています。
音楽やアートの権利: 音楽やイラストなどの権利を守り、作った人(クリエイター)に正しくお金が支払われるようにするために、DLTが使われ始めています(NFTなどが関連します)。
選挙の投票: 投票結果が改ざんされるのを防ぎ、より公正な選挙を行うために、DLTを使った電子投票システムの研究が進んでいます。
デジタルな身分証明: インターネット上で、安全に自分の身元を証明するための新しい仕組み(デジタルID)にも、DLTが使われようとしています。
これらはほんの一例です。
アイデア次第で、DLTの使い道はもっともっと広がっていくでしょう。
分散型台帳技術(DLT)のこれから どうなっていくの?
分散型台帳技術(DLT)は、まだまだ進化の途中にある技術ですが、私たちの社会や経済を、より良く変えていく大きな力を持っていると言われています。
今ある課題、例えば処理速度の問題やルールの問題なども、世界中の技術者さんたちの努力によって、少しずつ解決に向かっています。
将来的には、DLTは、身の回りのモノがインターネットにつながる「IoT」や、コンピューターが自分で考える「AI(人工知能)」といった他の新しい技術と組み合わさることで、さらにすごい力を発揮するかもしれません。
例えば、たくさんのセンサーから集めた情報をDLTで安全に管理し、その情報をAIが分析して、自動で最適な判断をしてくれる、といった未来が考えられます。
スマートシティや自動運転といった、未来の社会を支える重要な技術になる可能性もあります。
また、「Web3(ウェブスリー)」という、新しいインターネットの形を作るための中心的な技術としても注目されています。
Web3は、一部の大きな会社に情報が集まるのではなく、もっと多くの人が情報をコントロールできる、分散化されたインターネットを目指す考え方です。
DLTは、そのための土台となる技術なんですね。
もちろん、新しい技術ですから、良い面だけでなく、注意すべき点や、社会全体で考えていかなければならないルール作りなども大切になってきます。
しかし、情報の信頼性や透明性を高めるDLTが、より公平で、より便利な社会を作っていく上で、重要な役割を果たしていくことは間違いないでしょう。
まとめ 分散型台帳技術(DLT)を知る第一歩
今回は、「分散型台帳(Distributed Ledger)とは」何か、その基本的な考え方から、仕組み、種類、メリットや課題、そして未来の可能性まで、できるだけ分かりやすくお話ししてきました。
DLTは、情報をみんなで分散して管理することで、セキュリティを高め、透明性を確保し、いろいろな手続きを効率的にする、とても画期的な技術です。
ブロックチェーンはその代表例ですが、DLTには他にも様々な形があります。
すでに金融や物流、医療など、多くの分野で活用が始まっており、私たちの生活をより良く、より便利に変えていく可能性を秘めています。
まだ発展途上の技術ではありますが、これからますます重要になっていく考え方ですので、ぜひこの機会に興味を持っていただけたら嬉しいです。
免責事項
この記事は、分散型台帳技術(DLT)に関する一般的な情報を提供することを目的として書かれたものです。
特定の金融商品やサービス、投資などを推奨したり、勧誘したりするものではありません。
DLTや関連技術、暗号資産などの利用や取引には、様々なリスクが伴う可能性があります。
この記事の情報を元に行ったいかなる行動の結果についても、この記事の作成者は一切の責任を負うことはできません。
技術の導入や投資などに関する判断は、ご自身の責任において、十分に情報を集め、よく検討した上で行ってください。
必要であれば、専門家にご相談することをおすすめします。




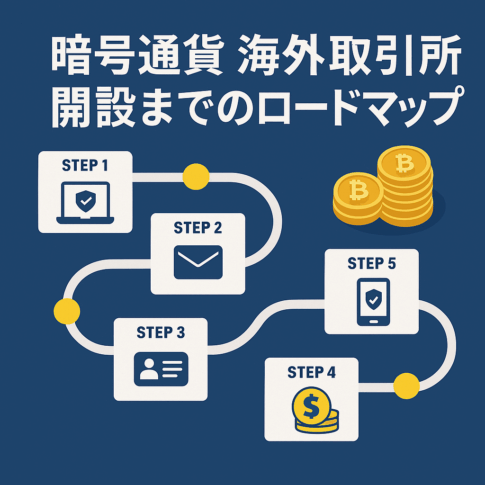


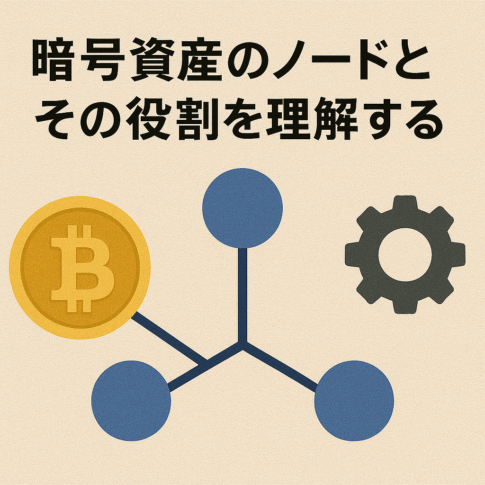
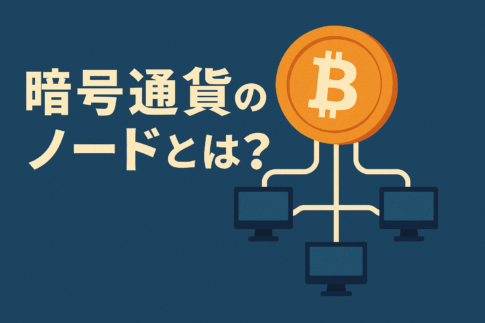

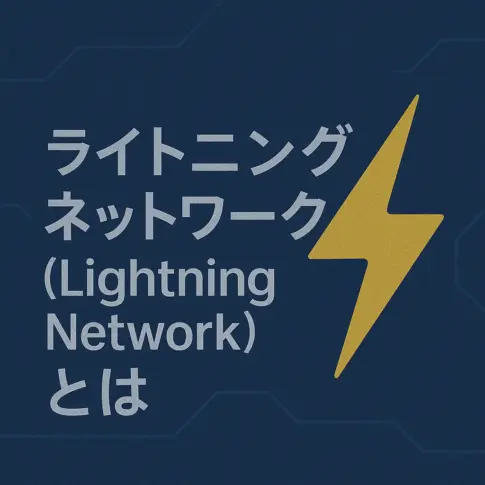




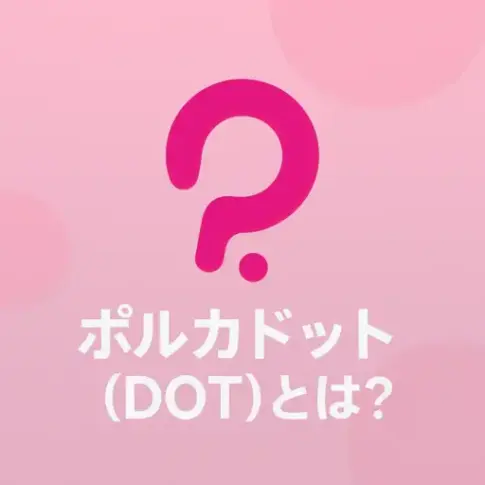
の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す