ブロックチェーン技術について情報を集めていると、「パブリックチェーン」という言葉と並んで、「プライベートチェーン」という言葉もよく見かけますね。
ビットコインやイーサリアムのように、誰でも自由に参加できるパブリックチェーンとは、どうやら少し違う特徴を持っているようです。
「プライベートチェーンって、具体的にはどんなブロックチェーンなんだろう?」 「どんな仕組みで動いていて、どんなことに使われているのかな?」 「パブリックチェーンとの違いが知りたい!」
そんな風に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、主に企業などで利用されることが多い「プライベートチェーン(Private Chain)」とは何か、その基本的な仕組みから、良い点や気になる点、実際の使われ方、他のブロックチェーンとの違いまで、詳しくお話ししていきます。
特定の暗号資産への投資をおすすめするものではありません。
あくまでブロックチェーン技術の一つの形であるプライベートチェーンについて、情報収集や学習の参考として読んでいただけると嬉しいです。
プライベートチェーンってどんなブロックチェーン?
まず、「プライベートチェーン(Private Chain)とは」何か、基本的なところから見ていきましょうか。
プライベートチェーンとは、その名前が示すように「私的」な、つまり特定の会社や組織が管理・運営しているブロックチェーンネットワークのことを指します。
誰でも自由に参加できるオープンなパブリックチェーンとは対照的に、プライベートチェーンは参加できる人が限られています。
ネットワークに参加したり、記録されている情報を見たり、新しい情報を承認したりするには、そのチェーンを管理している組織から「許可」をもらう必要があるんです。
このため、「許可型(Permissioned)ブロックチェーン」と呼ばれることもあります。
この「参加者が限定されている」という点が、プライベートチェーンの一番大きな特徴です。
この特徴が、パブリックチェーンとの様々な違いを生み出しています。
管理する組織が存在し、ネットワークのルールや参加者をコントロールできるので、これまでの会社などのシステム(中央集権型システム)に近い部分も持っていると言えますね。
プライベートチェーンはどうやって動いているの? その仕組み
プライベートチェーンがどのように動いているのか、その中心となる仕組みを見ていきましょう。
参加できる人が限られているからこその、ユニークな仕組みがありますよ。
アクセスは許可された人だけ「パーミッションド」モデル
プライベートチェーンの基本は、「パーミッションド(Permissioned)」、つまり許可制のアクセス管理です。
ネットワークに参加できるコンピューター(ノード)や、情報を見ることができる利用者さん、取引を承認する人などが、すべて管理している組織によって事前に決められています。
許可された人だけが、ネットワーク上で活動できる仕組みなんですね。
これにより、誰がネットワーク上でどんなことをしているのかを管理組織が把握しやすくなります。
会社の秘密情報など、機密性の高い情報を扱う上でのセキュリティ管理がしやすくなるというわけです。
外部の知らない人が自由に入ってくることがないので、悪意のある攻撃のリスクについても、パブリックチェーンとは違った形で対応することになります。
みんなの合意はどうやって取る? 使われるコンセンサスアルゴリズム
ブロックチェーンが記録の正しさを保つためには、「コンセンサスアルゴリズム」という、みんなで合意するためのルールが必要です。
プライベートチェーンでは、参加者が限られていて、お互いにある程度信頼できる関係にあることが多いです。
そのため、パブリックチェーンで使われるプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のような、たくさんの人が競争する複雑なルールは、必ずしも必要ではありません。
その代わりに、もっと速くて効率的なルールが使われることが多いんです。
例えば、次のようなコンセンサスアルゴリズムが、プライベートチェーンでよく利用されています。
プルーフ・オブ・オーソリティ(Proof of Authority, PoA)
事前に「この人なら信頼できる」と承認された特定のコンピューター(オーソリティ)が、ブロックの承認作業を行います。
身元がはっきりしている参加者が責任を持って作業するので、処理が速いのが特徴です。
PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)系統
ネットワークの中に、少数の悪いコンピューターや故障したコンピューターがいても、全体としては正しい合意ができるように設計されたアルゴリズムです。
メンバー間で投票のようなやり取りをして、合意を目指します。
取引の最終確定が速いのが良い点ですが、参加者が増えすぎると動きが遅くなる傾向があります。
Raft系統
主にコンピューターが故障した場合でも動き続けられることを重視したアルゴリズムです。
リーダー役を決めて、そのリーダーの指示で合意を進めます。
比較的仕組みがシンプルで分かりやすいと言われています。
これらのアルゴリズムは、PoWに比べてコンピューターのパワーや電気をあまり使わずに済みます。
取引の処理も速いので、会社の業務システムなど、効率が求められる場面に向いています。
管理者の役割は?
プライベートチェーンには、ネットワーク全体を管理・運営する一つの組織が存在します。
この管理者は、ネットワークに参加する人を承認したり、誰がどの情報にアクセスできるかを設定したり、チェーンのルールを決めたり変えたり、必要に応じて取引をチェックしたりと、広い範囲の権限を持っていることがあります。
特定の管理者がいないパブリックチェーンの考え方とは違い、はっきりとした管理主体がいることが、プライベートチェーンの大きな特徴です。
管理者がいることで、ルールの決定や変更がスムーズに進んだり、問題が起きた時に素早く対応できたりするメリットがあります。
しかし、その反面、管理者に力が集中しすぎるリスクも考えられますね。
プライベートチェーンのメリットは? どんな良い点がある?
プライベートチェーンを選ぶことには、特定の使い方をする場合に、パブリックチェーンにはない様々な良い点があります。
会社などがブロックチェーン技術を使おうとするときに、プライベートチェーンが選ばれる理由を見ていきましょう。
処理が速くてスムーズ! 高速処理と拡張性(スケーラビリティ)
プライベートチェーンは、参加者が限られていて、信頼できるコンピューターで運営されることが多いです。
そのため、みんなで合意するためのルール(コンセンサスアルゴリズム)をシンプルに、そして速くすることができます。
PoWのような時間のかかる計算競争がいらない場合が多く、取引が承認されて確定するまでの時間がとても短くなります。
これにより、1秒間に処理できる取引の数(スループット)が多くなり、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
たくさんのデータを素早く処理する必要がある会社のシステムなどには、とても有利ですね。
情報が守られる! 高いプライバシーと機密性
ネットワークに参加したり、情報を見たりできるのが、許可されたメンバーだけに限られているのがプライベートチェーンの大きな特徴です。
そのため、会社の内部情報やお客様のデータ、取引先との情報など、外部に漏れてはいけない機密性の高い情報を安全に扱うことができます。
取引の記録やプログラム(スマートコントラクト)の内容などを、関係ない人から完全に隠すことが可能です。
これは、パブリックチェーンの情報が基本的に公開されているのとは対照的ですね。
プライバシーを守りたい場合には、プライベートチェーンが有力な選択肢になります。
管理しやすい! 運営管理とガバナンスの容易さ
プライベートチェーンは、一つの管理組織がいるため、ネットワークのルールを変えたり、システムをアップデートしたり、参加者を管理したり、誰が何にアクセスできるかを調整したりといった作業を、比較的簡単かつ素早く行うことができます。
どうやって物事を決めるかのプロセスがはっきりしていて、会社のルールや法律の要求に合わせて、柔軟に運用ルールを変えることも可能です。
もし何か問題が起きた場合も、管理者が中心となって対応できます。
パブリックチェーンでは、みんなの意見をまとめてルールを変えるのに時間や手間がかかることがあるのに比べると、運営管理の面で効率が良いと言えます。
コストが抑えられるかも? コスト効率の可能性
プライベートチェーンでは、PoWのような大量の電気を使うコンセンサスアルゴリズムを使わないことが多いです。
そのため、ネットワークを維持するための運用コスト(電気代やコンピューターの費用など)を低く抑えられる可能性があります。
取引の手数料も、管理組織が決めることができるので、パブリックチェーンのように市場の混雑具合で値段が大きく変動することは少ないです。
予測可能で安定したコストで運用できる場合があるのは、企業にとっては嬉しい点ですね。
プライベートチェーンのデメリットや考慮すべき点は?
たくさんの良い点がある一方で、プライベートチェーンにはいくつかの気になる点や、導入する際に考えておくべき点もあります。
使い方によっては、これらの点が課題になるかもしれません。
管理者に力が集中? 中央集権化のリスク
プライベートチェーンは、一つの管理組織がいるため、どうしても中央集権的な性質を持ちます。
これは、管理者の考え一つでネットワークのルールが変わったり、特定の参加者にとって不利な状況になったりするリスクがあることを意味します。
もし管理者が悪意を持ったり、管理体制に問題があったりすると、ネットワーク全体の信頼性が揺らいでしまうかもしれません。
ブロックチェーンの大きな魅力である「非中央集権性(特定の管理者に頼らないこと)」が、プライベートチェーンでは限定的になってしまう点は、よく理解しておく必要があります。
透明性は低め? 透明性の制限
参加者が限られていて、情報へのアクセスも制限されていることは、プライバシーを守る上では良い点です。
しかし、その反面、透明性が低いという見方もできます。
ネットワークの外部から、記録が本当に正しいのか、ネットワークが健全に動いているのかを検証することが難しくなります。
パブリックチェーンのように「誰でもチェックできる」ことによる信頼性は、プライベートチェーンでは得にくい場合があります。
安全性は大丈夫? セキュリティに関する懸念
プライベートチェーンの安全性は、管理している組織の運用体制や、使われている技術、アクセス管理がどれだけしっかりしているかに大きく左右されます。
もし管理組織自体がサイバー攻撃を受けたり、内部の人が不正を働いたりした場合、ネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。
参加しているコンピューターの数が少ない場合、パブリックチェーンに比べて、一部のコンピューターが結託して不正を行うリスクも、相対的に高まるかもしれません。
「プライベート」という名前だからといって、必ずしも安全性が保証されているわけではありません。
適切なセキュリティ対策と、しっかりとした運用体制を作ることがとても大切です。
広がりに限界? ネットワーク効果の限定
参加者が限られているため、パブリックチェーンのように、世界中の多様な人々が参加することで新しいアイデアが生まれたり、参加者が増えるほどネットワーク全体の価値が高まったりする効果(ネットワーク効果)は、プライベートチェーンでは期待しにくい面があります。
外部のシステムと連携したり、オープンな形で多くの人と協力したりするには、制約が出てくる可能性があります。
プライベートチェーンはどんなことに使われているの? ユースケース
プライベートチェーンは、その特徴を活かして、特に会社や組織の中、あるいは特定の企業グループの間で利用が進んでいます。
具体的にどんな場面で使われているのか、例を見てみましょう。
会社の中での利用 業務効率化など
大切な書類の管理: 契約書や会社の決定事項、発明などの記録を、後から書き換えられない形で安全に記録・管理し、いつ誰がアクセスしたかを追跡できるようにします。
内部チェックやルールの遵守: 取引の記録や仕事の流れを透明かつ追跡可能な形で記録することで、内部のチェック作業を効率化したり、ルールが守られていることを証明したりするのに役立ちます。
会社資産の管理: 会社の設備や権利など、様々な資産の持ち主や移動の履歴を管理します。
モノの流れを管理 サプライチェーン管理
製品の追跡: 材料の仕入れから、製造、配送、販売までの製品の流れや品質に関する情報を、関係する会社の間で安全に、リアルタイムで共有します。
これにより、サプライチェーン全体が見えやすくなり、偽物製品の防止や、問題発生時の素早い対応、品質管理の向上などが期待できます。
金融機関での利用
銀行間の決済など: 銀行同士のお金のやり取りや、銀行内部のシステムの一部にプライベートチェーンを利用して、処理を速くしたり、コストを下げたり、リスクを減らしたりする試みがあります。
顧客情報の管理(KYC/AML): お客様の情報を安全に管理・共有し、法律で求められる確認作業(本人確認やマネーロンダリング対策)を効率的に行うために使われることがあります。
医療分野での利用
電子カルテの共有(限定的な範囲で): 患者さんの同意のもと、特定の病院グループ内などで、診療情報を安全に共有するための基盤として検討されることがあります。
プライバシー保護が特に重要視される分野ですね。
その他の利用例
会員管理やポイントシステム: 特定の会員組織の中で、ポイントを発行・管理したり、会員であることを証明したりするのに使われることがあります。
研究開発データの共有: 一緒に研究を進める会社や研究機関の間で、研究データを安全に共有・管理するために利用される場合があります。
これらの使われ方に共通しているのは、参加者が限られていて、ある程度の信頼関係があること、情報の秘密を守ることや処理の速さが重視される、といった点ですね。
プライベートチェーンと他のチェーンタイプとの比較
プライベートチェーンの特徴をよりはっきりさせるために、パブリックチェーンやコンソーシアムチェーンと比べてみましょう。
パブリックチェーン
参加者: 誰でもOK(パーミッションレス)
管理者: いない(非中央集権)
透明性: 高い(基本オープン)
処理速度: 相対的に遅め
主な使い道: 暗号資産、オープンなサービス
例: ビットコイン、イーサリアム
プライベートチェーン
参加者: 管理組織の許可が必要(パーミッションド)
管理者: 一つの組織(中央集権的)
透明性: 低い(参加者限定)
処理速度: 速い
主な使い道: 企業内システム、秘密情報の管理
例: Hyperledger Fabric (構成による), R3 Corda (一部) ※プラットフォームは構成次第
コンソーシアムチェーン
参加者: 参加組織グループの許可が必要(パーミッションド)
管理者: 複数の組織(連合型)
透明性: 中くらい(参加組織限定)
処理速度: 速い
主な使い道: 企業間の連携、業界共通の基盤
例: Hyperledger Fabric (構成による), R3 Corda
このように、それぞれのチェーンタイプには違う特徴があり、解決したい問題や目的に合わせて使い分けられています。
プライベートチェーンは、特に会社などが管理権限を保ちながら、ブロックチェーンの良い点(書き換えられない、効率が良いなど)を利用したい場合に、適した選択肢と言えるでしょう。
プライベートチェーンの代表的なプラットフォーム例
プライベートチェーン(やコンソーシアムチェーン)を作るためのソフトウェア基盤もいくつかあります。
代表的なものとしては、次のようなものが挙げられます。
Hyperledger Fabric(ハイパーレジャー ファブリック): Linux Foundationが中心となって進めているHyperledgerプロジェクトの一つで、企業向けのブロックチェーン基盤として広く使われています。
部品を組み合わせるような柔軟な設計が可能で、参加者の役割や権限を細かく設定できます。
複数の企業で使うコンソーシアムチェーンとしての利用が多いですが、プライベートチェーンとしても構築できます。
R3 Corda(アールスリー コルダ): 主に金融業界向けに開発された分散台帳プラットフォームです。
取引の情報を関係者だけで共有するなど、プライバシー保護を重視した設計が特徴です。
厳密にはブロックチェーンとは少し違う構造を持つ部分もありますが、広い意味でのプライベート/コンソーシアム型プラットフォームとして知られています。
これらのプラットフォームは、企業が自分たちのニーズに合わせてカスタマイズし、プライベートなブロックチェーンネットワークを作るための道具を提供してくれています。
プライベートチェーンのこれから
プライベートチェーンは、ブロックチェーン技術を実際のビジネスの問題解決に役立てるための、実用的な方法として、多くの企業で導入が検討されたり、試されたりしてきました。
これから先、プライベートチェーンはどのように発展していくのでしょうか。
一つの方向性として、他の種類のチェーンとの連携が強まることが考えられます。
プライベートチェーンで管理している情報を、必要に応じてパブリックチェーンや他のコンソーシアムチェーンと安全につなぐ「相互運用性」の技術が進歩すれば、プライベートチェーンの閉じた良さを保ちつつ、外部とのつながりも持てるようになるかもしれません。
プライバシーを守る技術(ゼロ知識証明など)が発展することで、プライベートチェーンの高い機密性を保ちながらも、限られた情報だけを外部に証明するような、より高度な使い方も考えられています。
クラウドサービスとの連携が進み、企業がもっと手軽にプライベートチェーンを導入・運用できる環境が整っていくことも予想されますね。
一方で、パブリックチェーンの処理能力やプライバシー機能が向上していく中で、これまでプライベートチェーンが担ってきた役割の一部が、将来的にはパブリックチェーンやその補助技術(レイヤー2ソリューション)で置き換えられる可能性も議論されています。
プライベートチェーンは、企業がブロックチェーン技術のメリットを活用するための重要な選択肢であり続けると考えられます。
しかし、技術全体の進化の中で、その役割や立ち位置は変わっていく可能性も秘めていると言えるでしょう。
まとめ プライベートチェーンを理解する
今回は、「プライベートチェーン(Private Chain)とは」何か、その基本的な仕組みから、メリット・デメリット、使われ方、他のチェーンタイプとの比較、そして将来について、詳しく見てきました。
プライベートチェーンは、特定の組織が管理し、許可された参加者だけが利用できるブロックチェーンネットワークです。
処理速度が速いこと、機密情報を守りやすいこと、管理しやすいことなどの良い点があり、会社の内部システムや特定の業界での情報共有などに活用されています。
その一方で、中央集権的になりやすいことや、透明性が限られるといった側面も持っています。
パブリックチェーンとは違う特徴を持つプライベートチェーンを理解することは、ブロックチェーン技術がどのように現実世界の問題解決に使われているかを知る上で、とても役立ちます。
どんな目的で使いたいかに合わせて、最適なブロックチェーンのタイプを選ぶことが、技術をうまく活用する鍵になりますね。
免責事項
この記事は、プライベートチェーンに関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定のブロックチェーンプラットフォーム、サービス、または投資戦略を推奨・勧誘するものではありません。
ブロックチェーン技術の導入や利用、暗号資産の取引には様々なリスクが伴います。
本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為の結果についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。
技術の評価や導入、投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討の上で行ってください。
必要に応じて、専門家にご相談することをお勧めします。


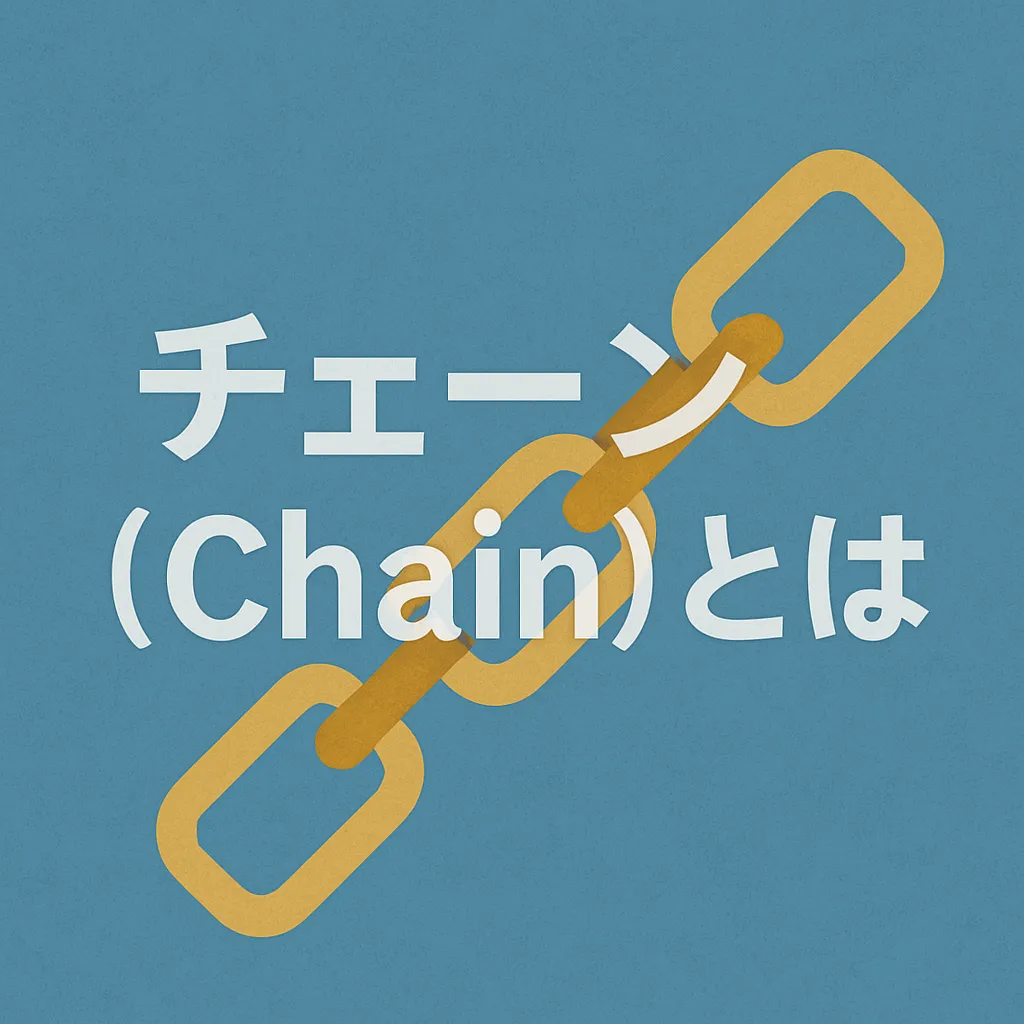

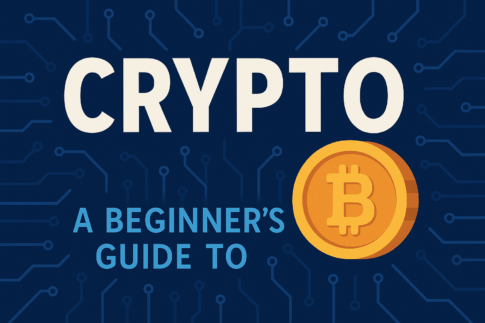
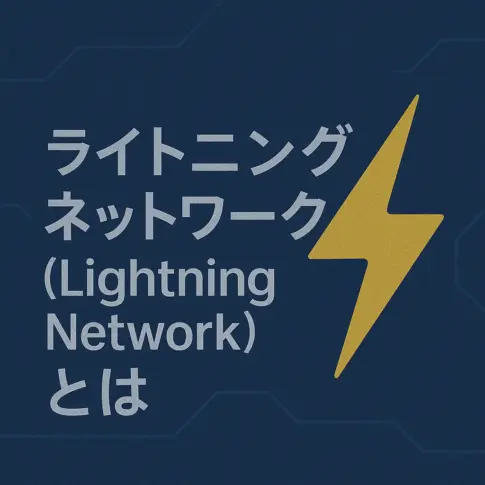

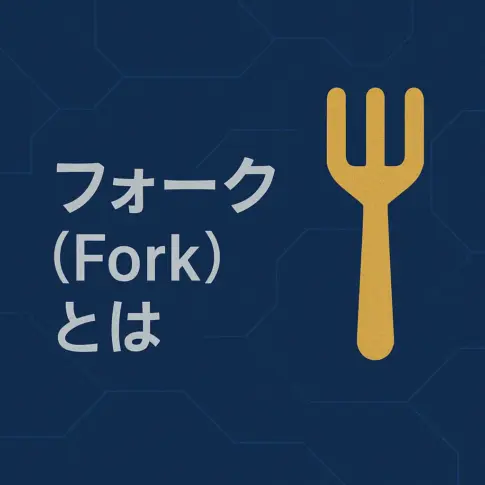







の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す