ブロックチェーン技術や暗号資産(仮想通貨)に関心を持つ中で、「ICO(アイシーオー)」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。
「Initial Coin Offering」の略で、日本語では「新規暗号資産公開」や「初期コイン募集」などと訳されます。
一時期、新しい資金調達の方法として大きな注目を集めました。
しかし、同時に様々な問題点も指摘されたんです。
「ICOって、具体的にはどんな仕組みなの?」
「どうして注目されたり、問題視されたりしたんだろう?」
「今はどうなっているの?」
そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。
ICOは、ブロックチェーンプロジェクトが資金を集めるための独特な方法でした。
その仕組みや背景、リスクを理解することは、この分野の動向を知る上で役立ちます。
この記事では、「ICO(Initial Coin Offering)とは」何か、その基本的な意味から、仕組み、目的、メリットやデメリット、そして重要なリスクや規制について、詳しく解説していきます。
特定のプロジェクトや暗号資産への投資をおすすめするものではありません。
あくまでICOという仕組みについての情報提供と、学習を目的としています。
ICO(Initial Coin Offering)とは何か? 基本的な意味を知ろう
まず、「ICO(Initial Coin Offering)とは」何か、その基本的な定義から見ていきましょう。
ICOがどんなものか、イメージをつかむところから始めますね。
新しい資金調達の方法としてのICO
ICOとは、会社やプロジェクトチームが、新しいプロジェクトやサービスを始めるために、独自のデジタルな「トークン」と呼ばれるものを新たに発行し、それを販売することによって資金を集める方法のことです。
資金は主に、ビットコインやイーサリアムといった既存の暗号資産で集められました。
株式市場で会社が新しく株を売り出すIPO(新規株式公開)に例えられることもあります。
しかし、ICOの仕組みや法律上の扱いは、IPOとは大きく異なっています。
ICOは、特にブロックチェーン技術を使った新しいプロジェクトにとって、これまでのお金の集め方、例えば銀行からの融資や投資会社からの出資などとは違う、新しい選択肢として登場しました。
インターネットを通じて、世界中のたくさんの人々から、比較的短い時間で、大きな資金を集められる可能性があるとして、2017年頃にとても大きなブームになったんです。
プロジェクトチームは、自分たちのアイデアや計画を「ホワイトペーパー」という計画書にまとめて公開します。
その計画に共感し、「これは将来性がありそうだ」と感じた人たちが、ビットコインやイーサリアムなどを送って、プロジェクトが発行する独自のトークンを買う(交換する)、というのが一般的な流れでした。
IPO(新規株式公開)との違いは?
ICOはよくIPO(新規株式公開)と比べられますが、大切な違いがたくさんあります。
IPOは、会社が証券取引所に株を上場させて、一般の投資家さんに株を売ることでお金を集める方法ですね。
IPOをするには、証券会社などが間に入り、証券取引所の厳しいチェックをクリアして、会社の詳しい財務情報などを公開する必要があります。
株を買った投資家さんは、その会社のオーナーの一部になったり(議決権)、利益の一部(配当)を受け取ったりする権利を得ます。
一方、ICOは、多くの場合、証券会社などを通さずに、プロジェクトチームが直接トークンを発行して販売します。
法律のルールや審査基準がIPOほどしっかり決まっていませんでした。
どんな情報を公開するかという基準も、プロジェクトによってバラバラでした。
ICOで発行されるトークンが持つ意味合いも様々です。
必ずしも会社のオーナーになる権利や配当をもらえる権利を表すものではありませんでした。
プロジェクトのサービスを使うための権利(ユーティリティトークン)だったり、単に将来値段が上がることを期待されるものだったりと、その内容は本当にいろいろだったんです。
このように、ICOはIPOに比べて、手軽に実施できる可能性がある反面、ルールや参加者を守る仕組みの面で、大きな課題を抱えていたと言えますね。
ICOはどのように行われる? その仕組みとプロセス
ICOが実施される際の、一般的な流れや仕組みを見ていきましょう。
プロジェクトによって細かい部分は違いますが、大まかな流れを知ることで、ICOがどんな風に行われていたかが分かります。
プロジェクトの計画とホワイトペーパーの公開
まず、ICOを行おうとするプロジェクトチームは、自分たちが作りたいプロジェクトの内容、技術的な仕組み、解決したい問題、開発のスケジュール、チームメンバーの紹介、そして発行するトークンの詳しい情報(何のために発行するか、全部でいくつ発行するか、どうやって配るか、トークンで何ができるかなど)をまとめた「ホワイトペーパー」という文書を作って公開します。
このホワイトペーパーは、プロジェクトに興味を持った人が、その内容や将来性を判断するための、とても重要な資料になります。
ウェブサイトやSNSなどを使って、プロジェクトを知ってもらうための宣伝活動も行われます。
トークンの発行と販売(トークンセール)
次に、プロジェクトチームは、ブロックチェーンの技術(イーサリアムのERC-20という規格などがよく使われました)を使って、独自のトークンを発行します。
そして、決められた期間内に、一般の人々に向けてトークンを販売します。
これを「トークンセール」や「クラウドセール」などと呼びます。
参加したい人は、指定されたアドレスにビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を送ります。
その見返りとして、プロジェクトが発行した新しいトークンを受け取る、という仕組みです。
トークンの値段は、最初から決まっている場合もあれば、オークションで決まる場合、期間中に集まったお金の総額によって変わる場合など、いろいろな方式がありました。
どれくらいの資金を集めたいか、目標金額(キャップ)を設定することもよくありました。
集まった資金の活用とプロジェクト開発
トークンセールで集まった資金は、プロジェクトチームが、ソフトウェアの開発、宣伝活動、会社の運営費用など、ホワイトペーパーに書かれた計画を実行するために使います。
トークンを買った人は、プロジェクトが成功して、トークンの価値が上がることを期待したり、そのトークンを使ってプロジェクトのサービスを利用できるようになることを期待したりします。
しかし、計画通りにプロジェクトが進む保証は全くありません。
開発が遅れたり、途中で中止されたりするリスクも常にありました。
なぜICOが行われるのか? その目的
プロジェクトチームが、銀行融資や投資会社からの出資といった従来の方法ではなく、ICOという手段を選んだ背景には、いくつかの目的がありました。
ICOならではの特性が、特定のプロジェクトにとって魅力的に見えた部分があったんですね。
どんな目的があったのか、見てみましょう。
プロジェクト開発資金の調達
一番分かりやすい目的は、プロジェクトを開発して実現するために必要なお金を集めることです。
特に、ブロックチェーン技術を使った新しい、革新的なアイデアを持つスタートアップ企業にとっては、これまでの金融の仕組みではなかなか評価されにくかったり、お金を集めるのが難しかったりする場合がありました。
ICOは、インターネットを通じて、国境に関係なく、世界中の人々から直接、資金を募ることができる可能性がありました。
銀行や投資会社を通さないため、手続きが比較的早く、コストも抑えられると考えられた面もあります。
コミュニティの形成と活性化
ICOは、単にお金を集めるというだけではありませんでした。
プロジェクトのとても早い段階から、そのアイデアに関心を持ち、応援してくれる利用者さんや開発者さんのコミュニティを作るための手段としても機能したんです。
トークンを買った人たちは、単にお金を出した投資家というだけではなく、「このプロジェクトを成功させたい」と願う「支援者」や「最初のファン」のような意識を持つことがあります。
トークンを持っていることで、プロジェクトの運営方針を決める投票に参加できたり、サービスを他の人より先に使えたり、といった特別なメリットが用意されることもありました。
早い時期から熱心なコミュニティを作ることは、プロジェクトが広まったり、発展したりするために、とても重要な力になり得ます。
ICOのメリットは?(プロジェクト側・参加者側から見た側面)
ICOには、実施するプロジェクト側と、トークンを購入する参加者側の双方にとって、いくつかの潜在的なメリットがあると考えられていました。
ただし、これらはあくまで理想的な側面であり、実際には多くのリスクも伴うことを理解しておく必要があります。
どんな良い点が期待されていたのか、見てみましょう。
プロジェクト側のメリット(資金調達のしやすさ等、過去の視点も交えつつ)
プロジェクトチームにとって、ICOはこれまでの資金調達の方法と比べて、いくつか魅力的に見える点がありました。
一つは、国の境を越えて、世界中の幅広い人々から資金を集められる可能性があったことです。
インターネットを使ってプロジェクトの魅力を伝え、共感を呼ぶことができれば、短い期間で大きな資金を集めることに成功した事例も(特にブームの時期には)ありました。
株式会社が株を発行する場合と違って、会社の所有権(議決権など)を渡す必要がないケースが多く、プロジェクトの経営権を自分たちで持ち続けやすいと考えられました。
銀行からお金を借りるように、後で返す必要もありません。
トークンセールを通じて、早い段階から利用者さんのコミュニティを作り、プロジェクトへの関心を高める宣伝効果も期待できました。
参加者側のメリット(初期参加の機会等、リスクを強調しつつ)
トークンを購入する参加者さん側にも、いくつかの期待できる点がありました。
最も大きなものは、「これは!」と思うような有望なプロジェクトに、とても早い段階から関わって、応援できる機会がある、という点でしょう。
もしそのプロジェクトが大成功して、発行されたトークンの価値が将来的にすごく上がれば、大きな利益を得られる可能性がありました。
(ただし、これは非常にギャンブル的な側面が強く、成功の保証は全くありませんでした)。
トークンによっては、そのプロジェクトが提供するサービスやプラットフォームを利用するための権利(ユーティリティ)が付いている場合もありました。
早くからトークンを持っておくことで、将来的にサービスをお得に使えたり、他の人より先にアクセスできたりするかもしれない、という期待もありました。
しかし、これらのメリットはあくまで「可能性」の話です。
後でお話しするように、ICOには非常に高いリスクが伴うことを、決して忘れてはいけません。
ICOに潜むリスクと課題(重要)
ICOブームは、その手軽さや大きなリターンへの期待感から多くの注目を集めました。
しかし、その裏で多くの問題点や深刻なリスクも明らかになりました。
ICOに関わる際には、これらのリスクを十分に理解しておくことが、何よりも大切です。
どんな危険があったのか、しっかり見ていきましょう。
プロジェクト失敗や詐欺のリスク
ICOでお金を集めようとするプロジェクトの多くは、まだアイデア段階だったり、開発が始まったばかりだったりするスタートアップです。
その事業計画が本当に実現できるのか、技術的に可能なのかは、誰にも分かりません。
計画書(ホワイトペーパー)に書かれていた通りに開発が進まず、プロジェクトが途中で頓挫したり、サービスが結局始まらなかったりするケースは、残念ながら非常に多くありました。
さらに深刻だったのは、最初からお金を集めることだけが目的の、悪質な詐欺プロジェクト(スキャムと呼ばれます)がたくさん現れたことです。
実現不可能な夢のような計画を語ったり、嘘の情報で人をだましたりしてお金を集め、プロジェクトチームがそのまま連絡を絶って消えてしまう、といった被害が世界中で多発しました。
ホワイトペーパーの内容や、チームメンバーが本当に実在するのか、信頼できるのかなどを慎重に見極める必要がありましたが、一般の参加者さんにとって、それはとても難しいことでした。
トークン価格の大きな変動リスク
ICOで発行されたトークンは、暗号資産取引所に上場された後、価格がジェットコースターのように非常に大きく変動する(ボラティリティが高い)傾向がありました。
プロジェクトへの期待感や、市場全体の雰囲気、投機的なお金の流れなどによって、価格が急に何倍にもなることもあれば、逆に暴落してほとんど価値がなくなってしまうことも、決して珍しくありませんでした。
多くのICOトークンは、取引量が少なく(流動性が低い)、いざ売りたいと思ってもなかなか買い手が見つからなかったり、非常に安い値段でしか売れなかったりするリスクも抱えていました。
価格変動のリスクは極めて高く、参加したお金の大部分、あるいは全部を失ってしまう可能性も十分にあったのです。
法規制の不確実性と変化
ICOが急速に広まった当初は、多くの国や地域で、ICOが法律上どういう扱いになるのか、どんなルールを守るべきなのかが、はっきりしていませんでした。
そのため、詐欺的なプロジェクトを取り締まるのが難しかったり、参加者を守るための仕組みが不十分だったりしました。
その後、世界中の金融当局(日本では金融庁)がICOに対する監視を強め、新しいルールを作ったり、既存の法律を適用したりする動きが活発になりました。
しかし、国によってルールの内容は様々で、今もなお変化し続けています。
ICOで発行されるトークンが、法律上「株」のような有価証券と見なされるのか、それともビットコインのような「暗号資産(仮想通貨)」として扱われるのか、あるいは全く別の権利なのかによって、適用される法律(金融商品取引法や資金決済法など)が変わってきます。
後からルールが変わって、過去に行われたICOが法的な問題になったり、トークンの取引が制限されたりするリスクも存在します。
これらのリスクを考えると、ICOへの参加は極めて慎重な判断が必要であり、十分な情報収集とリスクへの深い理解が不可欠であったと言えます。
日本におけるICOの規制状況(金融庁の動向)
日本においても、ICOは一時期大きな注目を集めました。
しかし、それに伴って様々な問題も発生したため、金融庁を中心にルールの整備が進められてきました。
日本国内の状況について見ていきましょう。
過去のICOブームと問題点
2017年頃を中心に、日本でもICOによって資金を集めようとするプロジェクトが登場し、一部では大きな金額を集める事例もありました。
しかし、海外と同じように、プロジェクトの実態がよく分からなかったり、詐欺ではないかと疑われるような案件も少なくありませんでした。
消費者センターなどに相談が寄せられるケースもありました。
このような状況を受けて、金融庁はICOに対して注意を呼びかける情報を繰り返し出すようになりました。
金融庁の見解と現在の法規制(資金決済法・金融商品取引法)
金融庁は、ICOについて、その仕組みや発行されるトークンの性質によっては、すでに日本にある法律、「資金決済法」や「金融商品取引法」のルールの対象になる可能性がある、という考え方を示しています。
具体的に見てみましょう。
ICOで発行されるトークンが、ビットコインのように色々な相手への支払いに使えるなど、「暗号資産(仮想通貨)」としての性質を持っている場合は、資金決済法のルール(例えば、トークンを売買する業者は暗号資産交換業の登録が必要など)が関係してきます。
一方で、トークンが、プロジェクトの利益の一部を受け取る権利など、投資信託のような「投資」としての性質を持っている場合は、金融商品取引法のルール(例えば、トークンを販売する業者は金融商品取引業の登録が必要、情報をしっかり開示する必要があるなど)の対象となる可能性が高い、とされています。
つまり、ICOと一口に言っても、その中身によって守るべき法律やルールが違う、ということです。
2020年には、金融商品取引法や資金決済法が改正され、ICOを含む暗号資産に関するルールがさらに厳しくなりました。
利用者さんを守ることや、マネーロンダリング(悪いお金をきれいに見せかけること)を防ぐためのルールが整備されたのです。
これにより、日本国内で法律を守ってICOを実施するためのハードルは、以前に比べて格段に高くなったと言えます。
利用者保護の観点から
金融庁は、ICOのリスクについて、繰り返し注意を呼びかけています。
トークンの価格が大きく下がるリスク、詐欺のリスク、プロジェクトが失敗するリスクなどを挙げて、ICOへの参加はとても高いリスクがあることを強調しています。
「簡単に儲かる」といった話には乗らず、プロジェクトの内容やリスクを十分に自分で調べて理解した上で、自己責任で行う必要がある、というのが基本的な考え方です。
現在では、金融庁に登録されていない業者などが海外で行うICOなどに、日本から参加することは、法律による保護が期待できない可能性が高く、極めて慎重な判断が求められます。
ICOの代替? IEO、STO、IDOとの違い
ICOが抱えていた問題点や、世界的な規制強化の流れを受けて、よりルールを守り、参加者を保護することにも配慮した、新しい形のトークン発行や資金調達の方法が登場してきています。
ICOと比べながら、主なものを簡単に見てみましょう。
これらの新しい方法は、ICOの反省点を踏まえて生まれたものと言えるかもしれません。
IEO(Initial Exchange Offering)とは
IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)は、暗号資産取引所が中心となって、特定のプロジェクトのトークン販売を行う方法です。
プロジェクトチームが直接トークンを売るICOとは違い、取引所がまずプロジェクトの内容を審査します。
そして、トークンの販売から取引所への上場までをサポートします。
取引所が審査に関わることで、ICOに比べてプロジェクトの信頼性が高まり、詐欺的な案件のリスクが減ると期待されています。
参加者さんにとっても、普段使っている取引所のシステムを通じて参加できるので、分かりやすく安心感があるかもしれません。
日本でも、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者によって、IEOが実施される事例が出てきています。
STO(Security Token Offering)とは
STO(セキュリティ・トークン・オファリング)は、株式や不動産、債券といった現実世界の資産に対する権利などを、ブロックチェーン上で発行されるデジタルな証券「セキュリティトークン」として発行し、資金を集める方法です。
セキュリティトークンは、法律上「有価証券」として扱われるため、金融商品取引法などの証券に関するルールを守って発行・取引が行われます。
ICOで問題になったルールの曖昧さをなくし、投資家さんを保護する枠組みの中で資金調達を行うことを目指しています。
法律を守ることが重視されるため、手続きはICOよりも複雑になります。
しかし、より信頼性の高い資金調達や投資の手段として注目されています。
IDO(Initial DEX Offering)とは
IDO(イニシャル・デックス・オファリング)は、DEX(デックス、分散型取引所)と呼ばれる、特定の管理者がいないタイプの暗号資産取引所を通じて、新しいトークンを発行・販売する方法です。
IEOが会社などが運営する中央集権的な取引所(CEX)を介するのに対し、IDOはDEXのプログラム(スマートコントラクト)などを活用して、より分散化された形でトークンセールを行うことを目指します。
誰でも比較的簡単にトークンを発行・販売できる可能性がある一方で、プロジェクトの審査などが行われない場合が多く、ICOと同じように詐欺などのリスクには注意が必要です。
DeFi(分散型金融)が発展する中で登場してきた、比較的新しい資金調達の形です。
これらの新しい方法は、ICOが抱えていた課題、特にルールを守ることや参加者を保護するといった面に対応しようとする動きの中で生まれてきたと言えるでしょう。
まとめ ICOを理解する上で大切なこと
今回は、「ICO(Initial Coin Offering)とは」何か、その基本的な意味から、仕組み、目的、メリット・デメリット、リスク、規制、そしてIEOやSTOといった関連する資金調達方法との違いまで、詳しく見てきました。
ICOは、プロジェクトチームが独自のトークンを発行・販売することで資金を調達する、ブロックチェーン技術が可能にした新しい方法でした。
一時期は大きなブームとなり、画期的な資金調達手段として期待されました。
しかし、その手軽さゆえに、詐欺的なプロジェクトや計画倒れに終わるプロジェクトが多発し、多くの問題点も浮き彫りになりました。
現在では、世界的に規制が強化される傾向にあり、日本においても金融庁の監督のもと、資金決済法や金融商品取引法に基づいたルール整備が進んでいます。
安易なICOへの参加は非常に高いリスクを伴います。
ICOの仕組みや、なぜブームになり、そしてなぜ問題視されるようになったのか、その歴史と背景、そして伴うリスクを理解することは、暗号資産やブロックチェーン技術の動向、そして新しい資金調達方法の移り変わりを知る上で、とても重要です。
技術が持つ可能性と同時に、その利用に伴う課題や、ルール作りの必要性について考える良いきっかけにもなるでしょう。
免責事項
この記事は、ICO(Initial Coin Offering)に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定のICOプロジェクト、暗号資産、トークン、または投資戦略を推奨・勧誘するものではありません。
ICOへの参加や関連する暗号資産への投資は、価格変動、プロジェクトの失敗、詐欺など、非常に高いリスクを伴います。
投資した資金の全額を失う可能性もあります。
本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為の結果についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。
技術の評価や投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討の上で行ってください。
必要に応じて、金融庁のウェブサイトを確認したり、法律や金融の専門家にご相談することをお勧めします。


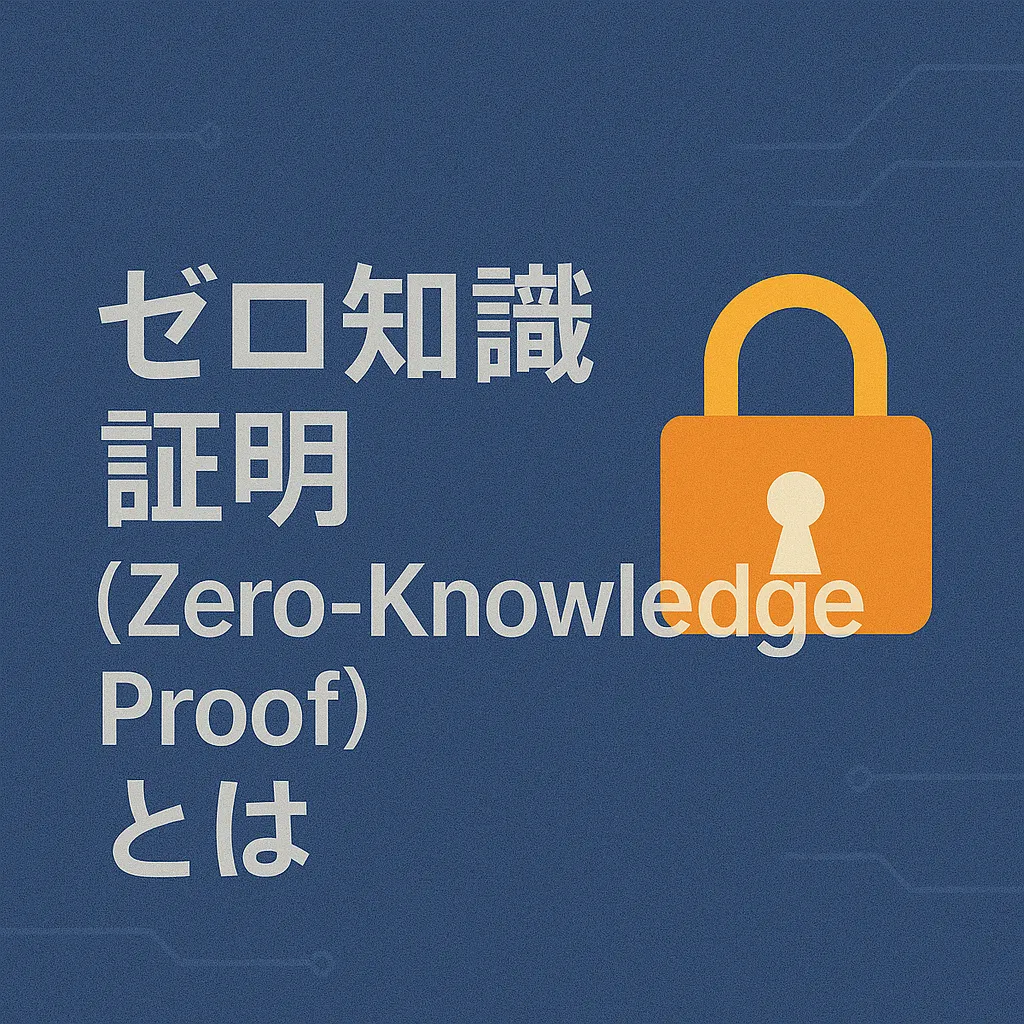






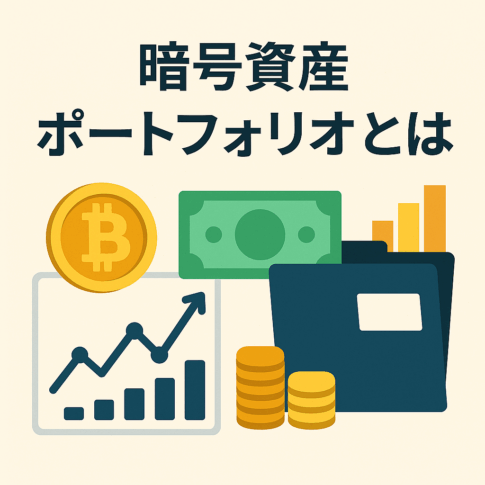





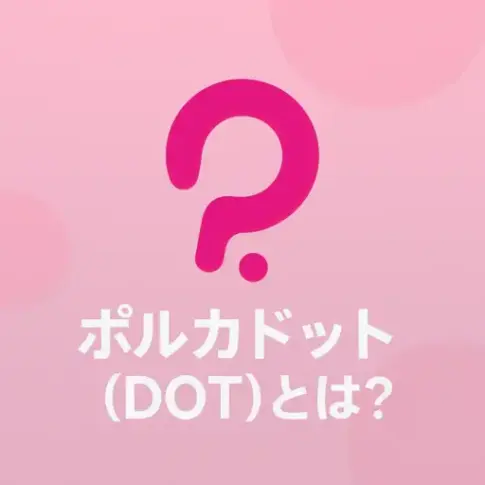
の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)


コメントを残す