DeFiは、Decentralized Financeの頭文字をとった言葉です。
日本語にすると「分散型金融」と訳されます。
これは、私たちが普段利用している銀行や証券会社のような、特定の会社が管理する仕組みとは少し違う、新しい金融の形を指しています。
ブロックチェーンという技術を使って、会社のような中心的な管理者がいなくても動く金融システムのことなんです。
インターネットがあれば、世界中のどこからでもアクセスできる可能性がある、そんな新しい金融のあり方として、今とても注目されています。
この記事では、「DeFiって、結局どういうものなの?」という疑問にお答えします。
DeFiの基本的な仕組みから、これまでの金融サービスとの違い、具体的なサービスの種類、利用する上での良い点や気をつけるべき点、これからの可能性について、わかりやすく、少し掘り下げてお話ししていきますね。
ただ、この記事は特定の金融商品を勧めたり、投資を促したりするものではありません。
あくまでDeFiというものについて、皆さんに情報をお届けし、学んでいただくことを目的としています。
安心して読み進めてくださいね。
DeFi(分散型金融)ってなんだろう? 基本的な考え方を知ろう
DeFi、つまり分散型金融は、その名前が示す通り「分散化」された、みんなで支える金融サービスの仕組みです。
これまでの金融システム、CeFi(中央集権型金融)と呼ばれるものは、銀行や証券会社といった会社が中心となって、私たちのお金の管理や送金、貸し借り、取引といったサービスを提供していました。
これらのサービスを使うときは、その会社を信用して、本人確認をしたり、時には審査を受けたり、手数料を支払ったりするのが普通でしたね。
CeFi(中央集権型金融)との違い
DeFiは、そういった中心となる会社を必要としない点が大きな特徴です。
代わりに、ブロックチェーン技術、特に「スマートコントラクト」というコンピュータープログラムを使って、金融に関するやり取りを自動で行います。
取引の記録はブロックチェーンという場所に、たくさんのコンピューターに分散して記録されます。
この記録は後から書き換えるのがとても難しいので、透明性や信頼性が高いと言われています。
DeFiを使う人は、自分のデジタルなお金(暗号資産)を自分で管理する「ウォレット」というものを通じて、会社などを介さずに直接、色々な金融サービスにアクセスできるようになります。
これが、DeFiが「分散型」と呼ばれる理由なんです。
DeFiを動かす技術の心臓部 ブロックチェーンとスマートコントラクト
DeFiが成り立つためには、ブロックチェーンとスマートコントラクトという技術が欠かせません。
この二つの技術について、少し詳しく見ていきましょう。
ブロックチェーン みんなで管理する記録帳
ブロックチェーンは、取引のデータを「ブロック」という箱に入れて、それを順番に鎖(チェーン)のようにつなげていく技術です。
一度つながった記録は、後から変更するのがとても難しくなっています。
ビットコインという有名な暗号資産で使われている技術ですが、DeFiでは、イーサリアム(Ethereum)のように、もっと複雑なプログラムを動かせる機能を持ったブロックチェーンがよく使われています。
この仕組みによって、特定の管理者がいなくても、みんなで取引記録を安全に管理できるんですね。
スマートコントラクト 自動で契約を実行するプログラム
スマートコントラクトは、あらかじめ決められたルールに従って、条件が整うと自動的に契約を実行してくれるプログラムのことです。
例えば、「AさんがBさんに1ETH(イーサリアムという暗号資産)を送ったら、自動的にBさんのウォレットからAさんのウォレットへ特定のデジタルアイテムを送る」といった約束事をプログラムにして、ブロックチェーン上で動かすことができます。
DeFiのサービスでは、このスマートコントラクトのおかげで、お金の貸し借りや利息の支払い、暗号資産の交換といった様々な取引が、人の手を借りずに自動で、しかも透明性が高い形で行われます。
これにより、手間やコストが削減されたり、処理が速くなったりすることが期待されています。
DeFiではどんなことができるの? 主なサービスの種類を見てみよう
DeFiの世界はどんどん広がっていて、色々な金融サービスが登場しています。
ここでは、代表的なものをいくつか紹介しますね。
DEX(分散型取引所) ユーザー同士で直接交換
まず、DEX(デックス)と呼ばれる分散型取引所があります。
これは、普通の証券取引所や暗号資産取引所(CEX)のように、運営会社が間に入って取引を仲介するのではなく、スマートコントラクトを使ってユーザー同士が直接、暗号資産を交換できる場所です。
多くの場合、AMM(自動マーケットメイカー)という仕組みが使われていて、ユーザーは「流動性プール」と呼ばれる暗号資産のペアが入った箱に対して取引を行います。
Uniswap(ユニスワップ)やSushiSwap(スシスワップ)などが有名ですね。
自分のウォレットをつなぐだけで、比較的安い手数料で暗号資産を交換できる可能性があります。
ですが、価格の変動によって損をしてしまう「インパーマネントロス」というリスクがあることも知っておく必要があります。
レンディングプラットフォーム 暗号資産の貸し借り
次に、レンディングプラットフォームというサービスがあります。
これは、暗号資産を誰かに貸して利息を受け取りたい人(貸し手)と、自分の持っている暗号資産を担保にして別の暗号資産を借りたい人(借り手)を、スマートコントラクトが自動で結びつけるサービスです。
貸し手は、自分の資産を預けることで、何もしなくても収益を得られる可能性があります。
借り手は、持っている暗号資産を売らなくても、一時的にお金(別の暗号資産)を借りることができます。
Aave(アーベ)やCompound(コンパウンド)などがよく知られています。
しかし、担保として預けた暗号資産の価格が大きく下がってしまうと、強制的に売却されてしまう「担保割れリスク」があるので注意が必要です。
イールドファーミングやリクイディティマイニング 報酬を得る運用方法
さらに、イールドファーミングやリクイディティマイニングといった、少し高度な運用方法もあります。
これは、先ほど紹介したDEXの流動性プールやレンディングプラットフォームに、自分の暗号資産を提供(流動性提供)することで、そのお礼として手数料の一部や、そのサービス独自の「ガバナンストークン」というものをもらう行為です。
ガバナンストークンは、そのサービスの運営方針を決める投票に参加できる権利のようなものです。
高いリターンが期待できる場合もありますが、スマートコントラクト自体のリスクや、暗号資産の価格変動リスクなど、複雑で大きなリスクも伴うことが一般的です。
その他のDeFiサービス
これら以外にも、DeFiの世界には様々なサービスがあります。
例えば、特定の暗号資産をネットワークに預けて運用や安全維持に協力し、報酬をもらう「ステーキング」。
現実世界の株価や通貨価格などに連動するデジタル資産「合成資産」を作ったり取引したりするサービス。
スマートコントラクトのバグなど、特定のトラブルに備えるための「分散型保険」など、本当に多岐にわたります。
DeFiを使うとどんな良いことがあるの? 考えられるメリット
DeFiがこれほど注目されているのには、従来の金融サービスにはない、いくつかの良い点があると考えられているからです。
どんなメリットが期待できるのか見ていきましょう。
メリット1 誰でもアクセスしやすい可能性
インターネットとデジタルウォレットがあれば、基本的に住んでいる場所や国籍、これまでの金融取引の履歴などに関わらず、誰でもDeFiサービスを利用できる可能性があります。
これは、銀行口座を持つのが難しい人々や、金融サービスが十分に普及していない地域の人々にとって、新しい金融への扉を開くかもしれません。
メリット2 取引の透明性が高い
ブロックチェーン上で行われる取引は、基本的に誰でも見ることができ、その記録が正しいかを確認できます。
これにより、取引の過程やお金の流れがはっきり見えるので、不正が行われにくい環境が期待されます。
メリット3 効率が良くコストが抑えられる可能性
スマートコントラクトが取引を自動で行うため、これまで金融機関が行っていた仲介の手間が省ける場合があります。
その結果、取引にかかる時間が短くなったり、手数料が安くなったりする可能性があります。
メリット4 自分の資産は自分で管理
DeFiでは多くの場合、ユーザー自身が「秘密鍵」という大切な情報を管理し、自分のウォレットを通じて直接、資産をコントロールします(ノンカストディアルと呼ばれます)。
これにより、サービスを提供している会社が倒産したり、一方的に資産を使えなくされたりするリスクから、ある程度距離を置くことができます。
ただし、これは裏を返せば、自分の資産を守る責任がすべて自分にある、ということでもあります。
メリット5 新しいサービスが生まれやすい
DeFiのサービス(プロトコル)は、設計図(ソースコード)が公開されていることが多く、他のサービスと自由に組み合わせることができます。
これは「マネーレゴ」とも呼ばれていて、既存のサービスをパズルのように組み合わせることで、次々と新しい金融商品やサービスが生まれています。
このイノベーションのスピード感も、DeFiの大きな魅力の一つと言えるでしょう。
DeFiに潜むリスク 知っておきたい注意点
DeFiはとても革新的ですが、利用する際には様々なリスクや課題があることを、しっかり理解しておくことが大切です。
これらの点を軽く考えていると、思わぬ損害につながる可能性もあります。
安全に利用するためにも、どんな点に気をつけるべきか確認しましょう。
注意点1 スマートコントラクトの弱点
スマートコントラクトはコンピュータープログラムなので、バグ(不具合)や設計上のミスが含まれている可能性があります。
悪いことを考える攻撃者は、この弱点を狙って不正に資金を盗み出すことがあります。
多くのプロジェクトでは、専門家によるプログラムのチェック(監査)が行われていますが、チェック済みだからといって、リスクが完全になくなるわけではありません。
注意点2 暗号資産の価格変動
DeFiで扱われる暗号資産の多くは、価格がとても大きく変動することがあります。
レンディングで担保として預けている資産の価値が急に下がると、強制的に売られてしまうリスクがあります。
イールドファーミングなどで得られる報酬の価値も、市場の状況によって大きく変わってしまいます。
注意点3 インパーマネントロス(変動損失)
DEXの流動性プールに暗号資産ペアを預ける際には、インパーマネントロスという特有のリスクがあります。
これは、預けた二つの暗号資産の価格比率が変わることで、ただ持っているだけの場合よりも資産価値が減ってしまう現象のことです。
プールから得られる手数料収入が、この損失を上回らない可能性もあります。
注意点4 ルール(規制)の不確かさ
DeFiはまだ新しい分野なので、各国の法律やルールが十分に整っていなかったり、これから変わったりする可能性があります。
将来、新しいルールができて、特定のDeFiサービスが使えなくなったり、税金の扱いが変わったりするかもしれません。
注意点5 処理の遅れや手数料の高騰
特にイーサリアムのように人気のあるブロックチェーンでは、利用者が増えると取引の処理に時間がかかったり、手数料(ガス代)がとても高くなったりすることがあります。
これにより、少額の取引がしにくくなったり、思ったタイミングで取引ができなかったりする場合があります。
現在、この問題を解決するための新しい技術(レイヤー2スケーリングソリューションなど)の開発が進められています。
注意点6 操作の難しさ
ウォレットの設定や秘密鍵の管理、手数料の調整、各サービスの仕組みの理解など、これまでの金融サービスと比べて、DeFiを利用するには自分で学ばなければならないことが多いのが現状です。
初心者の方にとっては、少し難しく感じられるかもしれません。
注意点7 詐欺的なプロジェクト
残念ながら、中には詐欺的な目的で作られたプロジェクトも存在します。
高いリターンをうたってお金を集めた後、開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」と呼ばれる手口などが報告されています。
利用するプロジェクトが信頼できるか、開発チームはどんな人たちなのか、慎重に情報を集めることが大切です。
これらのリスクをよく理解した上で、自分で情報を集めて分析し(DYOR: Do Your Own Research と呼ばれます)、もし失っても生活に困らない範囲の資金で、とても慎重に利用を考えることが重要です。
DeFiを始めるには?(あくまで情報として)
もしDeFiの世界に少し触れてみたいと思った場合、一般的にはいくつかの準備が必要です。
これは具体的な投資をお勧めするものではなく、あくまで一般的な手順の情報提供としてお読みください。
まず、自分の暗号資産を管理するためのデジタルウォレットを作ることから始まります。
MetaMask(メタマスク)などが、パソコンのブラウザやスマートフォンのアプリで使えるウォレットとしてよく知られています。
ウォレットを作るときに表示される「秘密鍵」や「リカバリーフレーズ(シードフレーズ)」は、あなたのお金へのアクセス権そのものです。
絶対に他の人に教えてはいけませんし、失くさないように厳重に管理する必要があります。
もしこれらが他人の手に渡ったり、失くしてしまったりすると、資産を取り戻せなくなる可能性が非常に高いです。
次に、DeFiサービスで使う暗号資産を手に入れる必要があります。
これは通常、日本円などの法定通貨を使って、中央集権型の暗号資産取引所(CEX)で購入します。
多くのDeFiサービスが基盤としているイーサリアム(ETH)は、取引手数料(ガス代)の支払いにも必要になるため、最初に準備することが多い暗号資産です。
手に入れた暗号資産を、取引所から自分のウォレットに送金します。
送金先のアドレスを間違えてしまうと、資産がどこかへ行ってしまい、取り戻すことはほぼできません。
送金操作は、細心の注意を払って行ってください。
ウォレットに資金が準備できたら、使ってみたいDeFiサービス(dAppと呼ばれます)のウェブサイトを開き、自分のウォレットを接続します。
これで、DeFiサービスとあなたのウォレットが、スマートコントラクトを通じてやり取りできるようになります。
実際にサービスを使うときは、それぞれのサービスの画面の指示に従って操作しますが、必ずその仕組みやリスクを十分に理解してから実行するようにしてください。
まずは少額から試してみる、信頼できる情報源をいくつか確認するなど、慎重に進めることがとても大切です。
DeFiのこれから 未来はどうなる?
DeFiは、これからの金融のあり方を大きく変えるかもしれない分野として、今後も発展していくことが期待されています。
技術的な課題であった処理速度や手数料の問題(スケーラビリティ問題)に対しては、「レイヤー2」と呼ばれる新しい技術が広まったり、イーサリアム自体の性能が向上したりすることで、改善が進むと考えられています。
これにより、もっと速くて安い手数料で取引ができるようになれば、DeFiを使う人がさらに増えるかもしれません。
サービスの使いやすさ(ユーザーインターフェース)の改善や、より安全に使える仕組みの開発も進められています。
将来的には、今よりもっと気軽に、安心して使える環境が整っていくことが期待されます。
また、これまでの金融機関(CeFi)とDeFiが、お互いの良いところを取り入れて協力し合う動きも出てくるかもしれません。
CeFiがDeFiの技術を使ったり、DeFiがCeFiの持つ信頼性や顧客ネットワークと連携したりすることで、もっと便利で新しい金融サービスが生まれる可能性もあります。
一方で、各国の政府や規制当局がDeFiをどう扱っていくかは、今後のDeFiの発展に大きく影響します。
利用者保護や不正利用防止といった観点から、これからどんなルールが作られるかによって、DeFiの世界がどう変わっていくか、注意深く見守る必要があります。
DeFiは、まだ生まれて間もない技術であり、解決すべき課題もたくさんあります。
しかし、金融をもっと身近なものにしたり、透明性を高めたり、効率を良くしたりする点で、大きな可能性を秘めていることは確かです。
これから技術が成熟し、ルールが整っていく中で、DeFiが私たちの金融生活にどんな変化をもたらすのか、引き続き注目していく価値があると言えるでしょう。
まとめ:DeFiは未来の金融を形作るかもしれない新しい波
この記事では、「DeFiって何?」という基本的なところから、その仕組み、良い点、そして見過ごせないリスクやこれからの可能性について、お話ししてきました。
DeFi、分散型金融は、ブロックチェーンとスマートコントラクトという技術を使って、特定の会社に頼らずに動く、新しい金融サービスの形です。
誰でもアクセスしやすい、透明性が高い、効率が良いといった良い面が期待される一方で、プログラムの弱点や価格変動、ルールの不確かさといった、注意すべき点もたくさんあります。
DeFiの世界に関わる場合は、これらのリスクをしっかり理解して、常に新しい情報を自分で集め、慎重に判断することがとても大切です。
この記事が、DeFiについて学び、情報を集めるための一つのきっかけとなれば幸いです。
DeFiはものすごいスピードで変化している分野であり、その未来がどうなるかはまだ誰にもわかりません。
しかし、これまでの金融システムのあり方に新しい可能性を示している、重要な動きであることは間違いなさそうです。
DeFiについて知っておくことは、これからの社会や経済の変化を理解する上で、きっと役立つはずです。
免責事項
本記事は、DeFi(分散型金融)に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定の金融商品、サービス、または投資戦略の推奨、勧誘、または助言を行うものではありません。
暗号資産およびDeFiサービスは、価格変動リスク、スマートコントラクトの脆弱性リスク、規制リスク、ハッキングリスク、秘密鍵管理リスクなど、様々なリスクを伴います。
本記事に掲載された情報に基づいて利用者が行った判断や行動により、いかなる損失や損害が生じたとしても、作成者は一切の責任を負いかねます。
DeFiサービスの利用や暗号資産への投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において、十分な情報収集とリスク評価の上で行ってください。
必要に応じて、金融、法律、税務等の専門家にご相談されることをお勧めします。
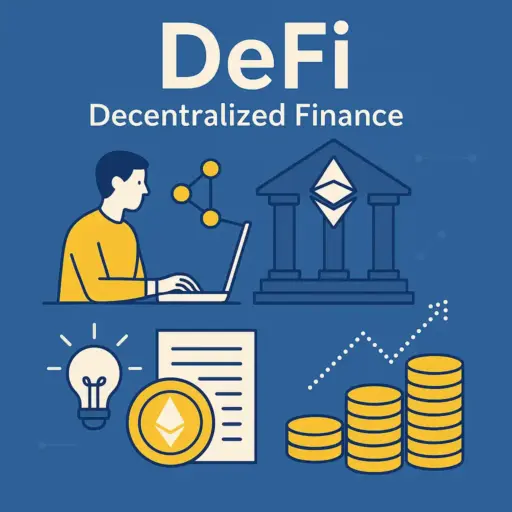


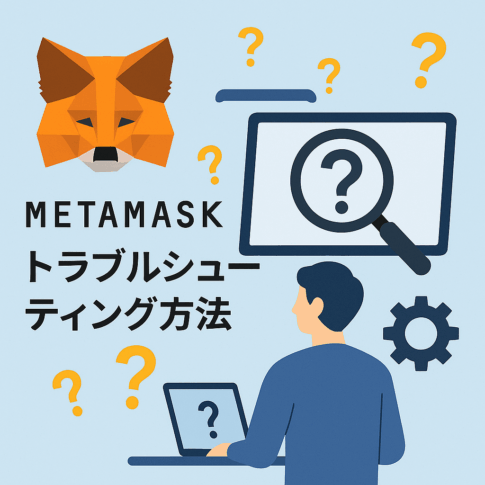



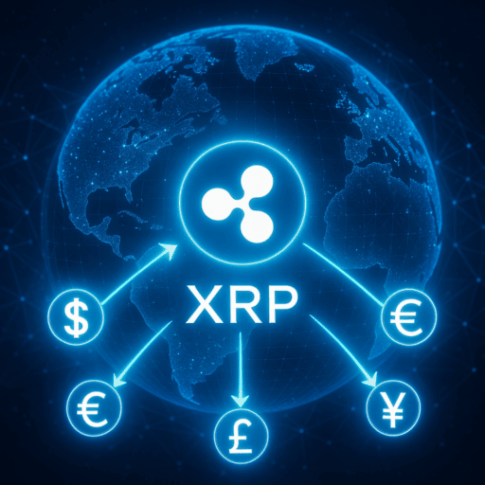







の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す