「ブロックチェーンゲーム」って言葉、よく聞くようになりましたよね。
なんだか新しいゲームみたいだけど、一体どんなものなんだろう?って気になっている方もいるかもしれません。
この記事では、そんなブロックチェーンゲームの基本的なことや、これまでのゲームとどう違うのか、その仕組みや特徴について、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。
特定のゲームをおすすめしたり、お金の話をしたりするわけではなく、あくまで「ブロックチェーンゲームってこういうものなんだ」という情報をお届けするのが目的なので、気軽に読んでみてくださいね。
ブロックチェーンゲームって何?まずは基本を知ろう
ブロックチェーンゲームというのは、その名前の通り「ブロックチェーン」っていう技術を使って作られているゲームのことなんです。
ブロックチェーンは、データをみんなで管理するノートみたいなもの、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
この技術のおかげで、ゲームの中のデータや記録を、特定の会社だけじゃなくて、参加しているみんなで安全に管理できる、と言われています。
ブロックチェーンがゲームを変える?非中央集権性ってなに?
この「みんなで管理する」っていうのが、ブロックチェーンゲームの面白いところなんです。
これまでのオンラインゲームだと、アイテムとかキャラクターのデータは、ゲームを作っている会社が全部管理していましたよね。
だから、もしゲームのサービスが終わっちゃったら、データも消えちゃう、なんてこともありました。
しかし、ブロックチェーンゲームだと、大切なデータの一部、例えば手に入れたアイテムの情報なんかが、ブロックチェーンっていうノートに書き込まれることがあるんです。
そうすると、もしゲームの運営会社さんがいなくなっても、理論上は、ブロックチェーンに残ったアイテムのデータはなくならない可能性がある、と考えられているんですよ。
ブロックチェーンゲームを動かす技術たち
ブロックチェーンゲームがどうやって動いているのか、もう少し詳しく見ていきましょうか。
いくつか、大切な技術が使われているんです。
ゲームの土台「ブロックチェーン技術」
まず、ゲームの土台になっているのが、さっきも出てきたブロックチェーン技術です。
これは、取引の記録などを「ブロック」っていう箱に入れて、それを順番につなげていく技術です。
一度記録したら、後から書き換えるのがとても難しい、と言われています。
誰でも記録を確認できる透明性も特徴で、ゲームの中でのアイテムの持ち主情報や、やり取りの記録を、しっかり守るのに役立っています。
アイテムが特別な宝物に?「NFT」の役割
次に注目したいのがNFT(エヌエフティー)、日本語だと「非代替性トークン」って呼ばれるものです。
なんだか難しそうに聞こえますが、これは「替えがきかない、世界に一つだけのデジタルデータ」のことなんです。
普通の100円玉は、どれも同じ価値ですよね。
しかし、NFTは、一つ一つに違う印がついていて、限定品みたいに扱われるんです。
ブロックチェーンゲームでは、このNFTを使って、ゲームに出てくるキャラクターやアイテム、土地なんかを表現することがあります。
これによって、プレイヤーさんは、ゲームのデータを、ただのデータとしてじゃなくて、自分だけの特別な「デジタル資産」みたいに感じて、持つことができるようになる、と考えられています。
ゲームとお金をつなぐ?「暗号資産」
そして、**暗号資産(仮想通貨)**も、多くのブロックチェーンゲームで使われています。
ビットコインとかイーサリアムって聞いたことありますか?
ああいった暗号資産が、ゲームの中のお金として使われたり、アイテムを買う時に必要になったり、ゲームをプレイしたご褒美としてもらえたりすることがあるんです。
NFTになったアイテムを、他のプレイヤーさんとやり取りする時にも、暗号資産が使われることがあります。
今までのゲームと何が違うの?新しい体験って?
ブロックチェーンやNFTが使われることで、ブロックチェーンゲームは、これまでのゲームとはちょっと違った、新しい楽しみ方ができる可能性があるんです。
どんなところが新しいのか、見ていきましょう。
ゲームの中のアイテムが自分のものに?「デジタル所有権」
一番大きな違いかもしれないのが、デジタル所有権っていう考え方です。
これまでのゲームだと、手に入れたアイテムって、実はゲーム会社さんから「借りてる」データっていう扱いだったんです。
だから、法的には自分のもの、とは言えませんでした。
しかし、ブロックチェーンゲームでNFTとして発行されたアイテムとかは、ブロックチェーン上に「これはあなたのものですよ」っていう記録が残るんです。
もちろん、ゲームのルールの中での話ですが、これによって、プレイヤーさんは、デジタルアイテムを、より「自分のもの」として実感できる可能性があるんですね。
プレイヤーが主役の市場?「プレイヤー主導の経済圏」
この「自分のもの」っていう感覚は、プレイヤーさん同士でアイテムをやり取りする市場みたいなものが生まれるきっかけになることもあります。
NFTになったアイテムは、ゲームの外にある専用の場所(マーケットプレイスって呼ばれます)で、他のプレイヤーさんと売ったり買ったりできることがあるんです。
珍しいアイテムを手に入れたり、使わなくなったアイテムを他の人に譲ったり、そんなプレイヤーさん同士のやり取りが生まれる可能性があるんですね。
ただ、本当に売買できるのか、どんなルールなのかは、ゲームによって全然違うので、そこは注意が必要です。
ウソやごまかしが難しい?「透明性と公平性」
ブロックチェーンのもう一つの特徴、透明性と公平性も、ゲームの体験に関わってきます。
アイテムがいつ、いくつ作られて、誰が持っているか、みたいな情報が、ブロックチェーン上で公開されていて、誰でも見られる場合があるんです。
これによって、運営がズルをしていないか、とかが分かりやすくなる、と考えられています。
例えば、「すごくレアなアイテムが、実はこっそりたくさん作られてた!」なんてことが、起こりにくくなるかもしれませんね。
話題の「Play & Earn」ってどういうこと?
ブロックチェーンゲームの話をしていると、「Play to Earn(P2E)」とか「Play & Earn」っていう言葉を聞くことがあるかもしれません。
これは、「プレイして稼ぐ」とか「プレイしながら(何か価値を)得る」っていう意味合いで使われています。
具体的には、ゲームの中でクエストをクリアしたり、対戦に勝ったり、アイテムを作ったりすることで、ご褒美として暗号資産やNFTがもらえる可能性がある、っていう仕組みのことなんです。
ゲームで報酬がもらえる仕組み
もらったNFTアイテムをマーケットプレイスで売ったり、暗号資産を交換したりすることで、現実のお金に近い価値になる可能性も、ゼロではありません。
この点が、ただ「楽しむため」だったこれまでのゲームとは違う、新しい魅力として注目されている理由の一つなんですね。
報酬をもらう方法はゲームによって本当に色々で、ゲームの中での活動だったり、キャラクターを育てたり、持っている土地を活用したり、他のプレイヤーさんに自分のキャラクターを貸してあげたり(スカラーシップ制度、なんて呼ばれることもあります)と、様々です。
知っておきたい大切な注意点
しかし、ここでしっかりお伝えしておきたいことがあります。
「Play & Earn」は、あくまでブロックチェーンゲームが持っている「可能性」の一つだということです。
誰もが簡単に、しかも確実に、お金を稼げるわけでは決してありません。
もらえる報酬の価値は、市場の状況とか、ゲームの人気、欲しい人と売りたい人のバランスなんかで、大きく変わる可能性があります。
それに、ゲームによっては、始めるためにお金(暗号資産やNFTを買う費用)が必要になることもあります。
ゲームの仕組みやリスクをよく知らないまま、「稼げるらしい」という話だけを信じてしまうのは、とても危ないかもしれません。
あくまで、「ゲームを楽しんでいたら、おまけで何か報酬がもらえることもあるかも」くらいの気持ちでいるのが、ちょうどいいかもしれませんね。
どんなブロックチェーンゲームがあるの?
ブロックチェーンゲームって、何か特定のジャンルだけがあるわけじゃないんです。
普通のゲームと同じように、RPGとか、カードゲーム、街づくりみたいなシミュレーションゲーム、キャラクターを育てるゲーム、スポーツゲーム、パズルゲームまで、本当に色々な種類のゲームが作られています。
いろんなジャンルのゲームたち
例えば、集めたモンスターで戦うゲームとか、仮想空間の土地を持って、そこに建物を建てたり、イベントを開いたりするメタバース系のゲーム、絵画みたいなアート作品やコレクションアイテムとしてのNFTを楽しむゲームなんかが存在します。
有名なゲームの名前をいくつか挙げると、「Axie Infinity」さんや「The Sandbox」さん、「Decentraland」さんあたりがよく聞くかもしれません。
しかし、これらは本当にたくさんあるブロックチェーンゲームの中の、ほんの一部です。
新しいゲームもどんどん出てきていて、内容は常に新しくなっています。
ブロックチェーンゲーム、始めてみたいと思ったら
ブロックチェーンゲーム、ちょっと面白そうだな、触ってみたいな、と思った時に、知っておくと良いことがいくつかあります。
まず、何よりも情報を集めることがすごく大切です。
気になるゲームがあったら、公式のウェブサイトを見たり、プレイヤーさんたちのコミュニティを覗いてみたり、信頼できる情報をしっかり探して、ゲームの内容や仕組み、必要なもの、どんなリスクがあるのかを、じっくり調べることから始めましょう。
一般的に必要になるかもしれないもの
ブロックチェーンゲームを遊ぶためには、多くの場合、暗号資産ウォレットっていうものが必要になります。
これは、暗号資産やNFTを入れておくための、デジタルのお財布みたいなものです。
ウォレットにも色々な種類があるので、遊びたいゲームがどのウォレットに対応しているかを確認する必要があります。
ゲームによっては、始めるために特定の暗号資産(例えばイーサリアムとか)が必要だったり、ゲームで使うNFTを最初に買わないといけなかったりする場合もあります。
ゲーム選びも慎重に
どのゲームを選ぶか、どのサービスを使うかも、よく考えて決めたいところです。
ゲーム自体が面白いか、これからどうなっていくか、作っているチームは信頼できそうか、プレイヤーさんたちのコミュニティは盛り上がっているか、そんな点も見てみると良いかもしれません。
遊ぶ前に知っておきたいこと、注意点
ブロックチェーンゲームに関わる上で、いくつか「これは知っておいた方がいいよ」という注意点があります。
安全に楽しむためにも、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。
価値が変わるかも?「価格変動リスク」
まず、価格変動リスクです。
ゲームの中で使われる暗号資産やNFTの価値は、一定ではありません。
市場の状況や、法律やルールの変更、ゲームの人気なんかによって、価値が上がったり、逆に下がったり、大きく変わる可能性があります。
自分の資産は自分で守る「セキュリティ」
次に、セキュリティの問題です。
暗号資産ウォレットの管理は、基本的に自分自身で行うことになります。
お財布の鍵(秘密鍵やパスワード)をなくしたり、誰かに知られたりしたら、中の資産を失ってしまうかもしれません。
偽物のウェブサイトに誘導して情報を盗もうとする詐欺(フィッシング詐欺って言います)や、悪いプログラムが入ったゲームにも注意が必要です。
信頼できる情報をもとに、慎重に行動することが大切です。
ルールが変わるかも?「法規制や税金」
三つ目は、法律やルール、税金に関することです。
ブロックチェーンゲームや、そこで使われる暗号資産、NFTに関するルールは、国や地域によって違いますし、まだ新しくて、これから変わっていく可能性も高いです。
ゲームで得た利益に税金がかかるのか、かかるとしたらどう計算するのか、といったことも、複雑で分かりにくい場合があります。
もし心配なことがあれば、税金の専門家さんなどに相談することも考えてみてください。
ゲームとして面白い?「ゲームのクオリティ」
最後に、ゲームとしての面白さです。
ブロックチェーンとかNFTっていう新しい技術が注目されがちですが、それを使っているからといって、全てのゲームが面白いとは限りません。
普通のゲームと同じように、絵がきれいか、ゲームのシステムは楽しいか、物語は魅力的か、といったゲーム自体の質も様々です。
技術的な面に加えて、純粋に「ゲームとして楽しめるか」という視点も、忘れないようにしたいですね。
ブロックチェーンゲームのこれから(ちょっと未来の話)
ブロックチェーンゲームは、まだまだ新しい分野で、技術もどんどん進歩しています。
これから、ブロックチェーンの処理がもっと速くなったり、もっと簡単に使えるようになったりすれば、さらに多くの人にとって、当たり前のゲームになっていくかもしれません。
ゲームの枠を超える可能性も
ゲームという枠を超えて、仮想空間の「メタバース」とくっついたり、お金の仕組み(DeFiって呼ばれます)を取り入れた、もっと新しい遊び方が生まれてくることも考えられます。
デジタルな世界で「ものを持つ」ということや、そこでの経済活動のあり方に、ブロックチェーンゲームが大きな変化をもたらす可能性もある、なんて言われています。
これからの課題
一方で、一度にたくさんの人が遊ぶと処理が追いつかなくなる問題(スケーラビリティって言います)や、法律やルールの整備、安全対策の強化、そして何よりも、長く続けられて、ちゃんと面白いゲームを作り続けること、といった課題も、まだまだたくさんあります。
これらの課題をどう乗り越えて、これからどんな風に発展していくのか、注目していきたいですね。
おわりに:ブロックチェーンゲームをもっと知るために
さて、ここまで「ブロックチェーンゲームって何?」という疑問に答えるために、基本的なことから、仕組み、特徴、そして注意したい点まで、一緒に見てきました。
ブロックチェーン技術やNFTを使うことで、デジタルアイテムを「自分のもの」として持てたり、プレイヤーさん同士でやり取りしたり、これまでのゲームにはなかった新しい可能性が広がっていることが、少しイメージできたでしょうか。
「Play & Earn」っていう考え方も、ゲームとの新しい付き合い方として注目されています。
しかし、同時に、価値が変わるリスクや、セキュリティの問題、法律や税金のこと、そしてゲーム自体の面白さなど、色々な面から、しっかり情報を集めて、よく理解することがとても大切です。
ブロックチェーンゲームは、まだまだ発展している途中の分野で、情報は常に新しくなっています。
もし興味を持ったら、信頼できる情報をもとに学び続けて、最終的にはご自身の判断と責任で関わっていくようにしてくださいね。
この記事が、ブロックチェーンゲームという新しい世界を知る、ちょっとしたきっかけになれば嬉しいです。
免責事項
当記事は、ブロックチェーンゲームに関する一般的な情報提供および学習を目的として作成されており、特定の金融商品や暗号資産、ゲームへの投資、購入、または売却を推奨・勧誘するものではありません。
記事内で言及されている暗号資産やNFTの価格は変動する可能性があり、損失を被るリスクがあります。
ブロックチェーンゲームへの参加や関連する取引は、ご自身の判断と責任において行ってください。
当記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、執筆者および運営者は一切の責任を負いかねます。
必要に応じて、金融や税務の専門家にご相談ください。




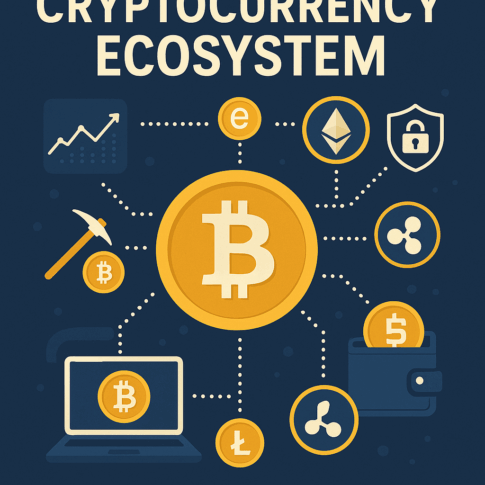

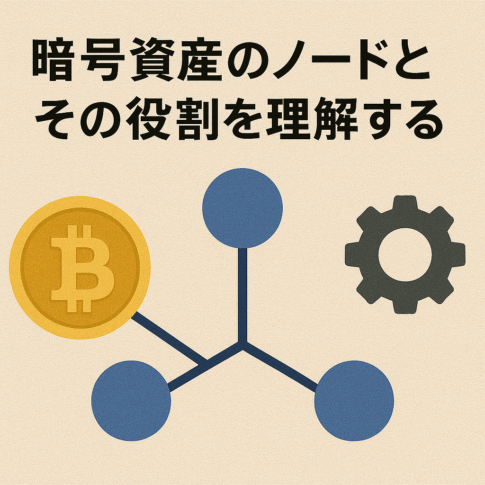

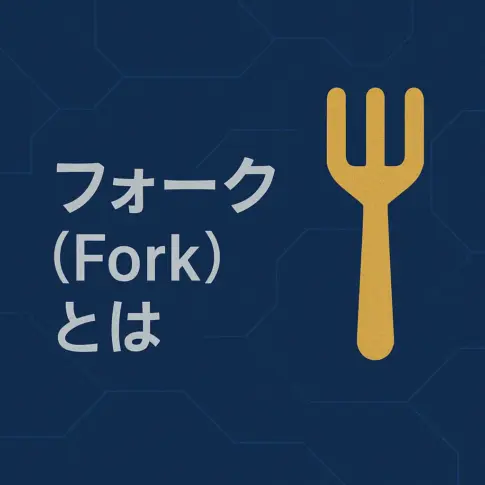

って何?特徴や仕組み-485x256.webp)





の仕組み-485x254.png)


コメントを残す