「ステーキングって最近よく聞くけど、一体どんな仕組みなんだろう?」
「暗号資産を持っているだけじゃなくて、何か活用する方法はないかな?」
もしかしたら、あなたもそんな風に思ったことがあるかもしれませんね。
この記事では、そんな疑問にお答えするために、「ステーキング」の世界をやさしく紐解いていきます。
ステーキングの基本的な考え方から、その背景にあるブロックチェーン技術との関わり、そして気になる報酬の仕組みや、始める前に知っておきたい大切な注意点まで。
専門用語はできるだけ少なく、具体的なイメージが湧くように解説しています。
この記事を読み終える頃には、「なるほど、ステーキングってそういうことだったのか!」とスッキリ理解できるよう、情報提供を目的として、わかりやすさを第一に心がけました。
投資を勧める内容ではありませんので、まずは「ステーキングについて学んでみよう」という気持ちで、気軽に読み進めてみてくださいね。
きっと、暗号資産の新しい一面が見えてくるはずです。
暗号資産のステーキング まずは基本を知ろう
ステーキングの世界に足を踏み入れる前に、まずは「ステーキングって、そもそも何をするの?」という基本的なところから見ていきましょう。
少し専門的な言葉も出てきますが、イメージしやすいように説明していきますね。
ステーキングって何だろう?
ステーキングをすごく簡単に言うと、特定の種類の暗号資産を、専用のお財布(ウォレット)やサービスを提供している場所(プラットフォーム)に預けて、動かせないようにロックすることです。
その行動によって、その暗号資産が動いているネットワーク、つまりブロックチェーンのお手伝いをすることになります。
そして、そのお手伝いのお礼として、報酬がもらえる可能性がある、というのがステーキングの基本的な考え方です。
よく銀行預金の利息に例えられることもありますが、仕組みやリスクは全く違うものと考えたほうが良いでしょう。
銀行預金は銀行への信用が基本ですが、ステーキングはブロックチェーンというみんなで管理するネットワークの安全性を保つための「貢献」に対するお礼、というイメージです。
このステーキングの背景には、「プルーフオブステーク(Proof of Stake、PoS)」という大切な仕組みが関わっています。
プルーフオブステーク(PoS)との関係
プルーフオブステーク(PoS)は、ブロックチェーンの取引記録が正しいかどうかを確認するための、たくさんのルール(コンセンサスアルゴリズム)のうちの一つです。
PoSを採用しているブロックチェーンでは、暗号資産をたくさん持っている人や、長く持っている人ほど、取引記録の確認作業に参加できるチャンスが増える傾向にあります。
ステーキングに参加するということは、自分の持っている暗号資産を「私はこのネットワークを信頼していますよ」という証として差し出す(ステークする)ことで、この確認作業に参加し、ネットワークを支える一員になる、ということです。
資産をロックすることで、「ちゃんとルールを守ってネットワークに貢献します」という意思表示にもなり、不正をしにくくする効果も期待されているんですよ。
ステーキングとブロックチェーン技術 PoSの役割をもう少し詳しく
ステーキングを理解するには、その土台となっているブロックチェーン技術、特にコンセンサスアルゴリズムについて少し知っておくと、よりイメージが湧きやすくなります。
ここでは、PoSがなぜ生まれ、どのような役割を果たしているのかを見ていきましょう。
ブロックチェーンを支える仕組み PoWとPoS
ビットコインという有名な暗号資産で使われているのが、「プルーフオブワーク(Proof of Work、PoW)」という仕組みです。
PoWでは、とても難しい計算問題を一番最初に解いた人が、新しい取引記録のブロックを作り、報酬をもらえます。
この計算競争は「マイニング」と呼ばれ、ネットワークを守る強固な仕組みですが、膨大な電気を使うことや、高性能なコンピューターが必要になる、といった課題も指摘されていました。
そこで考え出されたのが、「プルーフオブステーク(PoS)」です。
PoSでは、計算競争の代わりに、暗号資産をどれだけ持っているか(ステークしているか)が、ブロックを作る人を決める重要な要素になります。
PoSが注目される理由
PoSは、PoWに比べて使う電気の量がとても少ないと言われています。
環境への負荷が小さいというのは、大きなメリットと考えられていますね。
それに、暗号資産を持っている人自身が、そのネットワークが安全であることを望むはずなので、自分の資産を守るためにも、ルールに従ってきちんとネットワーク運営に参加する動機が生まれます。
このように、経済的な合理性でネットワークの安全性を保とうとするのがPoSの特徴です。
PoSにもいくつか種類があって、例えば「デリゲートプルーフオブステーク(DPoS)」では、暗号資産を持っている人が投票で代表者を選び、その代表者がブロックを作る、といった効率的な運営を目指す仕組みもあります。
ステーキングは、これらPoS系のブロックチェーンを支える、とても大切な活動の一つなのです。
ステーキングの仕組み 報酬はどこからやってくるの?
ステーキングに参加すると報酬がもらえる可能性がある、とお伝えしましたが、具体的にどうやって報酬が発生するのでしょうか。
ここでは、ステーキングに参加してから報酬を受け取るまでの流れと、報酬の源について見ていきましょう。
ステーキング報酬が発生するまで
まず、ステーキングを始めるには、ステーキングに対応している暗号資産について情報を集めるところからスタートです。
どの暗号資産にするか決めたら、それを手に入れて、ステーキングサービスを提供している場所(取引所やウォレットなど)に移します。
そして、そのサービスの指示に従って、「ステーキングします」という申し込み手続きを行います。
手続きが完了してステーキングが始まると、預けた暗号資産は、決められた期間、動かせないようにロックされます。
このロック期間中に、ネットワークのお手伝い(取引記録の確認作業への貢献)をすることで、報酬が支払われる仕組みです。
貢献の仕方は、自分で直接確認作業を行う「バリデーター」になる方法と、信頼できるバリデーターに自分の資産を預けて応援する「デリゲート(委任)」という方法があります。
報酬は何によって決まるの?
ステーキングでもらえる報酬は、主に2つのところから来ています。
一つは、そのブロックチェーンのルールによって新しく作られる暗号資産です。
ネットワーク全体で計画的に暗号資産の量を増やしていき、貢献してくれた人に配るイメージですね。
これを「インフレーション報酬」と呼ぶこともあります。
もう一つは、そのブロックチェーン上で誰かが取引をしたときに支払われる手数料の一部です。
もらえる報酬の量や、もらえるタイミングは、選んだ暗号資産の種類、ネットワーク全体でどれくらいの人がステーキングに参加しているか、自分が参加しているバリデーターがどれだけしっかり仕事をしているか、利用しているサービスの手数料など、色々な要因によって変わってきます。
ステーキングの主な特徴と知っておきたいこと
ステーキングには魅力的な面もありますが、参加する前に知っておくべき大切な点もいくつかあります。
ここでは、ステーキングの主な特徴と、特に気をつけておきたいリスクや注意点について、詳しく見ていきましょう。
ステーキングの魅力的なポイント
ステーキングの一番の魅力は、持っている暗号資産を使って、ネットワークの運営に参加し、そのお礼として報酬を得られる可能性があることでしょう。
ただ価格が上がるのを待つだけではなく、資産そのものから収益を得るチャンスがある、ということです。
それに、PoWのマイニングのように、特別な高性能コンピューターや専門知識がなくても、比較的少ない資金から始められる場合が多いのも、参加しやすいポイントかもしれません。
ネットワークの管理を一部の人に集中させず、多くの参加者で支える「分散性」を高めることにも繋がる、という側面もあります。
知っておきたい ステーキングのリスクと注意点
魅力的な面がある一方で、ステーキングには注意すべきリスクもあります。
まず、一番基本的なリスクは、ステーキングしている暗号資産自体の価格が下がってしまう可能性です。
市場の状況によっては、せっかく報酬をもらっても、日本円などに換算したときの価値が、最初に投資した額より減ってしまうこともあり得ます。
次に、ステーキング中は資産がロックされて、すぐには売ったり送ったりできなくなる点も重要です。
急に価格が変動しても、すぐに対応するのが難しくなる場合があります。
特に、ステーキングをやめるときに、「アンボンディング期間」という、資産がロックされたまま待たなければいけない期間が設定されていることが多いので、注意が必要です。
ネットワーク特有のリスクもあります。
「スラッシング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、ブロックの確認作業を行うバリデーターが、ルール違反(例えば、わざと間違った情報を流すなど)をしたり、仕事を怠ったりした場合に、ペナルティとして預けている資産の一部、場合によっては全部が没収されてしまう仕組みです。
自分でバリデーターになる場合はもちろん、信頼できないバリデーターに資産を預けてしまった場合も、この影響を受ける可能性があります。
どのバリデーターを選ぶかは、とても慎重に考える必要がありますね。
さらに、利用するサービス自体のリスクも考えなければいけません。
暗号資産取引所のような場所に資産を預けてステーキングする場合、もしその取引所がハッキングされたり、経営がうまくいかなくなったりすると、預けた資産が戻ってこなくなるリスク(カウンターパーティリスク)があります。
最近では、「リキッドステーキング」といって、ステーキングしながらも、その証明となる別のトークンをもらって、ある程度の自由度を保てるサービスも出てきています。
しかし、これらは複雑なプログラム(スマートコントラクト)で動いているため、プログラムの欠陥を悪用されるリスクも考えられます。
これらのリスクをよく理解して、自分の知識や、どれくらいリスクを受け入れられるかに合わせて、ステーキングの方法を選ぶことが大切です。
ステーキングと税金のこと 少しだけ触れておきます
日本でステーキングによって報酬を得た場合、その報酬は所得とみなされて、税金がかかる可能性が高いと考えられています。
一般的には、報酬を受け取ったときの暗号資産の価格(時価)で所得額を計算し、他のお給料などの所得と合わせて税金を計算することが多いようです。
しかし、税金の計算方法やルールは、個人の状況や、税に関する制度の変更によって変わることがあります。
特に、頻繁に報酬を受け取る場合や、複数の暗号資産でステーキングしている場合は、計算が複雑になりがちです。
ステーキングを含む暗号資産の税金については、自分で判断せずに、必ず税務署や、暗号資産に詳しい税理士さんに相談して、正しい情報を確認するようにしてください。
この記事は、税金に関するアドバイスをするものではありません。
ステーキングの始め方 一般的な流れ(情報提供)
もしステーキングに興味を持ち、「始めてみたいかも」と思った方のために、一般的な始め方の流れを情報提供としてご紹介します。
繰り返しになりますが、これは手順の紹介であり、ステーキングを推奨するものではありません。
情報収集が第一歩
何よりもまず、じっくりと情報を集めることが大切です。
ステーキングができる暗号資産はたくさんありますが、それぞれプロジェクトの目的や使われている技術、将来性、報酬の仕組み、リスクなどが異なります。
報酬率(利回り)の数字だけを見るのではなく、どれくらいの期間資産がロックされるのか、ステーキングをやめるときにどれくらい待つ必要があるのか(アンボンディング期間)、どんな場合にペナルティ(スラッシング)があるのか、といった細かい点まで、しっかりと調べましょう。
プロジェクトのウェブサイトや、信頼できる情報源を参考にすることをおすすめします。
ステーキングができる場所の種類
次に、どこでステーキングを行うか、プラットフォームを選びます。
主な選択肢としては、以下のようなものがあります。
暗号資産取引所 多くの取引所がステーキングサービスを提供しています。 普段使っている取引所で始められる手軽さがありますが、資産の管理は取引所に任せることになるため、取引所自体のリスク(ハッキングや倒産など)を考慮する必要があります。 手数料がかかる場合が多いので、その点も確認しましょう。
ソフトウェアウォレット(ノンカストディアル) 自分で秘密鍵(資産へのアクセス権)を管理するタイプのお財布(ウォレット)の中にも、ステーキング機能がついているものがあります。 資産を自分で管理できるのがメリットですが、操作方法やセキュリティ対策について、ある程度の知識が必要になります。
専用ステーキングサービス/プール 特定の暗号資産や、複数の資産のステーキングを専門に行うサービスです。 多くの場合、ユーザーは信頼できるバリデーターを選んで資産を預ける(委任する)形になります。 どのバリデーターを選ぶか、サービスの手数料はいくらか、などを比較検討することが大切です。
リキッドステーキングプロトコル ステーキングした資産の代わりに、別の流動性のあるトークンを受け取れる比較的新しいサービスです。 ステーキング中も資産を他の場所で活用できる可能性がある反面、スマートコントラクトのリスクなどが加わります。
どのプラットフォームを選ぶにしても、利用する前には必ず利用規約やリスクに関する説明をよく読んで、内容を十分に理解することが重要です。
そして、最終的にはご自身の判断と責任において、行動するようにしてください。
まとめ ステーキングを正しく理解するために
ステーキングは、プルーフオブステーク(PoS)系のブロックチェーンネットワークで、暗号資産を保有・ロックすることで、ネットワークの運営を支え、そのお礼として報酬を得る仕組みです。
マイニングと比べて参加しやすい面もありますが、暗号資産自体の価格変動リスク、資産がロックされることによる流動性の低下、ペナルティとして資産が没収されるスラッシングのリスク、利用するプラットフォームのリスクなど、たくさんの注意点があります。
ステーキングは、暗号資産の関わり方の一つとして興味深い技術ですが、その良い面だけではなく、複雑な仕組みと潜在的なリスクをしっかりと理解することが何よりも大切です。
もしステーキングに関心を持った場合は、信頼できる情報をさらに集め、ご自身の判断と責任で、慎重に検討を進めてくださいね。
この記事が、ステーキングという技術や、その背景にあるブロックチェーンの世界について、皆さんが理解を深めるための一つのきっかけとなれば嬉しいです。
免責事項
この記事は、暗号資産のステーキングに関する情報提供を目的として作成されたものであり、特定の金融商品や投資戦略の推奨、または投資助言を行うものではありません。
暗号資産の取引やステーキングには、価格変動リスク、流動性リスク、システムリスク、カウンターパーティリスク、法規制の変更リスクなど、様々なリスクが伴います。
記事の内容は、執筆時点の情報に基づいていますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
暗号資産への投資やステーキングに関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集とリスク分析を行った上で行ってください。
必要に応じて、金融の専門家や税務の専門家にご相談ください。
筆者および情報提供元は、この記事の情報に基づいて行われたいかなる行為の結果についても、一切の責任を負いません。






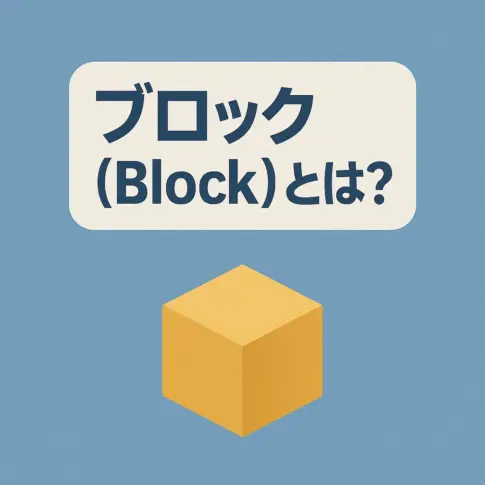
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)
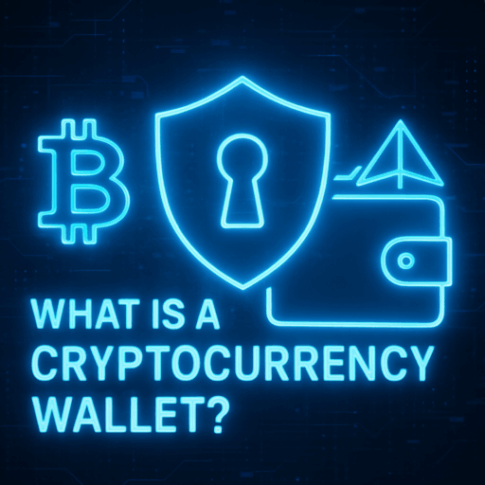
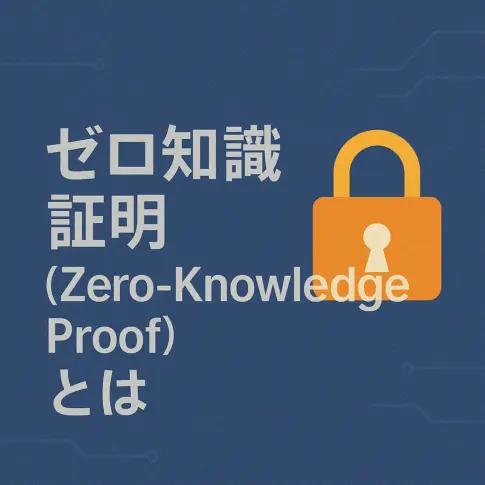






の仕組み-485x254.png)



コメントを残す