暗号資産(仮想通貨)の取引について調べていると、「DEX(デックス)」という言葉を目にすることが増えてきたかもしれませんね。
これは「Decentralized Exchange」の略で、日本語では「分散型取引所」と呼ばれます。
私たちが普段よく利用するかもしれないCoincheckさんやbitFlyerさんのような取引所(これらはCEX 中央集権型取引所と呼ばれます)とは、仕組みが大きく異なる、新しいタイプの取引所なんです。
「DEXって、普通の取引所と何が違うの?」
「使うメリットはある? 注意点はないのかな?」
DEXは、DeFi(分散型金融)という、ブロックチェーンを使った新しい金融サービスの中心的な役割を担っています。
その仕組みを理解することは、暗号資産の世界をより深く知る上でとても役立ちます。
この記事では、「DEX(Decentralized Exchange)とは」何か、その基本的な考え方から、CEXとの違い、使われている技術、メリットやデメリット、そして今後の可能性まで、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
特定の取引所や暗号資産への投資をおすすめするものではありません。
あくまでDEXという技術や仕組みについての情報提供と、学習を目的としています。
DEX(分散型取引所)とは何か? 基本的な意味を知ろう
まず、「DEX(Decentralized Exchange)とは」何か、基本的なところから見ていきましょう。
DEXがどんなものか、その核心となる考え方をつかむところから始めますね。
DEXを理解する上で、従来の取引所との違いを知ることがポイントになります。
中央管理者がいない取引所
DEXの最も大きな特徴は、その名の通り「分散型」であることです。
つまり特定の会社や組織のような「中央管理者」が存在しない暗号資産取引所である、という点です。
一般的な暗号資産取引所(CEX)は、企業が運営しています。
利用者の資産を預かり、取引の注文を管理し、売買を仲介します。
しかし、DEXでは、このような中央管理者を介さずに、利用者さん同士が直接、暗号資産を交換することができます。
管理者がいない、というのが大きなポイントですね。
P2P(ピアツーピア)での直接取引
DEXでは、取引はブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)を通じて、利用者さんから利用者さんへ(P2P ピアツーピア)直接行われます。
取引所という「場所」は提供されます。
しかし、取引の実行自体は当事者間で行われ、その記録はブロックチェーンに刻まれます。
自分の資産は、取引所に預けるのではありません。
自分自身のウォレット(お財布アプリなど)で管理したまま取引に参加するのが基本です。
この「管理者がいない」「利用者同士で直接取引」「自分で資産を管理」という点が、DEXを理解する上での重要なキーワードになります。
DEXはどのように機能する? その仕組みを探る
中央管理者がいないのに、どうやってDEXは取引を成立させ、安全性を保っているのでしょうか。
その裏側にある仕組みを探ってみましょう。
ブロックチェーン技術ならではの、賢い仕組みが使われていますよ。
DEXの動き方を理解するために、いくつかの重要な要素を見ていきます。
スマートコントラクトが仲介役
DEXの心臓部とも言えるのが、「スマートコントラクト」です。
スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で、あらかじめ決められたルールに従って自動的に実行されるプログラムのことです。
DEXでは、このスマートコントラクトが、取引の注文を受け付けたり、価格を決定したり、資産の交換を実行したりといった、従来の取引所が担っていた役割の多くを自動で実行します。
例えば、「Aさんが1ETHを3000USDCで売りたい」「Bさんが3000USDCで1ETHを買いたい」という注文があった場合を考えます。
スマートコントラクトが条件が一致したことを確認し、自動的にそれぞれの資産の交換を実行してくれる、といった具合です。
人の手を介さずに、プログラムがルール通りに取引を進めてくれるんですね。
ブロックチェーン上での記録
DEXで行われた取引の結果は、すべてブロックチェーン上に記録されます。
誰がいつ、どのトークンをどれだけ交換したか、といった情報が、改ざんできない形で公開(パブリックチェーンの場合)されます。
そのため、取引の透明性が非常に高いのが特徴です。
CEXのように、取引所の内部データベースだけで処理されるわけではないんですね。
記録が公開されているのは、信頼性につながるポイントです。
取引方法の違い AMMとオーダーブック
DEXで暗号資産を交換する方法(取引のメカニズム)には、主に二つのタイプがあります。
「AMM(自動マーケットメイカー)」方式と「オーダーブック」方式です。
それぞれ、取引の仕方が少し異なります。
どんな違いがあるか見てみましょう。
AMM(自動マーケットメイカー)とは?
現在、多くのDEXで主流となっているのが、AMM(Automated Market Maker)方式です。
これは、従来の取引所のように「買いたい人」と「売りたい人」の注文を直接マッチングさせる(板取引)のではありません。
「流動性プール」と呼ばれる、あらかじめ用意された暗号資産のペア(例えばETHとUSDCのペア)のプールに対して、利用者が直接トークンを交換(スワップ)する仕組みです。
トークンの価格は、そのプールの2種類のトークンの比率に基づいて、数式(アルゴリズム)によって自動的に決定されます。
例えば、プール内のETHが少なくなり、USDCが多くなれば、ETHの価格は自動的に上がり、USDCの価格は下がるといった具合です。
この仕組みにより、常に誰かしら(プール)と取引ができるため、「買い手や売り手が見つからない」という状況が起こりにくくなります。
Uniswap(ユニスワップ)やPancakeSwap(パンケーキスワップ)などが、このAMM方式を採用している代表的なDEXです。
オーダーブック方式のDEXとは?
もう一つが、従来の株式取引所やCEXなどでお馴染みの「オーダーブック」方式を採用したDEXです。
こちらは、「〇〇円で買いたい」「△△円で売りたい」といった利用者さんからの注文(オーダー)を、「板」と呼ばれる一覧に記録します。
価格と数量が一致する注文同士をマッチングさせて取引を成立させます。
指値注文(価格を指定する注文)や成行注文(価格を指定しない注文)などが可能です。
AMM方式に比べて、より細かい価格設定で取引したい場合などに適しています。
しかし、ブロックチェーン上でオーダーブックを管理・マッチングさせるのは技術的に複雑です。
処理速度やコストの面で課題があるため、AMM方式ほど広く普及はしていません。
dYdXなどがオーダーブック方式を採用している例として挙げられます。
最近では、両方の方式の利点を組み合わせようとするハイブリッド型のDEXも登場しています。
流動性プールと流動性提供者
AMM方式のDEXを支える上で欠かせないのが、「流動性プール(Liquidity Pool)」と「流動性提供者(Liquidity Provider, LP)」の存在です。
この仕組みがあるから、AMMはスムーズに動くんですね。
流動性プールとは?
流動性プールとは、AMMがトークンの交換を行うために、2種類(またはそれ以上)のトークンペアが大量に預けられている場所(スマートコントラクト)のことです。
例えば、「ETH/USDCプール」には、たくさんのETHとUSDCが預けられています。
利用者は、このプールに対してETHを預けてUSDCを受け取ったり、逆にUSDCを預けてETHを受け取ったりすることで、トークンの交換を行います。
プールが取引の相手になってくれるイメージですね。
流動性提供者(LP)とは?
では、このプールにトークンを預けているのは誰でしょうか。
それが「流動性提供者(LP)」です。
LPは、自分の持っているトークンペア(例えばETHとUSDC)を流動性プールに預け入れることで、そのプールの「流動性」(取引のしやすさ)を高めることに貢献します。
プールにトークンがたくさんあれば、利用者はいつでもスムーズに交換できますね。
LPは、その見返りとして、そのプールで行われた取引の手数料の一部を受け取ることができます。
これが、LPがトークンを預ける動機(インセンティブ)になります。
この仕組みによって、AMM方式のDEXは、常に取引可能なトークンの在庫(流動性)を確保しているのです。
DEXとCEX(中央集権型取引所)の違いは?
DEX(分散型取引所)の特徴をより深く理解するために、私たちが普段よく使うかもしれないCEX(中央集権型取引所、例えばCoincheckさんやbitFlyerさんなど)と比較してみましょう。
両者には、仕組みや使い勝手、リスクの性質などにおいて、いくつかの重要な違いがあります。
どちらが良い悪いではなく、違いを知ることが大切です。
資産の管理方法(カストディ)
これが最も大きな違いの一つです。
CEXでは、利用者は取引を行うために、自分の暗号資産を取引所が開設したウォレットに預け入れる必要があります。
つまり、取引中は、資産の管理権(秘密鍵の管理)を取引所に委託する形になります(カストディアル)。
一方、DEXでは、利用者は基本的に自分自身のウォレット(MetaMaskなど)をDEXのプラットフォームに接続し、自分のウォレットから直接取引を行います。
取引が完了するまで、資産は自分の管理下にあります(ノンカストディアル、セルフカストディ)。
自分で資産を管理し続けられる点は、DEXの大きな魅力です。
どちらの管理方法が自分に合っているか、考えるポイントですね。
セキュリティの考え方
CEXは、企業が運営しているため、サーバーセキュリティや顧客資産の管理体制など、企業としてのセキュリティ対策が重要になります。
もし取引所自体がハッキングされたり、内部不正があったりすると、預けていた資産が失われるリスクがあります(カウンターパーティリスク)。
企業の信頼性が問われますね。
DEXは、スマートコントラクトに基づいて自動で運営されるため、取引所自体のハッキングリスクは理論上低いと考えられます。
しかし、スマートコントラクトのプログラムにバグや脆弱性があった場合、それを突かれてプール内の資金が盗まれるリスクがあります。
プログラムの安全性も重要です。
また、利用者さん自身がウォレットの秘密鍵を管理するため、自己管理の責任が重くなります。
秘密鍵を紛失したり、盗まれたりすると、資産を取り戻すことは極めて困難です。
どちらが良いというより、リスクの種類が異なる、と考えるのが良いでしょう。
匿名性とKYC(本人確認)
CEXを利用する場合、通常、口座開設時にKYC(Know Your Customer、本人確認)の手続きが必要です。
氏名、住所、身分証明書などを提出し、取引所は利用者の情報を把握します。
これは、マネーロンダリング対策などの規制に対応するためです。
DEXの多くは、利用にあたってKYCを必要としません。
ウォレットを接続するだけで取引を開始できるため、匿名性(仮名性)が高いと言えます。
プライバシーを重視する利用者さんにとってはメリットです。
しかし、規制当局からはマネーロンダリングなどに利用されるリスクが指摘されることもあります。
取り扱いトークンと上場プロセス
CEXでは、取引所が審査を行い、上場させるトークンを決定します。
比較的メジャーな、信頼性が確認されたトークンが中心になる傾向があります。
上場には厳しい基準があることが多いです。
DEX、特にAMM方式のものでは、誰でも比較的自由に新しいトークンの流動性プールを作成し、取引を開始することができます(パーミッションレス)。
そのため、CEXには上場していないような、新しくてマイナーなトークン(いわゆる草コイン)が非常に多く取引されています。
これは新しいプロジェクトに早期にアクセスできる機会がある一方で、詐欺的なトークンや価値のないトークンに遭遇するリスクも高いことを意味します。
自由度が高い分、注意も必要ですね。
手数料の構造
CEXでは、取引ごとに「取引手数料」がかかるのが一般的です。
これは取引所が設定します。
DEXでは、取引手数料(スワップ手数料)は、主に流動性提供者(LP)への報酬として支払われます。
これに加えて、取引をブロックチェーンに記録するための「ネットワーク手数料(ガス代)」が別途必要になります。
ネットワーク手数料は、ブロックチェーンの混雑状況によって大きく変動します。
そのため、特にイーサリアム上のDEXなどでは、ガス代が高騰すると少額の取引がしにくくなる場合があります。
手数料の仕組みも大きく異なりますね。
これらの違いを理解して、自分の目的やリスク許容度に合った取引所を選ぶことが大切ですね。
DEXを使うメリットは? どんな良い点がある?
中央集権的な管理者を介さず、ブロックチェーン上で直接取引を行うDEXには、CEXにはない独自のメリットがあります。
どんな良い点があるのか、見ていきましょう。
自由度の高さや新しい可能性が魅力かもしれません。
自分で資産を管理できる(セルフカストディ)
DEXの最大のメリットの一つは、取引中も自分の資産(暗号資産)を自分自身のウォレットで管理し続けられることです(ノンカストディアル)。
取引所に資産を預ける必要がないため、取引所のハッキングや倒産によって資産を失うリスク(カウンターパーティリスク)を回避できます。
自分の資産は自分で守る、というWeb3の考え方を体現していますね。
これは大きな安心感につながるかもしれません。
カウンターパーティリスクの低減
上記のセルフカストディと関連しますが、取引の相手方が取引所という単一の組織ではないため、その組織の信用リスクや運営リスクの影響を受けにくいと考えられます。
取引はスマートコントラクトによって自動執行されるため、相手が約束通りに資産を渡してくれるか、といった心配をする必要が(理論上は)ありません。
プログラムがルール通りに動くことを信頼する形ですね。
誰でも利用可能(パーミッションレス)
多くのDEXは、特定の国や地域に住んでいるか、あるいは本人確認(KYC)が完了しているか、といった条件なしに、ウォレットとインターネット接続があれば誰でも利用できます(パーミッションレス)。
これは、銀行口座を持てない人々や、金融サービスへのアクセスが制限されている地域の人々にとっても、新しい金融参加の機会を提供する可能性があります。
より開かれた金融システムと言えるかもしれません。
プライバシーの可能性
KYCが不要なDEXが多いため、利用者のプライバシーが比較的保護されやすい環境と言えます。
取引はアドレス(仮名)で行われ、個人情報と直接結びつくことはありません。
プライバシーを重視する方には魅力的な点です。
ただし、ブロックチェーン上の取引履歴は公開されているため、完全な匿名性が保証されるわけではない点には注意が必要です。
新しいトークンへのアクセス
DEXでは、CEXに上場される前の新しいプロジェクトのトークンや、非常にマイナーなトークンが数多く取引されています。
これは、新しい有望なプロジェクトを早期に発見し、参加する機会があることを意味します。
未来の有望株を見つけられるかもしれません。
しかし、同時に詐欺的なトークンや価値のないトークンも多く存在するため、十分な調査と注意(DYOR Do Your Own Research)が不可欠です。
チャンスとリスクは表裏一体ですね。
DEXのリスクと課題
多くの魅力を持つDEXですが、その分散的で新しい仕組みゆえの、特有のリスクや課題も存在します。
利用する際には、これらの点を十分に理解しておくことがとても大切です。
便利な反面、注意すべき点もしっかり見ていきましょう。
操作の難しさ(ユーザーエクスペリエンス)
DEXを利用するには、まず自分でウォレットを作成し、秘密鍵やシードフレーズを安全に管理する必要があります。
DEXのプラットフォームにウォレットを接続し、トランザクションに署名するといった操作も、暗号資産取引に慣れていない人にとっては、少し難しく感じられるかもしれません。
CEXのような手厚いカスタマーサポートも期待できません。
操作ミスによる資産損失のリスクは、すべて自己責任となります。
ユーザーエクスペリエンス(使いやすさ)の向上は、DEX普及のための大きな課題です。
自分で管理する責任が伴いますね。
ガス代(ネットワーク手数料)の問題
DEXでの取引(スワップや流動性提供など)は、ブロックチェーン上でのトランザクション実行を伴います。
そのため、取引手数料とは別に、ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代)がかかります。
特にイーサリアムのような人気のブロックチェーンでは、ネットワークが混雑するとガス代が非常に高騰することがあります。
少額の取引を行いたい場合、ガス代の方が高くついてしまう、という事態も起こりえます。
このガス代問題は、DEXの利用をためらわせる要因の一つとなっています。
(レイヤー2 DEXなど、この問題を解決しようとする動きもあります。)
手数料の変動には注意が必要ですね。
インパーマネントロス(変動損失)のリスク
AMM方式のDEXで流動性提供(LP)を行う場合、「インパーマネントロス(Impermanent Loss、変動損失)」という特有のリスクに注意が必要です。
これは、流動性プールに預けたトークンペアの価格比率が、預けた当初から大きく変動した場合に発生する可能性のある損失のことです。
具体的には、「プールに預けていた場合」の資産価値が、「もし預けずにそのまま二つのトークンを持ち続けていた場合」の資産価値よりも低くなってしまう現象を指します。
価格変動が大きいほど、インパーマネントロスの影響も大きくなる傾向があります。
LPは取引手数料を報酬として得られます。
しかし、価格変動によっては、手数料収入よりもインパーマネントロスの方が大きくなってしまう可能性もあるのです。
「Impermanent(一時的な)」という名前がついていますが、価格比率が元に戻らなければ、損失は確定してしまいます。
LPになる際には、このリスクを十分に理解しておく必要があります。
流動性提供はリターンだけでなくリスクもあるんですね。
スマートコントラクトの脆弱性リスク
DEXの機能は、スマートコントラクトというプログラムによって実現されています。
このスマートコントラクトにバグや設計上の欠陥(脆弱性)があった場合、悪意のある攻撃者によって悪用され、流動性プール内の資金が盗まれてしまうリスクがあります。
過去にも、有名なDEXやDeFiプロトコルがスマートコントラクトの脆弱性を突かれてハッキング被害に遭った事例は少なくありません。
DEXを利用する際には、そのプロトコルの監査状況やセキュリティ対策について、可能な範囲で確認することが望ましいです。
しかし、一般利用者さんにとっては難しい面もあります。
プログラムの安全性も確認が必要ですね。
処理速度とスリッページ
ブロックチェーンのトランザクション承認には時間がかかるため、DEXでの取引確定もCEXに比べて時間がかかる場合があります。
また、特に流動性の低いトークンペアや、大きな金額を一度に交換しようとした場合、注文した価格と実際に約定した価格の間にズレが生じる「スリッページ」が発生しやすくなります。
これは、自分の取引によってプールの価格が変動してしまうために起こります。
思った通りの価格で取引できない可能性も考慮が必要です。
フロントランニングのリスク
ブロックチェーン上の取引は、承認される前にメモリプールで待機状態になります。
悪意のある者は、このメモリプールを監視し、有利な取引(例えば、大きな買い注文)を見つけると、その取引が実行される直前に、より高いガス代を設定して自分の注文を割り込ませ、価格が動いた後に利益を得ようとする「フロントランニング」と呼ばれる攻撃を行う可能性があります。
これはDEXにおける潜在的なリスクの一つです。
取引が他の人に見られている可能性も意識する必要があります。
規制の不確実性
DEXやDeFiに対する法規制は、まだ世界的に見ても発展途上であり、不確実な部分が多く残されています。
国によっては、DEXの利用が制限されたり、将来的に規制が強化されたりする可能性もあります。
KYC/AML要件がDEXにも適用されるようになるかなど、今後の規制動向には注意が必要です。
法律やルールが変わる可能性も考えておく必要がありますね。
これらのリスクや課題を理解し、自己責任の原則のもとで利用することが、DEXと付き合っていく上で重要になりますね。
代表的なDEXの例
現在、様々なブロックチェーン上で、数多くのDEXが運営されています。
ここでは、特に有名で広く利用されているDEXの例をいくつか、コンセプトと共に紹介します。
特定のプラットフォームを推奨するものではありません。
どんなDEXがあるか知っておくと、選択肢が広がりますね。
Uniswap(ユニスワップ): イーサリアムブロックチェーン上で最も代表的なAMM方式のDEXの一つです。
シンプルなインターフェースと、誰でも自由にトークンペアの流動性プールを作成できるオープンさが特徴で、多くのDeFiプロジェクトのトークンが最初に取引される場所となっています。
DeFiの草分け的存在ですね。
PancakeSwap(パンケーキスワップ): BNB Smart Chain(旧 Binance Smart Chain)上で最も人気のあるAMM方式のDEXです。
イーサリアムに比べてガス代が安いという利点から、多くの利用者を獲得しました。
トークン交換だけでなく、イールドファーミングや宝くじなど、多様な機能を提供しています。
BNBチェーンを使うならチェックしたいDEXです。
SushiSwap(スシスワップ): Uniswapから派生(フォーク)して生まれたDEXで、イーサリアムをはじめとする複数のブロックチェーンに対応しています(マルチチェーン)。
流動性提供者へのインセンティブ設計などに特徴があります。
マルチチェーン対応は便利ですね。
Curve Finance(カーブファイナンス): 主にステーブルコイン(米ドルなどに価値が連動する暗号資産)同士の交換に特化したAMM方式のDEXです。
ステーブルコイン間のスリッページ(価格のズレ)を最小限に抑えるアルゴリズムを採用しているのが特徴です。
ステーブルコインの交換に強みがあります。
これらはほんの一例であり、他にも多くのユニークな特徴を持つDEXが存在します。
それぞれのDEXが動作するブロックチェーンや、採用している仕組み、取り扱っているトークンなどは異なります。
利用する際は、それぞれの特徴をよく調べてみてくださいね。
DEXのこれから
DEXは、DeFiエコシステムの中心的な存在として、急速に発展してきました。
その未来は、ブロックチェーン技術全体の進化と密接に関わっています。
これからDEXはどのように進化していくのでしょうか。
未来の金融の形を占う上で、DEXの動向は目が離せません。
スケーラビリティと利便性の向上
現在、DEXが抱える大きな課題であるガス代の高さや処理速度の遅さ(スケーラビリティ問題)を解決するための取り組みが活発です。
イーサリアムのレイヤー2ソリューション(zk-RollupやOptimistic Rollupなど)上で動作するDEXが増えることで、より高速で低コストな取引体験が実現されると期待されています。
利用者さんにとっての操作の難しさ(UX)も、ウォレットアプリの進化などによって、徐々に改善されていくでしょう。
CEXのような使いやすさを目指す動きも見られます。
もっと使いやすく、安くなるのは嬉しいですね。
相互運用性(クロスチェーン)の発展
異なるブロックチェーン間での資産の移動や交換をスムーズに行う「相互運用性(インターオペラビリティ)」の技術が進歩することで、DEXの可能性はさらに広がります。
特定のチェーンに縛られずに、様々なブロックチェーン上のトークンを一つのDEXでシームレスに交換できるようになるかもしれません(クロスチェーンDEX)。
これにより、DeFiエコシステム全体がより統合され、利便性が向上することが期待されます。
チェーンの垣根を越えた取引が当たり前になるかもしれません。
規制との向き合い方
DEXやDeFiに対する規制の動向は、今後の発展を左右する重要な要素です。
完全に分散化されているDEXに対して、どのように規制を適用していくのか、世界中で議論が続いています。
KYC/AML要件の導入、運営に関わるDAO(分散型自律組織)への規制など、様々な可能性が考えられます。
技術の革新性と、利用者保護や市場の健全性を求める規制との間で、どのようなバランスが見出されていくのか、注目が集まります。
規制に対応しつつ、DEXの持つメリットを維持していくための新しいアプローチも模索されていくでしょう。
ルール作りと技術革新のバランスが重要になりそうです。
DEXは、中央集権的な仲介者を必要としない、新しい金融取引の形を提供する可能性を秘めています。
課題を克服し、技術が成熟していく中で、私たちの金融システムや資産のあり方に、より大きな変化をもたらしていくかもしれません。
まとめ DEXを理解する
今回は、「DEX(Decentralized Exchange)とは」何か、その基本的な意味から、CEXとの違い、AMMやオーダーブックといった仕組み、流動性プール、インパーマネントロス、そしてメリットやリスク、今後の展望まで、詳しく見てきました。
DEXは、中央管理者を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて利用者さん同士が直接暗号資産を交換できる分散型取引所です。
自分で資産を管理できる(セルフカストディ)、誰でも利用できる(パーミッションレス)、透明性が高いといったメリットがある一方で、操作の難しさ、ガス代、インパーマネントロス、スマートコントラクトのリスクといった課題も抱えています。
AMM方式が主流ですが、オーダーブック方式やハイブリッド型も存在します。
ICOやIEOとは異なり、取引そのものを行うプラットフォームである点が特徴です。
DEXの仕組みや特性、そしてCEXとの違いを理解することは、DeFiやWeb3といった、ブロックチェーン技術がもたらす新しい潮流を読み解く上で、とても重要です。
技術はまだ発展途上ですが、その可能性に注目が集まっています。
免責事項
この記事は、DEX(分散型取引所)に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定のDEXプラットフォーム、暗号資産、トークン、または投資戦略を推奨・勧誘するものではありません。
DEXの利用や関連する暗号資産への投資、流動性提供には、スマートコントラクトのリスク、インパーマネントロスのリスク、価格変動リスク、操作ミスによる資産損失のリスクなど、様々な高いリスクが伴います。
投資した資金の全額または一部を失う可能性もあります。
本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為の結果についても、筆者および関係者は一切の責任を負いかねます。
技術の評価や利用、投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討の上で行ってください。
必要に応じて、技術や金融の専門家にご相談することをお勧めします。








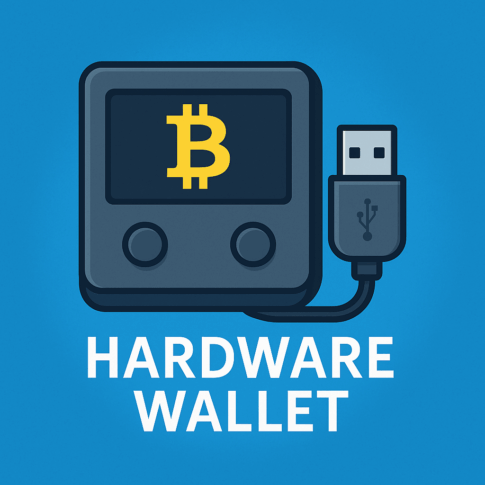







の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す