「ライトコインって、聞いたことはあるけど詳しくは知らない…」
「ビットコインとは何が違うの?」
「暗号資産に興味があるけど、何から学べばいいか分からない…」
もし、あなたが少しでもこのように感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
この記事では、数ある暗号資産の中でも歴史のある「ライトコイン」について、その誕生の背景から基本的な仕組み、そしてビットコインとの興味深い違いまで、初心者の方にも分かりやすく、そして楽しく学べるように解説していきます。
読み終わる頃には、きっとライトコインや暗号資産について、もっと知りたくなるはずですよ。
ライトコインってどんなもの?基本的な特徴を見てみよう
ライトコインがこの世に登場したのは、2011年の10月です。
作ったのは、チャーリー・リーさんという、元々はGoogleで働いていたエンジニアの方なんですよ。
リーさんは、ビットコインの設計図(ソースコード)を元にして、ライトコインを開発しました。
しかし、ただ真似しただけではありません。
ビットコインをもっと使いやすくするために、いくつかの改良を加えたんです。
特に、お店での支払いなど、日常的な場面でスムーズに使えるように、決済のスピードを上げることを目指していました。
ビットコインは「価値を保存しておく」イメージが強いかもしれません。
ですが、ライトコインは最初から「支払い手段」としての使いやすさを考えて作られた、そんな暗号資産なんですね。
ライトコインを支える技術 ブロックチェーンってなんだろう?
ライトコインが安全に取引できるのは、「ブロックチェーン」という技術のおかげです。
これはビットコインなど、多くの暗号資産で使われている、とても大切な仕組みなんですよ。
ブロックチェーンを簡単に説明すると、取引の記録を「ブロック」という箱に入れて、それを順番に「チェーン(鎖)」で繋いでいくようなイメージです。
この記録は世界中のコンピューターに分散して保存されるので、誰か一人が情報を書き換えたり、悪いことをしたりするのが、とても難しくなっています。
特定の会社や銀行のような中央管理者がいなくても、みんなで監視し合うことで、安全な取引を実現しているんですね。
ライトコインの全ての取引も、このブロックチェーンの上にしっかりと記録されています。
だから、私たちは安心してライトコインを使ったり、送ったりすることができるわけです。
この「分散型」という考え方が、これまでの金融システムとは違う、暗号資産の面白いところの一つです。
ビットコインとはここが違う ライトコインの独自性
ライトコインはビットコインを参考に作られましたが、もちろん違いもあります。
ここでは、ライトコインが持つユニークな点、ビットコインとの主な違いをいくつか見ていきましょう。
これらの違いを知ることで、ライトコインの個性がよりはっきりと見えてくるはずです。
取引スピードの違い もっと早く!を目指したライトコイン
まず大きな違いとして挙げられるのが、取引が承認されるまでの時間です。
ビットコインの場合、取引が確定する(ブロックが生成される)までに、平均で約10分かかると言われています。
少し時間がかかりますよね。
しかし、ライトコインはこの時間をぐっと短縮して、約2.5分にしたんです。
単純計算で、ビットコインの約4倍のスピードということになります。
この速さのおかげで、例えばお店でちょっとした買い物をするときなど、スピーディーな決済が求められる場面で、ライトコインは便利に使える可能性があると考えられています。
「もっと早く、もっと便利に」というライトコインの想いが、この部分に表れていますね。
マイニング方法の違い コインを生み出す仕組み
次に、新しいコインを発行したり、取引を承認したりする「マイニング」という作業で使われる計算方法(アルゴリズム)にも違いがあります。
ビットコインでは「SHA-256」というアルゴリズムが使われています。
これに対して、ライトコインは「Scrypt(スクリプト)」という、ちょっと違うタイプのアルゴリズムを採用しました。
このScryptは、計算するときにメモリ(記憶装置)をたくさん使うという特徴があります。
開発された当初、チャーリー・リーさんは、高価な専用マシン(ASIC)を持っている人だけがマイニングを独占してしまうのを避けたかったようです。
Scryptを採用することで、普通のパソコン(CPUやGPU)でもマイニングに参加しやすくして、より多くの人がネットワーク運営に関われるように、と考えたんですね。
ネットワークの公平性を保とうとした工夫と言えるでしょう。
ただし、技術はどんどん進歩するので、後にはScryptに対応した専用マシンも登場することになりました。
発行される枚数の違い 上限が決まっている
最後に、世の中に存在するコインの最大枚数にも違いがあります。
ビットコインは、最終的に発行される枚数が2100万枚と決められています。
一方、ライトコインはその4倍、8400万枚が上限として設定されているんです。
発行される枚数が多いということは、一般的に、コイン1枚あたりの価格がビットコインよりも低くなる傾向があるかもしれません。
もちろん、価格は需要と供給のバランスで決まるので、一概には言えません。
ですが、この発行枚数の違いも、二つのコインの個性を形作る要素の一つになっています。
ライトコインはビットコインのテスト役?先進技術の導入
ライトコインは、ビットコインの弟分と言われるだけではありません。
実は、新しい技術をビットコインより先に試す「テストの場」のような役割を果たしてきた側面もあるんです。
例えば、「SegWit(セグウィット)」という、取引の処理能力を上げるための技術があります。
あるいは、「ライトニングネットワーク」という、もっと速くて安い手数料で少額決済を可能にする技術もあります。
これらの重要な技術は、実はビットコインに導入されるよりも前に、ライトコインで先に採用され、実際に使われていたんですよ。
ライトコインが新しい技術に積極的に挑戦してきたことがわかりますね。
ライトコインについて学ぶということ
ここまで、ライトコインの特徴や仕組み、ビットコインとの違いなどを見てきました。
ライトコインは、ビットコインの基本的な考え方を引き継ぎながら、決済スピードの向上などを目指して独自の進化を遂げてきた暗号資産です。
その背景には、ブロックチェーンという革新的な技術があります。
暗号資産の世界は、日々変化していて、将来どうなるかを確実に予測することは誰にもできません。
コインの価値も常に変動しています。
しかし、ライトコインのような代表的な暗号資産が、どんな仕組みで動き、どんな歴史を持っているのかを知ることは、とても意味のあることだと考えられます。
デジタル通貨やブロックチェーン技術が、これからの社会や経済にどんな変化をもたらす可能性があるのか、そのヒントを与えてくれるかもしれません。
投資を勧めるものではありません。
あくまで、新しい技術や仕組みについて知るための情報収集、学習の一環として、ライトコインや暗号資産の世界に触れてみてはいかがでしょうか。
免責事項
当記事は、暗号資産に関する情報の提供を目的としており、特定の金融商品の投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。暗号資産の取引には価格変動リスク等があり、元本を失う可能性があります。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断で行ってください。当記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



の仕組み-485x254.png)

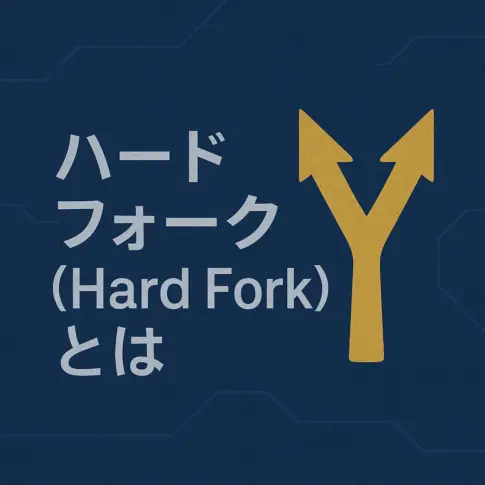


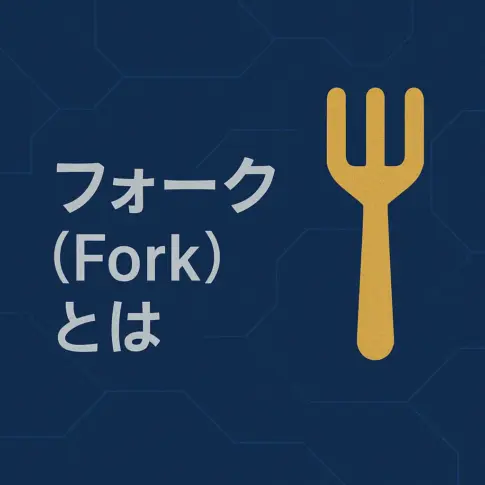
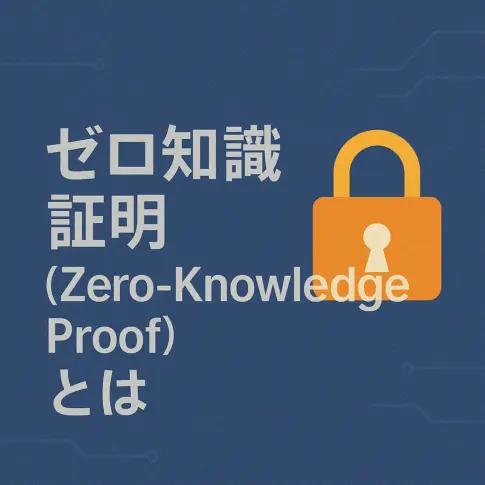






って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す