「マイニングって最近よく聞くけど、一体どんなものなんだろう?」
「ブロックチェーンと関係があるみたいだけど、仕組みがよくわからない…」
「暗号資産(仮想通貨)に興味があるけど、専門用語が多くて難しい…」
もし、あなたがこのように感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
この記事では、暗号資産の世界でとても重要な「マイニング」について、専門的な言葉をできるだけ使わずに、基礎からわかりやすく解説していきます。
マイニングがなぜ必要なのか、どんな仕組みで動いているのか、そして、これからどうなっていくのか。
読み終わる頃には、「なるほど、マイニングってそういうことだったのか!」とスッキリ理解できるよう、一緒に学んでいきましょう。
マイニングって、そもそもどういう意味? なぜ「採掘」と呼ばれるの?
まず、「マイニング」という言葉の意味からお話ししますね。
英語の「Mining」は、日本語で「採掘」という意味です。
金や銀を地面から掘り出す、あの採掘ですね。
暗号資産の世界で使われるマイニングは、新しく行われた取引のデータが正しいかどうかを確認して、その記録を「ブロックチェーン」というみんなが見られる台帳に書き加えていく作業のことを指します。
この作業をする人たちのことを「マイナー」つまり「採掘者」と呼びます。
なぜ「採掘」かというと、マイナーさんたちは、とても難しい計算問題を解くために、たくさんのコンピューターパワーと電気を使います。
まるで、たくさんの労力を使って地面から貴金属を掘り出すみたいですよね。
最初に問題を解いた人だけが、新しい取引記録を台帳に追加する権利と、ご褒美(報酬)をもらえます。
大変な作業をして、価値あるもの(新しい暗号資産)を手に入れるところが、貴金属の採掘に似ていることから「マイニング」と呼ばれるようになったんです。
マイニングはどんな仕組みで動いているの? 計算競争の「Proof of Work」を知ろう
マイニングが実際にどうやって動いているのか、その仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。
暗号資産にはいくつか種類があって、それぞれ少しずつ仕組みが違いますが、一番有名で、ビットコインも使っているのが「Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)」、略してPoWという方法です。
PoWのキホン 計算パワーで新しいブロックを作る競争
PoWの仕組みの中では、マイナーさんたちがみんなで計算競争をします。
まず、ネットワークで行われた新しい取引データを集めて、それが正しいかチェックします。
次に、チェック済みの取引データと、「ナンス」という特別な数字を組み合わせて、「ハッシュ関数」という計算機にかけます。
ハッシュ関数は、入れたデータから、予測できない別の文字列(ハッシュ値)を作り出す魔法の箱のようなものです。
少しでも元のデータが違うと、全く違うハッシュ値が出てきます。
マイナーさんたちの目標は、このハッシュ計算を何度も繰り返して、「ある特定の条件を満たすハッシュ値」を誰よりも早く見つけることです。
例えば、「ハッシュ値の先頭にゼロが10個並ぶ」みたいな条件ですね。
この条件に合うハッシュ値を見つけるのはとても大変で、コンピューターに膨大な計算をさせる必要があります。
この計算問題の難しさは、ネットワーク全体の計算能力に合わせて自動で調整されるんですよ。
ビットコインだと、大体10分に1回、誰かが正解を見つけられるくらいの難しさになっています。
正解者が取引を記録する権利をゲット
一番最初に正しいハッシュ値、つまり計算問題の「解き方」を見つけたマイナーさんが、自分がチェックした取引データをひとまとめにした「ブロック」という箱を作ります。
そして、その新しいブロックを、今までの取引記録が連なっている「ブロックチェーン」の一番後ろにくっつける権利をもらえます。
この新しいブロックには、一つ前のブロックの情報も含まれているので、ブロック同士が鎖のようにつながって、後から誰かがデータを書き換えるのが、ものすごく難しくなっているんです。
PoW以外の方法もあるの? 省エネな「Proof of Stake」
ちなみに、マイニングの仕組みはPoWだけではありません。
「Proof of Stake(プルーフ・オブ・ステーク)」、略してPoSという方法もあります。
PoSは、計算能力を競う代わりに、その暗号資産をたくさん持っている人や、長く持っている人が、新しいブロックを承認する権利を得やすい仕組みです。
PoWと比べて、使う電気の量がずっと少ないのが特徴です。
PoWのマイニングでは、専用の高性能コンピューター(ASIC)や、ゲーム用の高性能グラフィックボード(GPU)がたくさん使われます。
これらは動かすのに大量の電気を使うので、地球環境への影響も心配されている点です。
マイニングが果たしている大切な役割って何?
マイニングは、ただ計算しているだけでは無いんです。
暗号資産のシステム全体にとって、なくてはならない、いくつかの重要な役割を担っています。
役割その1 取引が正しいことを証明して記録する
マイニングの一番基本的なお仕事は、ネットワークで行われた取引が「本当に正しいですよ」と証明して、それを記録することです。
例えば、「AさんがBさんに1ビットコイン送りました」という取引があったとします。
マイナーさんは、Aさんが本当に1ビットコイン持っているか、同じビットコインを他の人にも送ろうとしていないか(二重支払い)などをしっかりチェックします。
そして、PoWの計算競争に勝ったマイナーさんが、チェック済みの正しい取引記録を新しいブロックにまとめて、ブロックチェーンに書き込みます。
一度ブロックチェーンに書かれた記録は、後から消したり書き換えたりすることが、ほぼできません。
これによって、銀行のような中心的な管理者がいなくても、みんなで取引の正しさを確認しあい、記録を守ることができるんです。
これが暗号資産の信頼性の基礎になっています。
役割その2 新しい暗号資産を生み出して世の中に供給する
マイニングには、もう一つ大切な役割があります。
それは、新しい暗号資産を生み出すことです。
計算競争に勝って、新しいブロックを作ることに成功したマイナーさんには、ご褒美として、新しく作られた暗号資産がプレゼントされます。
これを「ブロック報酬」と呼びます。
ビットコインの場合、このブロック報酬は、約4年ごとに半分になるようにプログラムされています。
「半減期」って聞いたことありませんか。
これによって、新しく生まれるビットコインの量がだんだん減っていき、最終的な発行枚数に上限が設けられているんです。
マイナーさんは、このブロック報酬の他に、取引をする人が支払う「取引手数料」も報酬としてもらえます。
将来、ブロック報酬がどんどん少なくなっていくと、この取引手数料がマイナーさんの主な収入源になると考えられています。
マイニングとブロックチェーンは一心同体? その深い関係性
マイニングとブロックチェーンは、お互いにとってなくてはならない、とても深い関係にあります。
ブロックチェーン技術は、取引の記録を「ブロック」という箱に入れて、それを順番に、暗号技術を使って鎖(チェーン)のようにつなげていくことで、みんなで情報を管理する技術です。
データが公開されていて透明性が高く、一度記録されると改ざんがとても難しいのが特徴です。
マイニング、特にPoWは、このブロックチェーンに新しいブロックを追加していくための、具体的な作業プロセスのことです。
マイナーさんたちの計算競争と、その結果による合意によって、どの取引記録を次のブロックとしてチェーンにつなげるかが決まります。
マイニングが続けられることで、ブロックチェーンはどんどん長くなっていき、最新の正しい取引状態が保たれます。
もしマイニングが止まってしまったら、新しい取引を記録できなくなり、ブロックチェーンはその役割を果たせなくなってしまいます。
ブロックチェーンの「分散性」を支えるマイニング
さらに大切なポイントがあります。
それは、マイニングがブロックチェーンの「分散性」という特徴を支えていることです。
特定の会社や組織が全てを管理しているのではなく、世界中にいるたくさんのマイナーさんたちがブロックを作る作業に参加することで、権力がどこか一箇所に集中するのを防いでいます。
もしどこか一人の管理者が故障したり、悪意を持ったりしても、システム全体が止まったり、乗っ取られたりするリスクを減らすことができます。
このように、みんなで検証しあう分散化されたプロセスこそが、ブロックチェーン技術の強さと信頼を生み出している源泉なんですね。
マイニングに参加するには? 主な3つの方法
もし「マイニングに参加してみたい」と思ったら、どんな方法があるのでしょうか。
個人や会社がマイニングに参加する主な方法を3つご紹介します。
1. ソロマイニング 自分ひとりで挑戦
これは文字通り、自分一人、または自分の会社だけで、持っているコンピューターを使ってマイニングに挑戦する方法です。
もし運良く新しいブロックを見つけられたら、ブロック報酬と取引手数料を全部ひとり占めできます。
しかし、特にビットコインのような人気の暗号資産では、PoWの計算競争はものすごく激しいです。
個人のコンピューターパワーだけで成功するのは、かなり難しく、収入も不安定になりがちです。
2. プールマイニング みんなで協力して挑戦
こちらは、たくさんのマイナーさんたちが協力して、それぞれのコンピューターパワーを持ち寄って、チームでマイニングを行う方法です。
「マイニングプール」というチームに参加します。
チーム全体としてブロックを見つけることに成功したら、その報酬を、チームに貢献した計算パワーの量に応じて、みんなで分け合います。
ソロマイニングと比べて、報酬をもらえるチャンスがぐっと増えて、安定した収入を期待しやすくなります。
現在、個人のマイナーさんの多くが、このプールマイニングという形で参加しています。
3. クラウドマイニング 機材を持たずに参加
これは、自分で高価なマイニング専用の機械を買ったり、設置したり、管理したりする代わりに、マイニングを専門に行っている会社が持っている計算能力(ハッシュパワー)の一部を、期間を決めて借りる(買う)方法です。
専門知識や特別な設備がなくても、手軽にマイニングに参加できるのがメリットです。
ただし、サービスを提供している会社が信頼できるか、契約内容や手数料はどうなっているかなどを、よく確認する必要があります。
中には詐欺のようなサービスもあるので、利用する際は十分な注意が必要です。
マイニングが抱える課題と、これからのこと
マイニングは暗号資産にとって欠かせないものですが、解決すべき課題もいくつかあります。
課題1 大量の電気を使うことによる環境問題
特にPoWのマイニングは、膨大な計算をするために、とても多くの電気を消費します。
これが地球環境に与える影響について、世界中で心配の声があがっています。
持続可能な社会を目指す上で、大きな課題と見なされることも少なくありません。
この問題への対応として、太陽光発電などの再生可能エネルギーをもっと利用しようという動きや、PoWよりも電気を使わないPoSなどの新しい仕組みへ移行する動きが進んでいます。
課題2 計算能力が一部に集中してしまうリスク
マイニングで報酬を得るために、大きな会社などが、とても性能の高い専用コンピューター(ASIC)を大量に用意して、巨大なマイニング工場(マイニングファーム)を運営するケースが増えています。
マイニングプールの規模も大きくなっています。
もし、少数の大きなマイニングプールが、ネットワーク全体の計算能力の半分以上(51%以上)を支配してしまうと、理論上は「51%攻撃」という不正行為が可能になるリスクが指摘されています。
これは、悪意のあるグループが、不正な取引を承認したり、正しい取引を妨害したりすることです。
みんなで分散して管理するというブロックチェーンの理想と、現実の経済的な競争との間で、難しい問題が起きています。
課題3 国によって違うルールや規制
暗号資産やマイニングに対する法律やルールは、国や地域によって大きく違います。
環境への影響や、お金の流れへの影響を考えて、マイニング活動を制限したり、禁止したりする国もあります。
一方で、新しい産業として育てようとする国もあります。
こうした各国の規制の動きは、マイニング事業のやり方や、暗号資産市場全体に大きな影響を与える可能性があります。
課題4 技術はどんどん進化していく
先ほどお話ししたように、電気の消費量を減らすなどの理由から、PoWからPoSへ移行しようとしているプロジェクト(例えばイーサリアム)があります。
最初からPoSや、さらに新しい仕組みを採用している暗号資産も増えています。
これらの新しい技術は、マイニングのあり方自体を変えていくかもしれません。
将来的には、PoWを使ったマイニングの役割が、今よりも小さくなっていく可能性も考えられますね。
まとめ 進化を続ける暗号資産を支える大切な技術「マイニング」
さて、ここまで「マイニング」について、その意味から仕組み、役割、種類、そして課題まで、一緒に見てきました。
マイニングは、暗号資産の取引が正しいことを証明し、それをブロックチェーンというみんなの台帳に記録することで、システム全体の安全性や透明性、信頼性を支える、とても重要なプロセスです。
新しい暗号資産を世の中に送り出すという、経済的な役割も持っています。
特定の管理者がいなくても、ネットワークに参加するみんなで合意を作り、データを管理していく。
そんな分散型システムの実現に、マイニングとブロックチェーン技術は欠かせない存在です。
一方で、電気の消費問題や、計算能力の集中、国ごとの規制の違いといった課題もあります。
PoSへの移行など、技術も常に進化を続けています。
マイニングの仕組みや役割、そして今まさに起きている変化を知ることは、これから私たちの社会に、もっと広がっていくかもしれない暗号資産やブロックチェーン技術の可能性を理解する上で、きっと役に立つはずです。
免責事項
この記事は、暗号資産(仮想通貨)のマイニングに関する情報提供および学習を目的として作成されたものであり、特定の金融商品や投資行動を推奨、勧誘するものではありません。
暗号資産への投資やマイニングへの参加は、価格変動リスク、流動性リスク、ハッキングリスク、規制リスクなど、様々なリスクを伴います。
実際に取引や投資を行う際には、ご自身の判断と責任において、十分な情報収集と比較検討を行った上で、決定してください。
本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、作成者および関係者は一切の責任を負いません。




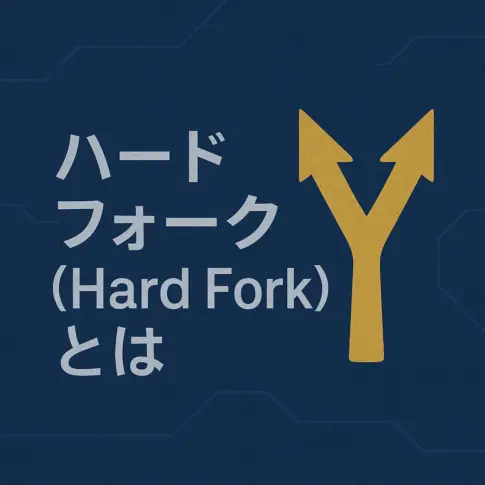

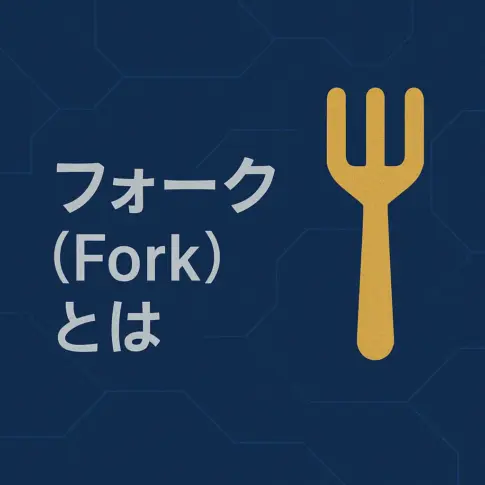



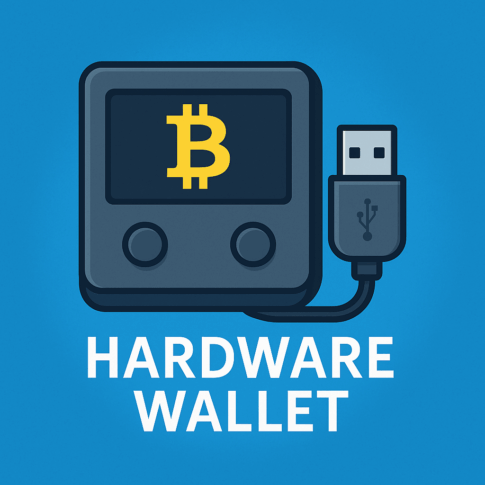





の仕組み-485x254.png)
って何?特徴や仕組み-485x256.webp)



コメントを残す