「暗号資産」や「ブロックチェーン」の関わりを見ていく中で、
「オンチェーン」というキーワード、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このオンチェーンという考え方は、暗号資産がどうやって動いているのかを理解する上で、とても大切なポイントになるんです。
この記事では、オンチェーンが一体何を指していて、どんな特徴があるのか、私たちのデジタルな活動にどんな影響を与えそうなのか、基本的な情報をわかりやすくお伝えして、皆さんと一緒に学びを深めていけたらと思っています。
オンチェーンのキホン ブロックチェーンとの関係って?
オンチェーンというのは、言葉の通り「ブロックチェーンの上で」という意味を持っています。
暗号資産の取引の記録だったり、「スマートコントラクト」っていうちょっと賢いプログラムが動いた記録だったり、色々なデータが「ブロックチェーン」というみんなが見られる大きなノートに直接書き込まれて、処理される状態のことなんですよ。
ブロックチェーンってどんなもの?
ブロックチェーンは、「分散型台帳技術」なんて呼ばれたりもします。
これは、どこか特定の会社や人が管理しているわけじゃなくて、インターネットにつながったたくさんのコンピューターが同じ情報を持ち合って、お互いにチェックすることで正しい記録を保っていく仕組みなんです。
このブロックチェーンの仕組みがあるからこそ、オンチェーンで処理されるデータは「確かにそうだね」ってみんなが納得できるものになるんですね。
オンチェーンで処理されること 主な特徴を見てみよう
オンチェーンで動いたり記録されたりするデータには、いくつか面白い特徴があるんです。
これらの特徴を知ると、オンチェーン技術がどんな可能性を秘めているのか、少しずつ見えてくるかもしれませんね。
みんなで見られる「透明性」
ブロックチェーンに書かれた取引の記録やデータは、基本的には誰でも見ることができますし、その内容を確かめることもできるんです。
もちろん、誰の取引かすぐには分からないように、お名前ではなくてアドレスという記号が使われていますが、お金の流れ自体は追いかけることができる場合があるんですよ。
書き換えられない「不変性」と「改ざん耐性」
一度ブロックチェーンに記録された情報は、後からこっそり変えたり、消したりすることが、ものすごく難しくなるように作られています。
このおかげで、記録されたデータの信頼性がグッと高まるんですね。
みんなで管理する「分散管理」
オンチェーンのデータは、どこか一箇所でまとめて管理されているわけではありません。
インターネットにつながっているたくさんのコンピューター(ノードって呼ばれます)が、それぞれデータを持ち合って、みんなで管理しているんです。
だから、もしどこか一つのコンピューターが止まっちゃっても、システム全体がダウンしてしまう心配が少ないと考えられています。
安心感につながる「セキュリティ」
これまでお話しした「透明性」や「書き換えられない性質」、「みんなで管理する仕組み」、これらに加えて、データを守るための特別な暗号技術が使われています。
これらの合わせ技で、悪い人が勝手に情報を盗んだり、データを書き換えたりすることに対して、とても強い守りが期待できると言われているんですよ。
オンチェーンで処理するってどんな良いことがあるの?
オンチェーンで取引したり、データを処理したりすることには、嬉しいポイントがいくつかあると考えられています。
どんなメリットがあるのか、一緒に見ていきましょうか。
信頼できてクリアな取引
すべての取引の記録が公開されていて、しかも書き換えるのがとても難しいので、取引の信頼性が高くて、内容もクリアになりやすいと言えるでしょう。
これは安心感につながりますよね。
誰かを介さずに直接やり取り
今までの金融の仕組みだと、銀行みたいな仲介役が間に入ることが多かったですよね。
でも、オンチェーンの世界では、P2P(ピアツーピア)といって、個人と個人の間で直接お金や価値を送り合うことができるようになるんです。
特定の誰かに頼らなくても、自由なやり取りが実現するかもしれないって、なんだかワクワクしませんか。
データが長く残りやすい「永続性」
ブロックチェーンのネットワークが動き続けている限り、そこに記録されたデータはずーっと残り続けると考えられています。
大切な記録が消えにくいっていうのは、大きなメリットですよね。
オンチェーン処理で気をつけておきたいことってある?
良いことばかりに見えるオンチェーン処理ですが、いくつか知っておきたいポイントもあるんです。 どんなことに気をつけたらいいのか、確認しておきましょう。
たくさんの処理は得意じゃない?「スケーラビリティ問題」
ブロックチェーンの上で処理する取引の量が増えてくると、ネットワーク全体の動きがゆっくりになったり、取引の確認に時間がかかったり、みんなが一斉に使うと道が混んじゃう、みたいなことが起きる可能性があるんです。
これを「スケーラビリティ問題」って呼んだりします。
手数料が高くなっちゃうことも「取引手数料(ガス代)の高騰」
ネットワークが混雑している時や、処理にたくさんのパワーが必要な複雑な取引をしようとすると、取引をスムーズに進めるために払う手数料(ガス代って呼ばれることもあります)が高くなってしまうことがあるんですね。
データがたくさん入らない?「データ容量の制約」
ブロックチェーンには、データを記録する箱(ブロックって言います)があって、その箱の大きさには限りがあるんです。
だから、ものすごくたくさんのデータをオンチェーンに保存しようとすると、それなりにお金がかかってしまう場合があるんですよ。
プライバシーは大丈夫?
すべての取引が公開されるっていうのは、透明性が高い反面、個々の取引の内容がみんなに見えちゃうっていうことで、プライバシーの確保がちょっと難しい側面があるって言われることもあります。
ですが、この点については、誰の取引か分かりにくくする技術や、プライバシーを特に大切に考えて作られたブロックチェーンも出てきているんですよ。
「オフチェーン」と比べるともっと分かりやすいかも
オンチェーンのことをもっと深く知るために、反対の言葉である「オフチェーン」と比べてみるのがおすすめです。
オフチェーンっていうのは、ブロックチェーンの外側で取引やデータの処理をする方法のことなんですよ。
処理する場所が違う
オンチェーンがブロックチェーンの上で処理するのに対して、オフチェーンはブロックチェーンの外にあるシステム、例えば取引所の内部データベースみたいなところを使います。
記録の仕方が違う
オンチェーンは、基本的にすべての取引をブロックチェーンに記録しようとします。
ですが、オフチェーンだと、取引の一部だけとか、最終的な結果だけをブロックチェーンに記録したり、あるいは全く記録しないこともあるんです。
透明性やスピード、手数料も違う
透明性でいうと、オンチェーンの方が高い傾向にあって、オフチェーンは関係者だけで情報を持つことが多いので、相対的に低いと言えますね。
処理のスピードは、一般的にオンチェーンがゆっくりになる傾向があって、オフチェーンは速い処理が得意です。
手数料も同じように、オンチェーンが高くなる傾向があって、オフチェーンは安く抑えられることが多いんですよ。
具体的な例で見てみよう
例えば、暗号資産を自分のウォレットから友達のウォレットに直接送るような場合や、DEX(分散型取引所)っていう特別な取引所で取引する場合、スマートコントラクトを動かす場合なんかは、オンチェーン処理の代表例です。
一方で、私たちがよく利用する多くの暗号資産取引所(CEX 中央集権型取引所って言います)では、ユーザーさん同士の頻繁な売買の注文は、取引所の内部データベースみたいなオフチェーンの仕組みで素早く処理されていることが多いんです。
そして、ユーザーさんが実際に暗号資産を自分の外部ウォレットに入れたり出したりする時に、オンチェーンでの取引が行われる、という流れが一般的ですね。
オンチェーンにはどんなデータが記録されているの?具体例を紹介
じゃあ、実際にどんな情報がオンチェーンに記録されているのか、いくつか例を見てみましょうか。
これを知ると、オンチェーンデータがどんなことに使えそうか、イメージが湧きやすくなるかもしれません。
暗号資産の送ったり受け取ったりの記録
どのアドレスからどのアドレスへ、どれくらいの暗号資産が、いつ送られたのか、といった情報が記録されています。 お金の流れが分かるんですね。
スマートコントラクトが動いた記録とその結果
ブロックチェーンの上で自動的に動くプログラムが、いつ、どんな風に実行されて、どんな結果になったのか、という記録です。
契約がちゃんと実行されたかどうかが分かります。
NFTの持ち主や移動の記録
デジタルアートとか、ゲームのアイテムみたいなNFT(非代替性トークン)が、今誰のもので、これまで誰の手に渡ってきたのか、という履歴が記録されています。
誰が本当の持ち主か分かるんですね。
DEX(分散型取引所)での取引の記録
どの暗号資産とどの暗号資産が、どれくらいの交換レートで取引されたのか、といった情報です。 どんな取引があったか確認できます。
これらのデータは、ブロックチェーンの仕組みのおかげで、みんなが見ることができて、確かめることができる形で記録されているんですよ。
オンチェーンデータ分析って何だろう?新しい情報活用の視点
ブロックチェーンの上に公開されている、これらのオンチェーンのデータを分析して、市場が今どんな状況なのか、プロジェクトは元気なのか、といったことに関するヒントを得ようとする試みを「オンチェーン分析」って呼んでいます。
オンチェーン分析をすることで、例えば下のようなことが分かると言われているんですよ。
市場の空気感を読んでみる
大きな資金を持っている投資家さんたちのウォレットの動きや、取引所にどれくらい資金が集まったり出て行ったりしているか、などを観察することで、市場に参加している人たちが今強気なのか弱気なのか、といった傾向を読み解こうとする分析があります。
市場のムードが分かるかもしれないんですね。
ネットワークが元気かチェックする
実際に使われているアドレスの数や、取引(トランザクションって言います)の数、ハッシュレート(マイニングっていう作業の計算能力のことです)なんかを調べることで、ブロックチェーンのネットワーク自体がどれくらい活発で、セキュリティはしっかりしているのかを評価しようとします。
ネットワークの健康診断みたいなものですね。
トークンの人気度や将来性を探る
特定のトークンが全部でどれくらいあって、市場にどれくらい出回っていて、しばらく動かされていないトークンはどれくらいあるのか、長い間持っている人はどれくらいいるのか、などを分析して、将来どんな風に価値が動くのかを予測するための一つの材料にする考え方もあります。
トークンの需要と供給のバランスが見えてくるかもしれません。
オンチェーン分析は、グラフとかで値動きを分析するテクニカル分析や、プロジェクトの内容を調べるファンダメンタル分析と並んで、暗号資産の市場を色々な角度から分析するための一つの方法として、だんだん注目されてきているんですよ。
まとめ オンチェーンが切り拓く未来とこれからのこと
「オンチェーン」っていうのは、暗号資産の取引や色々なデータが、ブロックチェーンっていう大きなノートに直接書き込まれて処理されることで、その透明さや書き換えられない強さ、みんなで管理する仕組みが、暗号資産の世界の信頼性や安全性を支える、とても大切な土台になっているんですね。
ですが、たくさんの処理をこなすのが得意じゃなかったり、取引の手数料が変動したりといった、実際に使っていく上での課題も分かってきています。
これらの課題を解決して、もっとたくさんの人が気持ちよく使えるようにするための技術開発も、活発に進められているんですよ。
例えば、オフチェーンの技術をうまく使った方法や、「レイヤー2スケーリングソリューション」って呼ばれる、ブロックチェーン本体(レイヤー1って言います)の負担を軽くしながら処理能力を上げるための技術なんかが代表的ですね。
オンチェーンで記録されるデータは、みんなが見られて確かめられるっていう性質から、新しい情報の使い方も広げています。
オンチェーンの仕組みを理解することは、暗号資産やブロックチェーン技術が私たちの生活や社会にどんな変化をもたらすのかを読み解く上で、これからますます大切になっていくと言えるでしょう。
この記事が、皆さんの理解の助けに少しでもなれたら嬉しいです。
・主な特徴は、透明性が高く、記録の改ざんが困難で、分散管理される点です。
・メリットとして信頼性の高さがありますが、処理速度や手数料に課題が生じることもあります。
・ブロックチェーン外で処理を行う「オフチェーン」とは対照的な仕組みです。
・公開されたオンチェーンデータは、市場分析など新しい情報活用に繋がります。
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品や暗号資産への投資を推奨するものではありません。
暗号資産への投資は価格変動リスクを伴い、元本を失う可能性があります。
投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行うようにしてください。
本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。
オンチェーン情報を学べる情報源
オンチェーンの概念や関連技術について解説している信頼性の高い情報源をご紹介します。
イーサリアム財団 (Ethereum Foundation):
https://ethereum.org/ja/developers/docs/
(トランザクションやブロック、スマートコントラクトに関する解説があります)




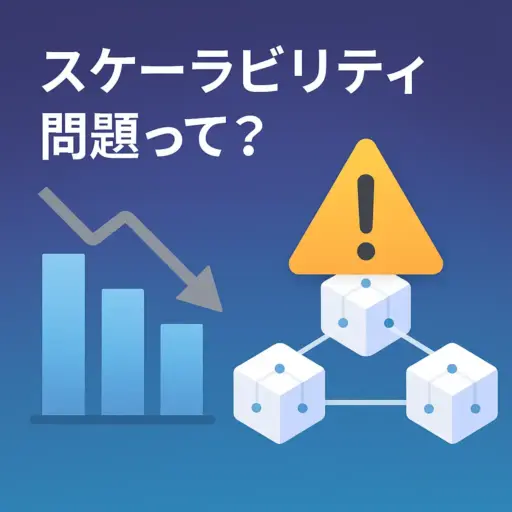

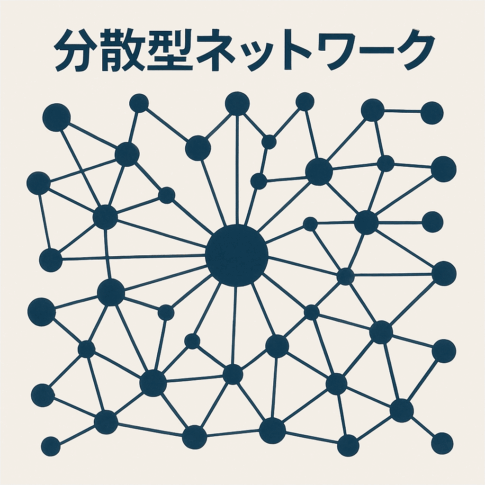

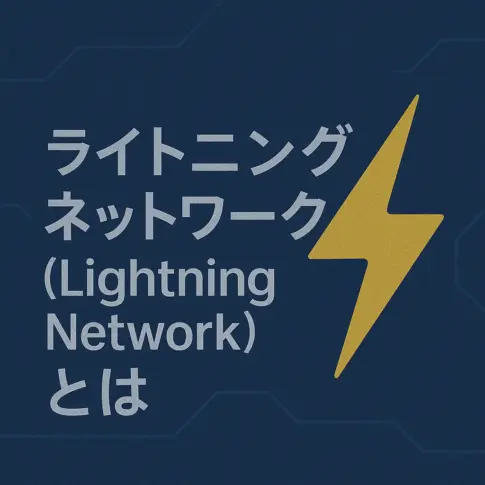

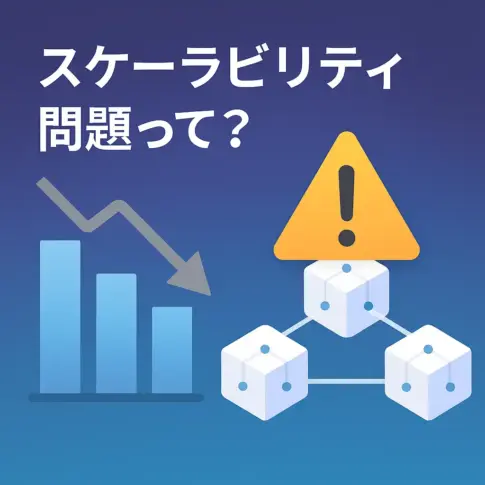

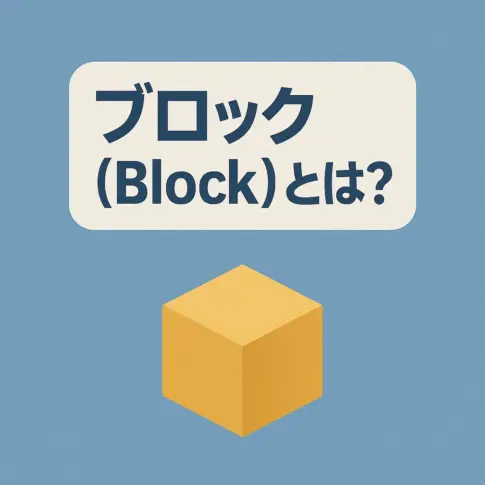









・透明で改ざん不可能?オンチェーン処理のすごい特徴をチェック!
・メリットだけじゃない!オンチェーンの注意点と可能性を学ぶ。
・オフチェーンとの違いは何?具体例でスッキリわかる!
・新しい情報活用術!オンチェーンデータ分析の世界を覗いてみよう。