「Trust Wallet(トラストウォレット)」について気になっていますか。
Trust Walletは、たくさんの種類のデジタル資産を自分で管理できる便利なツールの一つとして注目されています。
この記事では、Trust Walletが一体どんなものなのか、基本的な情報から特徴、使い方、そして利用する上で知っておきたいセキュリティのことまで、分かりやすくお伝えできればと思います。
特定の金融商品をオススメするものではなく、あくまで情報提供と学習を目的としていますので、その点を理解して読み進めてくださいね。
- 1 Trust Walletの基本情報 概要とこれまでの歩み
- 2 Trust Walletの主な特徴と便利な機能
- 3 Trust Walletのプラットフォーム モバイルアプリとブラウザ拡張機能
- 4 Trust Walletのセキュリティについて考える 大切な資産を守るために
- 5 Trust Walletの手数料について知っておこう
- 6 Trust Walletを始める前に知っておきたいこと 他の人の意見や比較情報
- 7 Trust Walletの最近の動きと今後の展望(参考として見てみよう)
- 8 Trust Walletのサポート体制とコミュニティ 困ったときはどうする?
- 9 まとめ Trust Walletを安全に使うために知っておきたいこと
Trust Walletの基本情報 概要とこれまでの歩み
Trust Walletについて知るために、まずは基本的な情報から見ていきましょう。
どのような背景で登場し、どんな特徴を持っているのでしょうか。
Trust Walletってどんなもの?
Trust Walletとは、一言で説明すると、ユーザー自身が「秘密鍵」という大切な情報を管理するタイプの暗号資産ウォレットです。
これをノンカストディアル型と呼びます。
この仕組みによって、利用者は自分の持っているデジタル資産を直接コントロールできるんです。
スマートフォン向けのアプリ(iPhoneでもAndroidでも使えます)と、パソコンのブラウザで使える拡張機能(ChromeやEdgeなどで利用可能)の2つの形で提供されています。
自分の使い方に合わせて選べるのは嬉しいポイントですね。
Trust Walletはいつ、誰が作ったの?
Trust Walletは、2017年にヴィクター・ラドチェンコさんという方によって作られました。
最初は、イーサリアムという暗号資産と、それに関連するトークン専用のモバイルウォレットとしてスタートしたんです。
ですが、その使いやすさやセキュリティへの意識の高さから、だんだんと多くの人に使われるようになりました。
大きな変化があったのは2018年のことです。
世界的に有名な暗号資産取引所であるBinance(バイナンス)に買収されたんですね。
この出来事によって、Trust Walletは開発に必要な資金やサポート体制がよりしっかりしたものになったと考えられています。
対応できるブロックチェーンやデジタル資産の種類も、ぐんと増えました。
Binanceが提供する広いサービスとの連携も進んで、例えばBNB Chain(以前はBinance Smart Chainと呼ばれていました)への対応はその代表例と言えるでしょう。
ただ、大きな会社に買収されると、ウォレットが中立でいられるのか、特定の会社のサービスに偏ってしまうのではないか、といった声が一部の利用者から出ることもあります。
Trust Walletが目指していること
Trust Walletが掲げている目標は、暗号資産をもっとシンプルで、誰にでもアクセスしやすいものにすることだと言われています。
そして、誰もがWeb3という新しいインターネットの世界へ、安全に参加できるように手助けをすることを目指しているそうです。
その先には、Web3を体験する上で最も信頼される中心的な場所になり、分散型と呼ばれる新しい仕組みの中で信頼の基準を打ち立てたい、という大きなビジョンがあるようです。
これらの考え方は、特にWeb3の新しい技術にこれから触れてみようという人たちにとって、使いやすさや安心感を大切にしている姿勢として伝わってきますね。
Trust Walletの主な特徴と便利な機能
Trust Walletがたくさんの人に利用されているのには、いろいろな機能や特徴があるからなんです。
ここでは、その中でも特に注目したいポイントをいくつか紹介しますね。
たくさんの種類のデジタル資産に対応
Trust Walletのすごいところの一つは、本当にたくさんの種類のデジタル資産に対応している点です。
情報によると、なんと1000万種類以上のデジタル資産と、100を超えるブロックチェーンをサポートしていると言われています。
これには、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった有名な暗号資産はもちろんのこと、ERC-20(イーサリアムをベースにしたトークンの規格)やBEP-20(BNB Chainをベースにしたトークンの規格)といった様々なトークン、それからNFT(非代替性トークン)も含まれているんです。
これだけ幅広く対応していると、利用者は一つのウォレットでいろいろな種類のデジタル資産をまとめて管理できるかもしれません。
そうなれば、複数のウォレットを使い分ける手間が省けて便利ですよね。
さらに、新しく登場したトークンや、まだあまり知られていないプロジェクトの資産を扱いたい人のために、自分でトークンやネットワークを追加する機能も備わっていると言われています。
これは、変化の速い暗号資産業界で、ウォレットの使い勝手を良くするための大切な機能と言えるでしょう。
デジタル資産の送り方、受け取り方、そして保管
Trust Walletは、デジタル資産を送ったり受け取ったりする操作が、直感的に分かりやすいように作られています。
利用者は、資産を受け取るための自分のウォレットアドレスを作って、他の人に教えることができます。
反対に、他の人のウォレットアドレスを指定して、自分の資産を送ることも可能です。
このとき、一番大切な情報である「秘密鍵」は、利用者のスマートフォンやパソコンの中に直接保存される仕組みになっています。
これが、Trust Walletがノンカストディアル(自己管理型)であることの基本なんです。
この仕組みのおかげで、第三者が利用者の許可なく資産に触れることが難しくなっています。
しかし、暗号資産の取引は、一度ブロックチェーンという台帳に記録されると、後から取り消すことができません。
ですから、アドレスの入力ミスなどには、十分に気をつける必要がありますね。
アプリの中で直接デジタル資産を交換できるスワップ機能
Trust Walletには、アプリの中で持っているデジタル資産を別の種類のデジタル資産に交換できる「スワップ機能」がついています。
この機能は、Uniswap(ユニスワップ)やPancakeSwap(パンケーキスワップ)といった分散型取引所(DEX)の仕組みを利用していると言われています。
そのため、利用者はTrust Walletからわざわざ外部の取引所に資産を移さなくても、直接トークンを交換できる場合があるんです。
これは、特にDeFi(分散型金融)を利用する人にとっては、手間が省けて便利な機能かもしれません。
ただし、DEXの仕組みを使ったスワップでは、そのDEXでかかるガス代(ネットワーク手数料)や、スリッページ(注文した価格と実際に取引された価格の差)の影響を受けることを覚えておきましょう。
クレジットカードなどで暗号資産を買える機能
Trust Walletでは、外部の決済サービスを通じて、クレジットカードやデビットカード、またはApple PayやGoogle Payといった方法で、直接暗号資産を購入できるオプションが用意されていることがあります。
これによって、特に暗号資産の取引にまだ慣れていない人が、普段使っているお金(法定通貨)から比較的簡単にデジタル資産を手に入れることができるかもしれません。
Coinbase PayやBinance Payといったサービスと連携することで、すでに持っている取引所の口座から資産を移すことも可能とされています。
しかし、外部の決済サービスを利用する場合、一般的にはKYC(本人確認)やAML(マネーロンダリング対策)といった手続きが必要になることが多いです。
利用するサービスによっては、手数料が少し高めにかかる可能性も考えておいた方が良いでしょう。
持っているだけで報酬が期待できるステーキング機能
Trust Walletは、いくつかの種類の暗号資産について、アプリの中で直接「ステーキング」ができる機能に対応しています。
ステーキングというのは、対象となる暗号資産を持っていることで、そのネットワークの運営に貢献し、その見返りとして報酬を得る仕組みのことです。
BNB、Tezos (XTZ)、Tron (TRX)、Cosmos (ATOM)など、複数の暗号資産のステーキングがサポートされていると言われています。
これによって、利用者は外部のステーキング専用のサービスを使わなくても、Trust Walletの中で手軽に報酬を得るチャンスを探せるかもしれません。
ただし、ステーキングでもらえる報酬の割合や条件、それに伴うリスク(例えば、ネットワークの運営に問題があった場合など)は、それぞれのブロックチェーンのルールによって異なります。
Trust Wallet自体が、これらを管理したり保証したりするわけではないことを理解しておく必要があります。
いろいろなサービスに繋がるDAppブラウザ
Trust Walletには、「DAppブラウザ」という機能が組み込まれています。
DAppというのは、分散型アプリケーションの略です。
このブラウザを使うと、利用者はウォレットから直接、DeFiのサービス、NFTのマーケットプレイス、ブロックチェーンを使ったゲームなど、様々なDAppにアクセスして利用することができます。
これは、広大なWeb3の世界への入り口のようなもので、利用者がいろいろな分散型サービスに参加するのを簡単にしてくれるかもしれませんね。
NFTの管理もこれ一つで
Trust Walletは、イーサリアムやBNB Smart Chainなど、複数のブロックチェーン上で作られたNFT(非代替性トークン)を保管したり、見たり、管理したりすることをサポートしています。
利用者は、内蔵されているDAppブラウザを通じて、OpenSea(オープンシー)やRarible(ラリブル)といったNFTのマーケットプレイスと直接やり取りをして、NFTを買ったり売ったりすることも可能です。
NFTの市場がどんどん大きくなっている中で、ウォレットの中で手軽にNFTを管理できる機能は、NFTを集めている人や取引している人にとって、とても大切な要素の一つと言えるでしょう。
Trust Walletのプラットフォーム モバイルアプリとブラウザ拡張機能
Trust Walletは、主に2つの形で使うことができます。
一つはスマートフォン用の「モバイルアプリ」、もう一つはパソコンのブラウザで使う「ブラウザ拡張機能」です。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
いつでもどこでも使える Trust Wallet モバイルアプリ
Trust Walletのモバイルアプリは、iPhone(iOS)とAndroidのスマートフォン向けに提供されていて、それぞれのアプリストアからダウンロードできます。
設定は比較的簡単で、新しいウォレットを作って、一番大切な情報である12個の単語でできた「リカバリーフレーズ」を安全な場所にメモして保管する、という手順で進められます。
アプリの中では、持っている資産の管理、送ったり受け取ったりする操作、DAppを探して使うことなどができます。
セキュリティを高めるために、指紋認証や顔認証といったスマートフォンの機能も利用できる場合があるようです。
モバイルアプリはTrust Walletの原点とも言えるもので、外出先で資産を管理したり、すぐに取引したりするのに向いていると考えられますね。
パソコンでじっくり使える Trust Wallet ブラウザ拡張機能
Trust Walletは、Chrome(クローム)、Brave(ブレイブ)、Edge(エッジ)、Opera(オペラ)といった、よく使われているウェブブラウザに対応した「ブラウザ拡張機能」も提供しています。
これを使うと、パソコンのデスクトップ環境で暗号資産やNFTを管理したり、DAppと連携したりすることができるようになります。
設定は、ブラウザのウェブストアから拡張機能をインストールして、新しいウォレットを作るか、すでに持っているウォレットをリカバリーフレーズを使って読み込むことで完了します。
特に、複雑なDAppとのやり取りや、大きな画面で細かい操作をしたい人にとっては、ブラウザ拡張機能が便利な選択肢になるでしょう。
モバイルアプリとブラウザ拡張機能、どう違うの?
Trust Walletのモバイルアプリとブラウザ拡張機能は、たくさんのブロックチェーンに対応していたり、NFTを管理できたり、大切な秘密鍵を安全に保管できたりと、多くの基本的な機能を共有しています。
しかし、それぞれは違う使い方や好みに合うように最適化されていると言えます。
モバイルアプリは、内蔵されているDAppブラウザによって、外出先でもスムーズにDAppを使えるように設計されています。
一方、ブラウザ拡張機能はデスクトップでの利用に特化していて、より大きな画面で、ブラウザの中でWeb3の活動をするのに便利なように作られています。
この2つのプラットフォームは、どちらか一つだけを選ぶというよりは、お互いを補い合う関係にあると考えるのが良いかもしれません。
例えば、リカバリーフレーズを読み込ませることで、モバイルアプリとブラウザ拡張機能の両方で同じウォレットを使うこともできます。
これによって、家のパソコンでDAppを利用して、外出先ではスマートフォンで資産の状況を確認する、といった使い分けができるようになります。
ただし、2つの違うプラットフォームで、常に同じ機能や使いやすさを保ち続けるのは、提供する側にとっては継続的な努力が必要な点でもありますね。
Trust Walletのセキュリティについて考える 大切な資産を守るために
暗号資産ウォレットを使う上で、セキュリティは一番気になることの一つですよね。
Trust Walletがセキュリティについてどのように考えていて、どんな機能があるのかを見ていきましょう。
自分で管理する「ノンカストディアル」ってどういう意味?
Trust Walletは「ノンカストディアルウォレット」です。
これは、利用者が自分自身の「秘密鍵」、つまり自分の暗号資産を完全に自分で管理するということを意味します。
Trust Walletを運営している会社は、利用者の秘密鍵やリカバリーフレーズをサーバーに保存することはない、とされています。
この仕組みは、どこか一箇所に情報が集まっているわけではないので、もし万が一、運営会社が破綻したり、一方的に資産が凍結されたりする、といったリスクから利用者を守る可能性があるんです。
しかし、同時に、セキュリティに関する全ての責任が利用者自身にかかってくる、ということも意味します。
「Not your keys, not your crypto(あなたの鍵でなければ、あなたの暗号資産ではない)」という言葉がこの業界でよく使われますが、これはまさにその通りで、自分で管理することは究極の管理権限と自由をもたらす一方で、高いレベルの個人的な責任が求められるんです。
もし、リカバリーフレーズをなくしてしまって、スマートフォンやパソコンにもアクセスできなくなったら、資産を取り戻すことがとても難しくなるか、場合によっては不可能になってしまう可能性が高いのです。
この点は、鍵の管理について利用者自身がしっかりと学んで、慎重に対応することがいかに重要かを示しています。
とても大切なリカバリーフレーズと秘密鍵
暗号資産にアクセスしたり管理したりする上で、一番大切な情報は「リカバリーフレーズ(シードフレーズとも呼ばれます)」と「秘密鍵」です。
これらの情報がもし他の人に知られてしまうと、不正に資金が動かされたり、盗まれたりする危険性があります。
リカバリーフレーズは、ウォレットを作った時に生成される、通常Trust Walletでは12個(場合によっては24個)の単語が連続して並んだものです。
これは、ウォレット全体と、それに関連する全ての秘密鍵を元に戻すための「マスターキー」のような役割を果たします。
ウォレットのバックアップや復元には絶対に欠かせないものです。
秘密鍵は、特定の暗号資産アドレスに対応する、ユニークな文字列のことです。
そのアドレスの中にある資金を管理する権限を与えてくれます。
リカバリーフレーズを使って、これらの個別の秘密鍵が作られる仕組みになっています。
リカバリーフレーズはウォレット全体の究極のバックアップで、個々の秘密鍵はそのウォレットの中の特定の資産アドレスを管理する、という違いを理解しておくことが大切です。
多くの利用者は、主にリカバリーフレーズを安全に保管することに力を注ぐことになるでしょう。
リカバリーフレーズと秘密鍵を守るための具体的な方法
リカバリーフレーズと秘密鍵を安全に管理することは、自分の資産を守るための基本中の基本です。
ここでは、一般的に良いとされている方法をいくつか紹介しますね。
まず、リカバリーフレーズは、紙に正確に書き留めて、インターネットに繋がっていない安全な場所に保管することが基本です。
ハッキングのリスクを避けるために、メールやクラウドストレージ、スクリーンショットといったデジタルな形で保存することはおすすめできません。
CRYPTOTAG(クリプトタグ)のような金属製のプレートに刻印するなど、水濡れや火災にも強い物理的なもので保管することも考えてみる価値があります。
次に、リカバリーフレーズや秘密鍵は、絶対に他の人と共有してはいけません。
Trust Walletのサポート担当者や、その他のどんな正規の組織も、これらの情報を尋ねることは絶対にない、とされています。
もし尋ねられた場合は、それは詐欺の可能性が高いと考えて、決して教えないようにしましょう。
また、物理的なコピーをいくつか作って、それぞれを違う安全な場所(例えば、地理的に離れた場所など)に保管することで、火事や盗難といった予期せぬ事態に備えることも有効です。
テクノロジーを責任を持って使うなら、強力でユニークなパスワードで暗号化されたメモ帳アプリや、信頼できるパスワードマネージャーを、デジタルバックアップの補助として利用することも考えられます。
しかし、その場合でも、オフラインでの物理的なバックアップが一番優先されるべきであることに変わりはありません。
バックアップの方法 手動と暗号化クラウドバックアップ
Trust Walletは、利用者のリカバリーフレーズを守るために、いくつかのバックアップ方法を提供していると言われています。
標準的な方法は「手動バックアップ」です。
これは、利用者が12個のリカバリーフレーズを紙などに書き留めて保管するやり方ですね。
それに加えて、Trust WalletはリカバリーフレーズをGoogle DriveやiCloudといったクラウドストレージにバックアップするオプションも提供している場合があります。
この時、フレーズは利用者が設定したパスワードで暗号化される仕組みになっているとされます。
これは追加の安全策として役立つかもしれませんが、この方法の安全性は、利用者が設定する暗号化パスワードの強さとユニークさ、そして利用者自身のクラウドアカウントのセキュリティに完全に依存します。
もしクラウドバックアップを利用する場合には、他のサービスで使っているパスワードを使い回したりせず、とても強力で推測されにくいパスワードを設定することが非常に重要です。
Trust Walletが提供するセキュリティ機能
Trust Walletは、利用者の資産を守るために、アプリ自体にもいくつかのセキュリティ機能を備えていると言われています。
これらには、アプリを起動する時のパスコード設定、指紋認証や顔認証といった生体認証機能、秘密鍵を守るためのオプションのセキュアエレメントサポート、暗号化バックアップ、プライバシーコントロールの強化、そして「Trust Walletセキュリティスキャナー」などが含まれるとされています。
これらの機能は、スマートフォンやパソコンに保存されたウォレットへの不正なアクセスを防ぐための、追加の保護層として役立つかもしれません。
特に注目したいのが、Trust Walletセキュリティスキャナーです。
この機能は、取引を実行する前に、その内容をシミュレートして、怪しいパターンや、すでに知られている悪意のあるアドレスへの送金などを検出し、利用者に警告を発する機能であると言われています。
これによって、利用者が悪意のあるDAppやコントラクトと、知らずにやり取りしてしまうリスクを減らせるかもしれませんね。
利用する上で知っておきたい一般的なリスク
暗号資産の世界は、残念ながら、詐欺やハッキングのリスクといつも隣り合わせです。
Trust Wallet自体がノンカストディアルで、利用者が鍵を管理する仕組みであっても、利用者がフィッシング詐欺に引っかかったり、ウイルスに感染した端末でウォレットを使ったり、あるいは安全ではないDAppに接続したりすることで、資産を失ってしまう可能性は依然としてあります。
過去には、Trust Walletの利用者の残高が一時的に正しく表示されなくなるという、表示上の不具合が発生し、一部の利用者の間で混乱が起きたことも報告されています。
これはハッキングではなかったのですが、その後問題は解決され、資金は安全だったとされています。
しかし、このような出来事は、どんな金融系のアプリであっても、利用者の信頼を保つためには、迅速で透明性の高い情報伝達がいかに重要であるかを示しています。
利用者は、接続するDAppが本当に信頼できるものなのか、コントラクトアドレスは正しいのかなど、自分自身で確認するなど、常に慎重な行動を心がける必要があります。
ウォレットはあくまでWeb3への入り口であり、接続先の全てのDAppの安全性を保証するものではないのです。
Trust Walletの手数料について知っておこう
Trust Walletを利用する時に、どんな手数料がかかる可能性があるのか、事前に理解しておくことは大切ですよね。
詳しく見ていきましょう。
基本的な利用にかかる手数料
Trust Wallet自体は、暗号資産を送ったり受け取ったりすることや、ウォレットの基本的な機能を使うことに対して、手数料を請求することはない、とされています。
つまり、ウォレットアプリをダウンロードしたり、普通に資産を保管したりする機能の利用は無料であると考えて良さそうです。
ネットワーク手数料(ガス代)って何?
利用者が実際に支払う必要があるのは、主に「ネットワーク手数料(ガス代とも呼ばれます)」です。
これは、トランザクション(取引や送金など)をブロックチェーンという台帳の上で処理して記録するために、そのブロックチェーンネットワークのマイナーやバリデーター(検証する人たち)に支払われる手数料のことです。
Trust Walletが集めるものではなく、利用するブロックチェーンの仕組みによって発生するものなんですね。
ネットワーク手数料の金額は、その時のブロックチェーンの混雑具合や、トランザクションの複雑さ、データの大きさなどに基づいて変わります。
例えば、イーサリアムネットワークがとても混雑している時には、ガス代が非常に高くなることがあります。
SWIFTウォレットと通常ウォレットの手数料の違い
Trust Walletは、利用者のニーズに合わせて、2種類のウォレットタイプを提供していると言われています。
「通常ウォレット」は、これまで説明してきた通り、12個のリカバリーフレーズを使い、トランザクションの手数料は、やり取りするブロックチェーンの基本的なトークン(例えば、イーサリアムネットワークならETH)で支払われます。
一方、「SWIFTウォレット(ベータ版とされています)」は、「アカウントアブストラクション」という技術を使っていて、リカバリーフレーズの代わりにパスキー(生体認証など)でウォレットを復元できるとされています。
また、トランザクション手数料の支払いには、200種類以上の違うトークンを利用できる柔軟性があると言われています。
これは、ガス代のために特定の基本トークンを別に用意する必要がないという点で、便利かもしれません。
ただし、SWIFTウォレットのガス代は、その基盤となる技術のために、通常のウォレットよりも高くなる可能性があるものの、最適化が進められている、とされています。
このSWIFTウォレットは、Web3の複雑な部分を一部隠すことで、より多くの人が利用しやすくなることを目指した機能と言えるでしょう。
Trust Wallet Token (TWT) ってどんなもの?
Trust Wallet Token (TWT) は、Trust Walletのサービスに関連する「ユーティリティトークン」で、主にBNB Smart Chain (BSC) というブロックチェーン上で運用されています。
TWTを持っていると、Trust Wallet内での特定のサービス(例えばDEXスワップなど)の手数料が割引になったり、Trust Walletの将来の方向性に関する運営に参加(提案や投票など)できたり、将来的には限定的な機能にアクセスできたりする、といったメリットが得られる可能性があるとされています。
ただし、これらの使い道やメリットは変わる可能性がありますし、TWTの価値も市場の状況によって変動するので、過度な期待はしない方が良いでしょう。
Trust Walletを始める前に知っておきたいこと 他の人の意見や比較情報
Trust Walletの利用を考えている時に、実際に使っている他の人の意見や、他のウォレットとの比較も参考になるかもしれませんね。
いくつかポイントを見ていきましょう。
実際に使っている人たちの声
多くの利用者からは、Trust Walletが対応している資産の種類がとても多いことや、アプリが軽快に動作すること、アプリの中でスワップ(交換)やステーキングができるのが便利だ、といった点が評価されているようです。
特に、Binanceのサービスとの連携がスムーズである点や、初めて使う人にも比較的わかりやすい画面構成である、という声も聞かれます。
一方で、少し気になる点としては、特にたくさんの種類の資産を持っている場合や、残高を同期する時に、アプリの動作が少し遅く感じられることがある、という指摘や、画面のデザインが長い間あまり大きな変更がない、という意見も見られます。
また、以前はモバイル専用だったことから、スマートフォンのハッキングや紛失に対する不安を感じる利用者もいたようです(現在はパソコンで使えるブラウザ拡張機能も提供されています)。
伝統的な意味での二要素認証(2FA)や、より強固なセキュリティを求める利用者からは、ハードウェアウォレットとの直接的な連携機能がないことを指摘する声もあります。
自分で管理するタイプのウォレットなので、その管理の難しさを感じる利用者もいるようです。
これらの意見は、あくまで個々の利用者の感想です。
利用する環境や目的によって評価は変わる可能性があることを理解しておいてくださいね。
他のウォレットと比べてみると?
Trust Wallet以外にも、たくさんの種類の暗号資産ウォレットがあります。
ここでは、代表的なものとしてMetaMask(メタマスク)とExodus Wallet(エクソダスウォレット)を例に挙げて、Trust Walletとの一般的な違いについて触れてみますね。
Trust Wallet と MetaMask の比較
MetaMaskは、特にイーサリアムとその互換性のあるチェーン(EVM互換チェーンと呼ばれます)のDAppを利用する際に、広く使われているウォレットです。
Trust WalletもMetaMaskも、スマートフォン用のアプリとパソコンのブラウザで使える拡張機能を提供しています。
大きな違いとして、Trust Walletは最初の設定のままでも、Solana(ソラナ)やBNB Chainなど、多くの異なるブロックチェーンをサポートしています。
それに対して、MetaMaskは主にイーサリアムやEVM互換チェーンに焦点を当てていて、他のネットワークを追加するには手動での設定が必要になる場合があります。
NFTのサポートに関しても、Trust Walletはよりスムーズに複数のチェーンのNFTを扱えることを目指しているのに対し、MetaMaskは主にイーサリアムベースのNFTに最適化されていると言われます。
ステーキング機能についても、Trust Walletは複数の暗号資産をアプリ内でステーキングできるのに対し、MetaMaskは主にイーサリアムのステーキングに焦点を当てている傾向があります。
どちらのウォレットもノンカストディアルですが、オープンソース(設計図が公開されていること)の状況については、情報源によって見解が異なる場合があるので注意が必要です。
一般的に、Trust Walletは、手動で設定しなくても幅広い種類の資産をサポートしていたり、ステーキングの選択肢が多かったりすることを求める利用者にとって、より使いやすく、モバイル中心でマルチチェーンに対応した選択肢として位置づけられることが多いようです。
Trust Wallet と Exodus Wallet の比較
Exodus Walletも、多くの種類の資産に対応した人気のソフトウェアウォレットです。
対応している資産の種類の幅広さでは、1000万種類以上に対応するとされるTrust Walletに対して、Exodusは約250から280種類の暗号資産をサポートしていると言われており、Trust Walletの方が大幅に広い可能性があります。
セキュリティの面では、どちらもノンカストディアルのソフトウェアウォレット(ホットウォレットと呼ばれ、インターネットに接続されています)で、パスフレーズやPINコードで保護されます。
手数料に関しては、どちらも基本的な利用は無料とされています。
使いやすさについては、どちらも一般的に分かりやすいと評価されていますが、DAppへのアクセスに関しては、Trust Walletの方がよりスムーズに接続できると言われることがあります。
大きな違いの一つとして、ExodusはTrezor(トレザー)やLedger(レジャー)といったハードウェアウォレット(物理的なデバイスで、より安全性が高いとされます)との連携機能を備えています。
それに対して、Trust Walletには現時点で、そういったハードウェアウォレットとの直接的な連携サポートがないとされています。
高額な資産を持っていて、最大限のセキュリティを求める利用者にとっては、このハードウェアウォレットとの連携ができるかどうかは、重要な判断材料になるかもしれませんね。
これらの比較は、あくまで一般的な傾向です。
各ウォレットの機能や仕様は、アップデートによって変わる可能性があるので、最新の情報を確認することが大切ですよ。
Trust Walletの最近の動きと今後の展望(参考として見てみよう)
Trust Walletは、提供するサービスの範囲を広げたり、利用者の使いやすさを良くしたりするために、継続的に開発やアップデートを行っているようです。
最近では、Cardano(カルダノ)ネットワークのアップグレードへの対応や、Sonic(ソニック、以前はFTMと呼ばれていました)ネットワークの統合、XRPLトークンのサポート開始など、より多くのブロックチェーンに対応するための強化が見られる、という情報があります。
また、ステーキングに関連するアップデートや、他のプロジェクトとの共同キャンペーン、セキュリティスキャナーの機能強化、そして利用者向けの教育的なコンテンツの発信などにも取り組んでいるようです。
Trust WalletのCEOであるエウィン・チェンさんは、将来のビジョンとして、Trust Walletが単なるウォレットから「信頼される仲間」へと進化し、Web3をもっとシンプルにして、利用者が真の所有権を持って安全に活動できるように力を与えることを目指す、と語っていると報じられています。
これは、単に取引をするためのツールを超えて、利用者のWeb3体験全体において、より協力的で欠かせない役割を果たそうという姿勢を示しているのかもしれませんね。
これらの情報は、あくまで現時点での動きや目標であり、将来どうなるかを保証するものではありません。
参考として捉えておくと良いでしょう。
Trust Walletのサポート体制とコミュニティ 困ったときはどうする?
Trust Walletを使っていて何か困ったことがあった場合、どこに相談すれば良いのでしょうか。
公式のサポート体制や、利用者同士のコミュニティについて見ていきましょう。
公式のサポート窓口
Trust Walletの公式なサポートは、主にウェブサイト上にあるFAQ(よくある質問とその回答)のセクションや、「お問い合わせ」フォームを通じて提供されているようです。
また、Telegram(テレグラム)、Twitter (X)、Facebook(フェイスブック)、Instagram(インスタグラム)、YouTube(ユーチューブ)、LinkedIn(リンクトイン)、Discord(ディスコード)、TikTok(ティックトック)といったソーシャルメディアのチャンネルも運営されています。
これらは主に、新しい情報のお知らせや、利用者同士の交流のために使われていると考えられます。
ここで、とても大切な注意点があります。
インターネット上には、Trust Walletのサポートを装った偽の電話番号や連絡先が出回っている可能性があります。
Trust Walletの公式サイト(trustwallet.com)では、電話によるサポートは提供されていない、と明記されている場合があります。
個別のサポートが必要な場合は、公式サイトの中にある「お問い合わせ」ページやFAQを参照するように案内されています。
Trust Walletのサポート担当者が、あなたのリカバリーフレーズや秘密鍵を尋ねることは絶対にありません。
もしそのような要求があった場合は、ほぼ間違いなく詐欺ですので、決して応じないでください。
サポートが必要な場合は、必ず公式サイトからアクセスできる正規の窓口を利用するようにしましょう。
利用者同士で助け合えるコミュニティ
Trust Walletは、たくさんのソーシャルメディアのプラットフォーム上で、活発なコミュニティを形成しています。
特にTelegramやTwitter (X)では、世界中の利用者が集まるグローバルコミュニティだけでなく、特定の地域や言語ごとのコミュニティチャンネルも存在すると言われています。
これらのコミュニティは、利用者同士が情報を交換したり、お互いにサポートし合ったりする場として機能している可能性があります。
困ったことがあった時に、他の利用者の経験談が参考になることもあるかもしれませんね。
まとめ Trust Walletを安全に使うために知っておきたいこと
Trust Walletは、その分かりやすい操作画面、たくさんの種類のブロックチェーンに対応している点、そしてノンカストディアル(自分で管理する)という性質によって、多くの人々にとってWeb3という新しいインターネットの世界への入り口の一つとなり得る暗号資産ウォレットです。
スマートフォンでの使いやすさ、DAppブラウザ、ステーキング機能、そして多くの資産に対応している点は、大きな魅力と言えるでしょう。
しかし、利用するにあたっては、ノンカストディアルであることの責任を十分に理解することが、何よりも大切です。
つまり、あなたの持っている資産のセキュリティは、あなた自身の知識と行動にかかっている、ということなんです。
リカバリーフレーズと秘密鍵の管理は最も重要で、これらをなくしてしまったり、他の人に知られてしまったりすれば、資産を永久に失ってしまう可能性があります。
推奨されているセキュリティ対策をしっかりと行い、フィッシング詐欺やウイルスから自分自身を守るための知識を身につけることが求められます。
また、Trust Walletはソフトウェアウォレット(ホットウォレット)であり、インターネットに接続された環境で使われます。
そのため、ハードウェアウォレット(コールドウォレット)と比較すると、本質的にオンライン上のリスクにさらされやすい、という側面も理解しておく必要があります。
特に高額な資産を長期間保管する場合には、リスクを分散させる観点から、ハードウェアウォレットと併用するなどの方法を検討することも一つの手です。
この記事が、Trust Walletに関する基本的な情報を得て、安全な利用について考えるための一つの助けになれば嬉しいです。
どんなツールを利用するにしても、ご自身で十分に情報を集めて、理解を深め、慎重に判断することが最も重要ですよ。
・アプリ内で資産の送受信、交換(スワップ)、ステーキング、DAppブラウザ利用など多彩な機能を提供します。
・セキュリティの鍵は「リカバリーフレーズ」と「秘密鍵」の自己管理であり、その安全確保が最重要です。
・モバイルアプリとブラウザ拡張機能があり、利用シーンに応じて使い分けや同期が可能です。
・利用料は基本的に無料ですが、ネットワーク手数料が発生し、自己責任での安全対策が不可欠です。
【免責事項】
この記事は、情報提供および学習を目的として作成されており、特定の金融商品や投資行動を推奨・勧誘するものではありません。
暗号資産の取引やウォレットの利用には、価格変動リスク、流動性リスク、ハッキングリスク、システム障害リスク、法的リスクなど、様々なリスクが伴います。
本記事の情報に基づいて被ったいかなる損失についても、作成者および情報提供元は一切の責任を負いかねます。
デジタル資産の取り扱いに関する決定は、ご自身の判断と責任において、十分なリサーチとデューデリジェンス(正当性の評価)を行った上で、慎重に行ってください。
必要に応じて、専門家にご相談されることをお勧めします。
本記事に掲載されている情報は、記事作成時点のものであり、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。 情報は予告なしに変更されることがあります。
【公式情報】
Trust Walletに関する最も信頼性の高い情報は、以下の公式サイトおよび関連ページから入手できます。
- Trust Wallet 公式サイト:https://trustwallet.com/
ウォレットのダウンロード、機能紹介、対応通貨、セキュリティに関する情報、ブログ記事などが掲載されています。
日本語にも対応しています (https://trustwallet.com/ja)。 - サポート・FAQ:https://support.trustwallet.com/
よくある質問への回答や、利用方法に関するサポート情報が提供されています。 - 公式ブログ:https://trustwallet.com/blog
最新のアップデート情報、新機能の紹介、暗号資産やWeb3に関する解説記事などが掲載されています。
重要な注意点
秘密鍵とリカバリーフレーズの管理:
Trust Walletは自己管理型ウォレットであるため、12単語のリカバリーフレーズ(シードフレーズ)の管理が極めて重要です。これを紛失したり、他人に知られたりすると、ウォレット内の資産を永久に失う可能性があります。絶対にオンライン上や他人に共有せず、安全な場所にオフラインで保管してください。
フィッシング詐欺への注意:
Trust Walletや他のウォレットを騙るフィッシングサイトや偽アプリ、偽のサポート担当者からの連絡には十分注意してください。公式サイトのURLを常に確認し、安易に秘密鍵やリカバリーフレーズを入力しないようにしましょう。
これらの情報源をご参照いただくことで、Trust Walletについてより深く理解することができるでしょう。特定の機能や情報についてさらに詳しく知りたい場合は、公式サイト内の検索機能を利用したり、サポートページを参照したりすることをお勧めします。

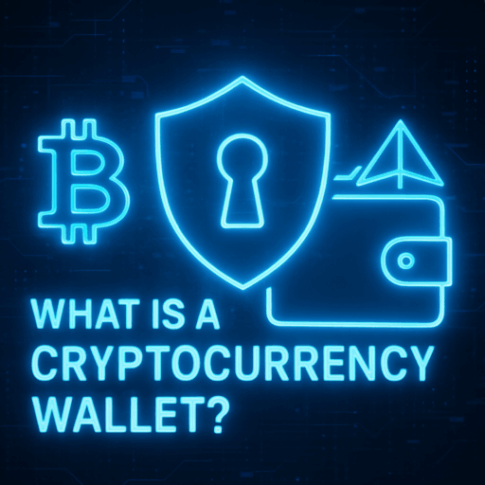










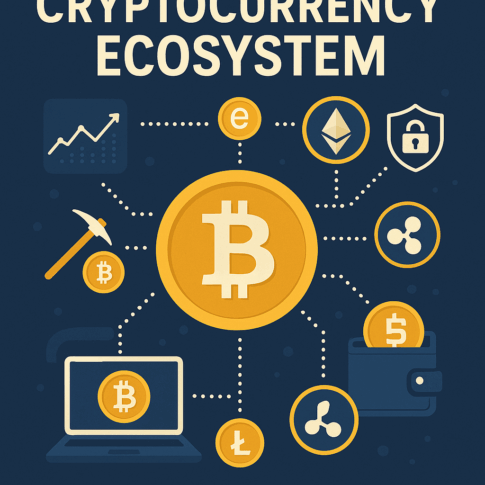



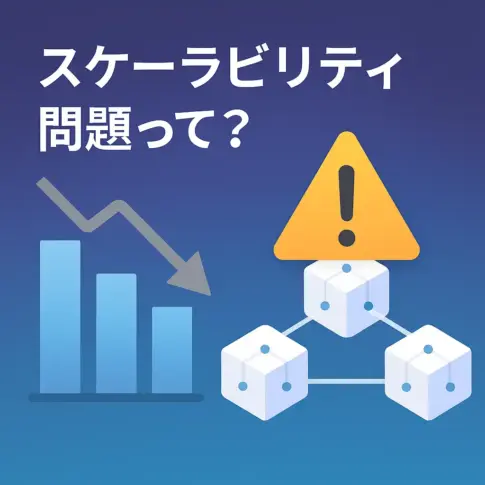






・1000万種以上のデジタル資産に対応!スマホで手軽に一元管理。
・アプリ内で資産交換やステーキングも!便利な機能が満載。
・セキュリティは最重要!自分で資産を守るための秘訣を解説。
・他のウォレットとの違いも比較!自分に合った選択の参考に。